2006年「PMコンピテンシーを高める一冊の本」で取り上げた本
一覧表を作るに当たって、
・プロジェクトマネジメント
・ジェネラルマネジメント
・リーダーシップ(チームマネジメント、組織論などを含む)
・プロフェッショナル
・人間力
・人材開発
・企業もの、開発もの
・思考法・仕事術
の8つのジャンルに分けた。
・のあとは記事のタイトル。
・の代わりに★があるのは各ジャンルで最もよかったと思う本。
【プロジェクトマネジメント】
・プロジェクトレビュー
菊島靖弘「実務で役立つ プロジェクト・レビュー」
・プロジェクトマネジメントベストプラクティス
ジョリオン・ハローズ「プロジェクトマネジメント・オフィス・ツールキット」
・リスクマネジメントの実践
John McManus(富野壽監訳)「ソフトウェア開発プロジェクトのリスク管理」
・PMBOKの次はこれだ!
Project Management Institute「The Standard for Portfolio Management」
・プロジェクトミーティングを改善しよう
中西真人「実務で役立つ プロジェクトファシリテーション」
・マネジメントが先か、プロジェクトマネジメントが先か
林伸二「組織が活力を取りもどす―プロジェクトの立案から監査まで」
・プロジェクトの危機を脱出する
デイビッド・ニクソン、スージー・シドンズ(中嶋秀隆訳)
「プロジェクト・マネジメント 危機からの脱出マニュアル―失敗ケースで学ぶ」
・プロジェクトファシリテーション教本
岡島幸男「プロジェクトを成功させる 現場リーダーの「技術」」
・体系を知り、スキルポートフォリオを作る
プロジェクトマネジメント協会(PMI東京支部訳)
「プロジェクトマネジメント プリンシプル」
・ぴったりサイズのプロジェクトマネジメント
カーティス・R・クック(中西全二訳)「実務で役立つプロジェクトマネジメント」
・これは使える!PMBOKのITプロジェクトの適用の具体的方法
山本需「PMBOK第3版を活用するITプロジェクトマネジメントへの適用と実践」
★プロジェクトマネジメントはサイエンスかアートか
スコット・バークン(村上 雅章訳)
「アート・オブ・プロジェクトマネジメント ―マイクロソフトで培われた実践手法」
・PMツールをベースにした実践的PM力を身につけよう
岡野智加
「Microsoft Projectでマスターするプロジェクトマネジメント 実践の極意」
【ジェネラルマネジメント】
・プロジェクトマネジメントは必要悪か
ジェームズ・フープス(有賀裕子訳)
「経営理論 偽りの系譜―マネジメント思想の巨人たちの功罪」
・コスト削減がプロジェクトを元気にする
村井哲之「社員のやる気に火をつける! コスト削減の教科書」
・MOTはPMの必須科目!~
技術経営コンソーシアム監修、三菱総合研究所編集「標準MOTガイド」
https://mat.lekumo.biz/books/2006/02/post_4aba.html
・PMの必須科目 テクノロジーマネジメントの決定版~
古田健二「第5世代のテクノロジーマネジメント―企業価値を高める市場ニーズと技術シーズの融合」
・現場を動かすマネジャーのノウハウ~
デューク・コーポレート・エデュケーション(嶋田水子訳)
「現場を動かすマネージャーのための『人を活用する技術』」
・マネジメントの原理を学ぼう
D・クイン・ミルズ(アークコミュニケーションズ監修、スコフィールド・素子訳)
「ハーバード流マネジメント「入門」」
・プロジェクトの目的マネジメントの重要性を知る
和田浩子「すべては、消費者のために。―P&Gのマーケティングで学んだこと。」
・プロジェクトの品質は顧客が決める
クリス・ディノーヴィ、J.D.パワーIV世(蓮見南海男訳)
「J.D.パワー 顧客満足のすべて」
・アメーバ型のプロジェクトを作ろう!
稲盛和夫「アメーバ経営―ひとりひとりの社員が主役」
・おとなのマネジメント論
天外伺朗「マネジメント革命 「燃える集団」を実現する「長老型」のススメ」
・技術者のためのマネジメント入門
伊丹敬之, 森健一編「技術者のためのマネジメント入門―生きたMOTのすべて」
★プロダクトマネジャーって何をする仕事!?
Linda Gorchels(新井宏征訳)「プロダクトマネジャーの教科書」
【チームマネジメント、リーダーシップ&組織論】
・PMのためのとっておきの1冊
石田淳(小阪裕司監修)「リーダーのためのとっておきのスキル」
・実務家に実感として分かる組織論
野田稔「組織論再入門―戦略実現に向けた人と組織のデザイン」
・役人とプロジェクトマネジャーの類似性
久保田勇夫「役人道入門―理想の官僚を目指して」
・リーダーがいつも考えるべきことは何か?
マーカス・バッキンガム(加賀山卓朗訳)
「最高のリーダー、マネジャーがいつも考えているたったひとつのこと」
・プロジェクトを熱狂させよう!
デビッド・シロタ(スカイライトコンサルティング訳)
「熱狂する社員 企業競争力を決定するモチベーションの3要素」
・リーダーシップを鍛えよう!
保田健治「ケースで鍛える 人間力リーダーシップ」
・リーダーの悪習慣
山中英嗣「なぜか思考停止するリーダー―MBAホルダーに見るリーダーの落とし穴」
・プロジェクトリーダーシップ~
ジェフリー・クレイムズ(沢崎冬日訳)
「ジャック・ウェルチ リーダーシップ4つの条件」
・サーバントリーダーシップこそ、PMリーダーシップ~
高橋佳哉、村上力「サーバント リーダーシップ論」
・プロジェクトの成功は支持してくれるステークホルダできまる~
サミュエル・ バカラック(坂東智子訳)「統率力。」
・7つの習慣を具体的に実践する~
スティーブン・コヴィー(フランクリンコヴィージャパン訳)
「ビジネスに活かす12のストーリー―「7つの習慣」実践ストーリー<1> 「7つの習慣」実践ストーリー-希望とインスピレーションあふれる- (1)」
・リーダーシップを開発するには~
D・クイン・ミルズ(アークコミュニケーションズ監修、スコフィールド・素子訳)
「ハーバード流リーダーシップ「入門」 」
・リーダーは君だ!~
新里聡「実践リーダーシップ「リーダーは君だ!」―リーダーシップ実践のための12ステップ」
・リーダーシップを行動で解説
グロービス・マネジメント・インスティテュート「MBAリーダーシップ」
・究極の学習理論
ピーター・センゲ他(野中郁次郎, 高遠 裕子訳)「出現する未来」
・コミュニケーションミスが死を招く
是本信義「組織のネジを締め直す鉄壁の「報・連・相」」
・物語でプロジェクトを動かす
平野日出木「「物語力」で人を動かせ!―ビジネスを必ず成功に導く画期的な手法」
・シンボルでリーダーシップを!~
ボイド・クラーク、ロン・クロスランド(田辺希久子訳)
「リーダーの「伝える力」」
・西遊記に学ぶチームマネジメント
成君憶、呉常春(泉京鹿訳)「水煮西遊記 中国ビジネス思想の源流を知る」
・スコープクリープに悩む人に
福田秀人「見切る! 強いリーダーの決断力」
★「個織」(こしき)
眞木準「ひとつ上のチーム。」
・メンバーの上司として心得るべきこと
嶋津 良智「あたりまえだけどなかなかできない 上司のルール」
・強い個とリーダーシップ
平尾誠二「人は誰もがリーダーである」
【プロフェッショナル】
・ビジネス・プロフェッショナル
大久保幸夫「ビジネス・プロフェッショナル―「プロ」として生きるための10話」
★この仕事は他の国ならもっと安くやれるだろうか~
ダニエル・ピンク(大前研一訳)
「ハイ・コンセプト「新しいこと」を考え出す人の時代」
・あなたはプロフェッショナルだといえるか?
波頭亮「プロフェッショナル原論」
【人間力、ヒューマンスキル】
・人間力をつける
ハーヴィ・マッケイ(栗原百代訳)
「ビジネス人間学―「超」のつく成功者になる94の法則」
・PMよ、第1感を鍛えよ!
マルコム・グラッドウェル(沢田博、阿部尚美訳)
「第1感 「最初の2秒」の「なんとなく」が正しい」
・正しいメンタリングの仕方を身につける
渡辺三枝子、平田史昭「メンタリング入門」
・はぐらかしの達人になろう
梅森 浩一「「はぐらかし」の技術」
・面目と調和を保つ交渉術~
ジム・トーマス(安達かをり訳)「パワー交渉術―絶対に成功する21のルール」
・説明できるPMを目指す
鶴野充茂「あたりまえだけどなかなかできない説明のルール」
・PMが定着しにくい理由が理解できる本~
マリヨン・ロバートソン「なぜ「思い込み」から抜け出せないのか」
★シロアリ被害を防げ!
マーク・エプラー(ルディー和子訳)「その無意識の習慣が部下とあなたをダメにする」
・ハーバード流コミュニケーション作法
Harvard Management Update編集部「対話力」
【人材開発、組織開発】
・最高のゴールを目指す
マイケル・レイ(鬼澤忍訳)「ハイエスト・ゴール―スタンフォード大学で教える創造性トレーニング」
・次世代プロジェクトマネジャーの育成をまじめに考える
佐藤達男、伊藤英雄「プロジェクトマネージャ育成法―ITプロジェクトを成功させる人材育成」
・プロジェクトに適した組織活性化方法論
デビッド・L.クーパーライダー「AI「最高の瞬間」を引きだす組織開発―未来志向の“問いかけ”が会社を救う」
・直観力に優れたマネジャーを育てる
児玉光雄「天才社員の育て方」
・PROJECT MANAGERS NOT PMPs
ヘンリー・ミンツバーグ(池村千秋訳)
「MBAが会社を滅ぼす マネジャーの正しい育て方」
★効率よく学ばせ、効率よく業務に活かす
中原淳 (編集)、荒木淳子、北村士朗、長岡健、橋本諭「企業内人材育成入門」
・個性を捨てろ!型にはまれ!
三田紀房「個性を捨てろ!型にはまれ! 」
【企業もの、開発もの】
・ライブドアはプロジェクトである!
株式会社ライブドア「livedoor?何だ?この会社」
・サントリー版プロジェクトX 伊右衛門開発物語~
峰如之介「なぜ、伊右衛門は売れたのか。」
・理屈はいつも死んでいる
高原慶一朗「理屈はいつも死んでいる」
・ヤクザに学ぶプロジェクトマネジメント
山平重樹「ヤクザに学ぶ組織論」
★誰もできないことをやるから面白い
岡野雅行「世界一の職人が教える仕事がおもしろくなる発想法―結果が出ない人はいない」
【思考法、仕事術】
・あるあるマーフィー探検隊!
リチャード・ロビンソン(小林由香利、杉浦茂樹、服部真琴訳)「やっぱり、あるある マーフィーの法則」
・リスクマインド向上のための必読書
坂井優基「パイロットが空から学んだ危機管理術」
・和して同ぜず
T.W. カン「日本企業改革開放論―中国人の上司とうまくやれますか」
・ベタなマネジメント論
芳晶せいじ「人とカネはこうして掴め! 夜王塾」
・持論でやる気を自己調整する
金井壽宏「働くみんなのモティベーション論」
・業務の生産性を上げる習慣
デビッド・アレン(森平慶司訳)
「仕事を成し遂げる技術―ストレスなく生産性を発揮する方法」
・非連続思考でピンチを乗り切る
リュック・ド・ブラバンデール(森澤篤監訳、秋葉洋子訳)
「BCG流 非連続思考法 アイデアがひらめく脳の運転技術」
・独りよがりからの脱却
出口知史「論理思考の「壁」を破る」
・仮説を操れないとPM失格!?
内田和成「仮説思考 BCG流 問題発見・解決の発想法」
・優秀なPMはシナリオを書くのがうまい~
高杉尚孝「問題解決のセオリー―論理的思考・分析からシナリオプランニングまで」
★人やチームの問題解決能力を向上させ、問題を解決する~
ブレア・ミラー、ロジャー・ファイアスティン、ジョナサン・ヴィハー(弓野 憲一、西浦 和樹、南 学、宗吉 秀樹訳)「創造的問題解決―なぜ問題が解決できないのか」
・ストレスを推進力に変える方法
サルバトール・マッディ、デボラ・コシャバ(山崎康司訳) 「仕事ストレスで伸びる人の心理学」
・目を覚ませ!いい仕事こそ、いい人生だ~
スクーリングパッド「ビンタ本」編集制作チーム、黒崎 輝男「ビンタ本」


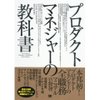

最近のコメント