 よろしければ、あなたの
よろしければ、あなたの
「プロジェクトマネジャーとして一皮むけたプロジェクト(経験)」
を教えてください。
可能なら、コメント欄を使ってください。自分のブログをお持ちの方は、トラックバックでも結構です。
といってもなかなか、ピンと来ないと思いますので、金井先生の「仕事で一皮むける」でケースとして取り上げられているものをリストしておきます。
・管理職になり、団交委員として組合とのネゴシエーションをする
・初の管理職で現場に異動、集団の力と技能の本当の意味を知る
・新規事業の立上げと撤収による人材温存策に腐心する
・「敵塩」ともなるプラント特命で、仮説・検証の重要性を学ぶ
・自分の価値観を押し付けないことと「公私の峻別」を体得する
・事業を起こす「しんどさ」と事業を成功に導く要素を知る
・必要なら客を巻き込む大胆さと正直さの必要性に気づく
・仕事に惚れ込み、悲壮がることなく楽しんでやる大切さを知る
・考えたらただちに行動を起こす「7割正しければ、GO」の必要性を学ぶ
・「心のつながり」と「ひとつの規範にこだわらないこと」の二大教訓
・営業成績最下位の地方支社に赴任、成績をAランクに引き上げる
・青天の霹靂人事で人材開発部長になり、人材開発に新風を吹き込む
・経営の方向付けを通し、部門の物差しを脱して大きな座標軸が獲得できた
・工場のS&Bで、専門を超えて何かを創り上げるダイナミズムを味わう
・リーダーとしてグローバルサプライネットワークを構築する
・営業転出で、旗本直参から尾張百万石の陪臣になったような悲哀を味わう
・課長にを部下に持ち、「個々人に合ったマネジメント」を学ぶ
・プロジェクトリーダーから代表取締役まで、自分の価値を高め続ける
・「あなたに頼んでいるのだ」のひと言が、自分のあり方を変えた
・上司の姿から、仕事への厳しさや妥協しない姿勢を身につける
・経済団体の会長スタッフ業務のなかで、瞬間を掴まえる「呼吸」を会得
・外部研修で、「複眼」でものを見るすごさを知る
といったようなものが並んでいます。業務上の秘密があると思いますので、このレベルで結構です。
ちなみに、好川がひとつあげるとすれば、
「技術士の資格をとり、技術者として自信が出てきた頃に、まったく知らない技術分野の技術開発プロジェクトのプロマネを任され、3年間にわたり、産学の30名くらいの専門家と折り合いをつけながら、非常に楽しくプロジェクト活動を行うことができ、大きな成果を得た」
です。技術者として仕事をし始めて8年目くらいのときのことだったのですが、このときにマネジメントは面白いと思いました。
では、みなさんの経験談をお待ちしています!

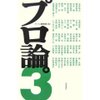


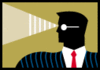






最近のコメント