【補助線】成果、仕事、作業
◆あるメルマガ読者からの質問
お盆休みにあるメルマガ読者から次のような質問を戴いた。質問の中では、プライベートなことも含めて、いろいろなことが書かれているので、編集して、質問だけを再構成する。
定型業務で改善をすることが重要なのはよく分かる。しかし、プロジェクトにおける改善というのはどのような意味があるのか?改善によって本来の達成できないような作業を可能にするというのはそれなりに分かるが、それはリスクを伴うことであって、一概によいとはいえないのではないか?(実際はもっと柔らかい文面でした)
メルマガやブログに、
カイゼンによって、通常はできない目標にチャレンジしよう
ということをよく言っているが、こういう受け止め方をされているのかと知ってちょっと驚いた。なぜ、このように受け止めるのかと考えていて、あることに思い当たった。
◆仕事と作業
仕事と作業の違いがあまりきちんと認識されていないのではないか?
話は変わるが、WBSの「work」という言葉は日本では仕事という意味でも使うし、作業という意味でも使う。このためか、若干、混乱しているように思える。
言葉の定義としては、仕事というのは、解決すべき課題に対して答えを出すことであり、仕事を成し遂げるための手段が作業である。たとえば、
・市場調査をし、商品の機能を設計する
というのは仕事である。これに対して、
・収集されたデータの指定された分析方法で分析する
というのは作業である。ここで注意すべきことは、仕事と作業の間にも仮説があることだ。たとえば、市場データを収集してこういう方法で分析しようというのは、その分析方法によって市場ニーズが抽出できるという仮説を持っているからだ。仮説がないのは定型業務であり、仮説があるのが非定形業務であるといってもよいだろう。
◆成果とはなにか?
さて、もう一つ、考える要素がある。成果だ。成果というのは仕事によってもたらされる。つまり与えられた課題をどの程度解決したか、言い換えると仕事の品質が成果である。ここにも仮説が重要な役割を持っている。
仕事をしてどれだけの成果を上げるかどうかは、この仮説の妥当性によるといってもよい。たとえば、上で引き合いに出した商品開発で、市場調査をしなくても商品を作って市場投入することはできなくはない。しかし、それでは期待する成果が得られないと分かっているので、市場調査という仕事を行うのだ。
WBSというのは成果、仕事、作業(ワークパッケージレベル)の仮説を作るためのツールである。
※仮説について勉強したい人はこちら
◆プロジェクトにおける改善の考え方
さて、改善の話に戻る。
この構造を考えればわかるように、カイゼンには2つのレベルがある。ひとつは、作業レベルの改善である。仕事を行うために、できるだけ無駄なく、作業を組み立てられるように改善をする。ここでは仕事として設定された課題を効率よく解決することが目的であるので、基本的にはリスクは小さくなることはあって、大きくなることはあってはならない。
ここで作業時間が減るので、時間ができる。プロジェクトの場合、この時間の使い方が問題なのだ。どのような仕事を組み合わせれば成果が最大化されるか、この仮説を徹底的にブラッシュアップするためにこの時間を使わなくてはならない。
それによってはじめて、期待以上の成果を上げることが可能になるし、成果目標をストレッチしても実現が可能になる。

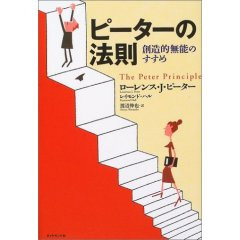
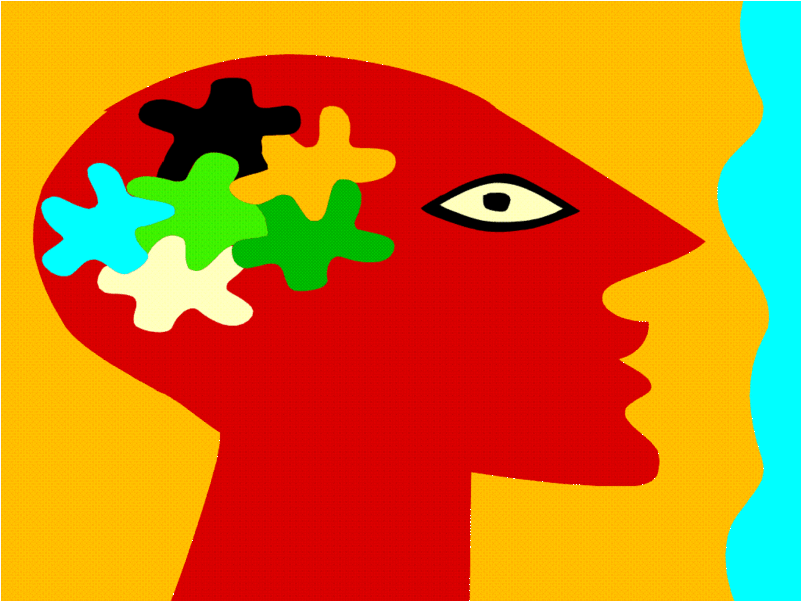

最近のコメント