【補助線】Aクラスのプロマネ。
Aクラスのプロマネ。
大手のSI企業だとどこの企業でも、プロジェクトマネジャー認定制度がある。企業によって差はあるが、おおむね、3~4段階で、段階は実績のあるプロジェクト規模というのが普通だ。
さて、人材マネジメントの世界に目を移すと、Aクラス社員、Bクラス社員、Cクラス社員という区分がある。これもプロジェクトマネジャー認定制度を同じ発想で、能力に着目した区分である。
ところが日本ではこの考え方は合わないのではないかと思うことがよくある。日本の人間観の中には、Bクラスがいるから、Aクラスがいるという人間観は根強くある。つまり、「能力の違いは役割の違いに過ぎない」という人間観がある。さすがに、最近では、CクラスがいるからBやAがいるというのは消えてきたが、僕が就職した頃は、それもアリだったように思う。
ここで言っているCクラスとは「いくら指導しても業績が改善されない」社員のことをいうので、それはもうこのような議論では論外だとしても、AクラスとBクラスは、役割だと考えることが間違いだと言えない部分がある。
一般企業でいえば、Aクラスの集まりだと思われているコンサルティングファームでも、やはり、Bクラスはできる。Cクラスもできるそうだ。そう考えると、組織の中ではBクラスにはBクラスの役割があると考えるのが自然である。
日本の組織の考え方で、強い組織を作るにはBクラス(二番手)が優秀な組織を作るとよいという考え方がある。この一番手、二番手は能力のことを言っているのではないのは明らかだ。能力のことを言っているのであれば、みんながAクラスを目指せばよいからだ。能力以外の何かで優秀なBクラスを必要としているのだ。
という風に考えると、そもそも、バリバリの能力を持った人材がAクラスという定義そのものが怪しくなる。
ここでふと思うのが官僚という人種のことである。明治にできた制度だが、官僚というのは、国を成長させることに目覚めた人たちである。結果として、よく勉強し、優秀な人材が集まるようになった。が、決して優秀なのは官僚だけではない。民間にも優秀な人材はいる。違いは、民間の優秀な人材が自分(自社)の発展だけを考えるのに対して、官僚は国家のことを考えていることだ(皮肉にも、その官僚が自社のことだけを考えるようになって、民間人と同じようになりつつあるようだが、、、)。
これは立場の違いである。
AクラスとBクラスの人材の違いもこれではないかと思う。話は、少しスケールダウンするが、Aクラスの人材は自分の成長の発展を考える。Bクラスの人材はAクラスの人材の描いたビジョンを実行するために自分の成長を考える。能力だけでいえば、Aクラスの人材に勝るとも劣らない人もいる。組織からみて、Aとか、Bとかいうのはそういうことではないかと思う。
さて、そこで、Aクラスのプロマネ。とはどういう人材か?少なくとも、10億のプロジェクトができるのがAクラスで、1億のプロジェクトができるがBではないだろう。もし、本気でそう思っている組織があるとしたら、その組織には明日はないと思う。単なる個人の集まりのような組織に過ぎない。
では、何か?あとは、あなたが考えて、コメントしてほしいと思うが、ヒントは2つあると思う。ひとつは、プロジェクトマネジメント自体を成長させることに目覚めた人だ。もうひとつは、プロジェクトマネジメントを企業の競争優位源泉にしていくことに目覚めた人だ。



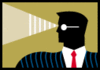




最近のコメント