【補助線】セーラー服と機関銃
3月8日にプロジェクトプロの峯本さんをお招きして、第2回のPMstyleスペシャルセミナーを実施した。今回のテーマ「内部統制とプロジェクトマネジメント」は、あまり、食いつきのよいテーマではなかったが、それでも、30名近くの方にご参加頂いた。お越しいただいた方、本当にありがとうございました。
食いつきの悪かった理由で、何人もから指摘されたのは、「内部統制プロジェクト」の話、あるいは、内部統制プロジェクトのマネジメントの話だと思ったというもの。ある知人が言った言葉が印象に残った。「プロジェクトマネジメントと内部統制」って「セーラー服と機関銃」みたいな印象を受けるテーマだとか。。。むう
だれもプロジェクトマネジメントで内部統制ができるとは思っていない。でも、、、
これは今後の反省点になった。確かに内部統制プロジェクトでもプロジェクトマネジメントは重要だが、内部統制としてのプロジェクトマネジメントはその数十倍重要なテーマだろう。
それはそれとして、峯本さんの話は、今まで僕が聞いた話の中ではもっともプロジェクトマネジメントの話に具体的に言及した話で、主催者としてだけではなく、一受講者としても満足なセミナーだった。
今のブームともいえるような内部統制への関心の高まりの原因になっているのは、いうまでもなく、来年の春から施行される日本版のSOX法である 。なぜ、SOX法という財務会計のシステムの健全性を規制する法律がこんなに関心を集めているかというと、実施基準(評価対象)の中に
(1)財務報告に関する業務プロセス
(2)事業目的に大きくかかわる勘定科目に至る業務プロセス
というものに並んで、
(3)質的に重要な業務プロセス
という一項目があるためである。つまり、いくら財務関連の業務プロセスがきちんとしていても、それ以外の業務プロセスがきちんとしていない限り、問題になるからだ。
先日、ついに、日本での実施基準が明確になった。全般的な印象としては、米国の実施基準と比べて(3)が重視されている印象がある。これは日本人の考え方や、これまでの仕事のスタイルを考えてみると、非常に現実的だし、ある意味で、競争力の源泉になっていくことが予想されるので、評価できる。
中でも注目されるのが、非定型業務が(3)の中でも重視されていることである。非定型業務とはいうまでもなくプロジェクト業務である。言い換えると、J-SOX法が施行されると、プロジェクトマネジメントをきちんとやらないとまずいという状況が発生したわけだ。
いよいよ、日本のプロジェクトマネジメントも正念場を迎える。今までのように、形を作っておけばよいといった状況からの一段の飛躍が必要になる。このテーマは、今後、PMstyleの重要課題として扱っていきたいと思うので、ひとつ上のプロマネ。を目指す方は、ぜひ、押さえておいてほしい!
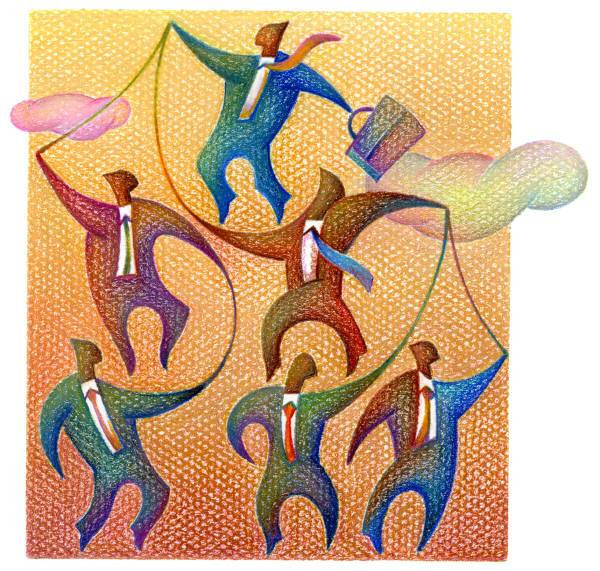



最近のコメント