 トム・デマルコ(伊豆原 弓訳)「ゆとりの法則 - 誰も書かなかったプロジェクト管理の誤解」、日経BP社(2001)
トム・デマルコ(伊豆原 弓訳)「ゆとりの法則 - 誰も書かなかったプロジェクト管理の誤解」、日経BP社(2001)
お奨め度:★★★★1/2
ソフトウエアプロジェクトマネジメントのグルである「トム・デマルコ」の3部作の一冊。「ゆとり(Slack)」がないと、プロジェクトや組織はどうなるかを非常に深い視点から書いている。
3部作におけるデマルコの基本的主張は、ソフトウエアの開発は知識労働であるという点にたっており、現在の肉体労働を前提にしたマネジメント手法では、効果を発揮しないという主張である。その中で、本書は、いくらプレッシャーを与えても生産性はあがらず、生産性を挙げるためには、別の方法が必要であり、その方法として「ゆとり」という概念を持ち出している。
ソフトウエア開発プロジェクトだけではなく、リードタイムがどんどん短くなっていく中で、きわめて重要な指摘ではないかと思う。
ちなみに、3部作残りの2作は以下の2作である。
 トム・デマルコ、ティモシー・リスター(松原友夫、山浦恒央 訳)「ピープルウエア 第2版 - ヤル気こそプロジェクト成功の鍵」日経BP社(2001)
トム・デマルコ、ティモシー・リスター(松原友夫、山浦恒央 訳)「ピープルウエア 第2版 - ヤル気こそプロジェクト成功の鍵」日経BP社(2001)
お奨め度:★★★★★
もう20年前に第1版が出版された本であるが、今、読んでいると、まさに、これから、このような視点が必要になってくるなと思わせる1冊である。この本に書かれていることは、ドラッカーが考える社会観とほぼ同じであり、デマルコは、まさに、IT界のドラッカーともいうべき存在である。
プロジェクトは何よりも「ひと」であり、
・一人一人の人格の尊重
・頭を使う人間にふさわしいオフィス
・人材の選び方・育て方
・結束したチームがもたらす効果
・仕事は楽しくあるべきもの
・仕事を生み出す組織づくり
という6つの視点から「ひと」を中心にしたプロジェクトマネジメントについて説いている。
 トム デマルコ(伊豆原 弓)「デッドライン―ソフト開発を成功に導く101の法則」、日経BP社(1999)
トム デマルコ(伊豆原 弓)「デッドライン―ソフト開発を成功に導く101の法則」、日経BP社(1999)
お奨め度:★★★1/2
この本は、ソフトウエアプロジェクトマネジメント全般に焦点を当てて、物語形式でポイントを述べている。しかし、単に教科書的な本ではなく、そのポイントの示し方に、デマルコの強烈な主張が入っているので、まず、デマルコを読むのであれば、この本から読まれることをお奨めする。
この3部作に加えて、最近、リスクマネジメントに関する本が出版された。こちらは別途、書評があるので、参考にしてほしい。
熊とワルツを

https://mat.lekumo.biz/books/2005/01/post_5.html
==========
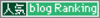 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!
 ジェームズ・リーズン、アラン・ホッブズ(高野 研一、佐相 邦英,、弘津 祐子,、上野 彰)「保守事故―ヒューマンエラーの未然防止のマネジメント」、日科技連出版社(2005)
ジェームズ・リーズン、アラン・ホッブズ(高野 研一、佐相 邦英,、弘津 祐子,、上野 彰)「保守事故―ヒューマンエラーの未然防止のマネジメント」、日科技連出版社(2005)![]() 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!

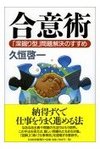
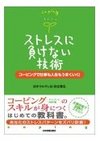
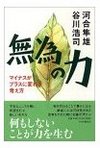







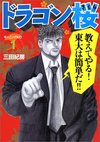
 PM Magazine No.3
PM Magazine No.3


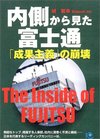







最近のコメント