 リチャード・ニスベット(村本由紀子訳)「木を見る西洋人 森を見る東洋人思考の違いはいかにして生まれるか」、ダイヤモンド社(2004)
リチャード・ニスベット(村本由紀子訳)「木を見る西洋人 森を見る東洋人思考の違いはいかにして生まれるか」、ダイヤモンド社(2004)
お奨め度:★★★★1/2
まず、この本の原題は ”The Geography of thought”である。このタイトルも素晴らしいが、訳者の村本さんのつけられたタイトルはなんと素晴らしいのだろうと感動ものだ。
日本の比喩に「木を見て、森を見ず」という比喩がある。広辞苑によると
細かな点に注意をし過ぎて大きく全体をつかまない
こととある。たぶん、10年くらい前までは、日本人の非常に重要な価値観であったように思うが、今は、あまり言われることがなくなった。
この本では、思考の普遍性に対するパラダイムの議論を、東洋と西洋という切り口からさまざまな視点で行っている。結論としては、普遍性がないということになるが、そこで取り上げられている事象は自分たちの立ち位置を確認するために非常に貴重な視点である。
好川は、第3章にある、自己に関する考察が興味深かったが、その人が興味を持っている事項が一通りを入っているのではないかと思う。
ここでは、米国人は
・ひとはそれぞれ、他者と違う個性を持っている。さらにひとは肝心な点で他者と違っていたいと思っている
・ひとは、だいたいにおいて自分の思うとおりに行動している。そして、自分の選択やこのみによって結果が決まると気分がよい
・・・
というのに対して、東洋では「出るくいは打たれる」というように、成功を集団目標とする傾向があるといった指摘から始まり、実にいろいろなことが指摘されている。
関連記事:森を見るか、木を見るか
==========
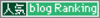 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!
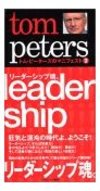
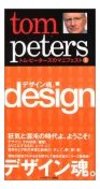
![]() 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!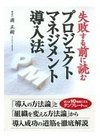








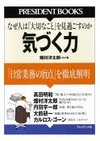




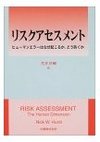


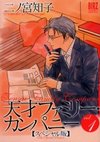
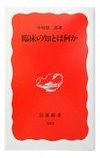







最近のコメント