時間へのスタンスを持とう!

お奨め度:★★★★
ビジネスにおける時間の使い方は効率性ばかり言われるが、例えば、ドラッカーは、「プロフェッショナル条件」の中で戦略性の重要性について説いている。
現実を考えた場合、会社(ビジネス)のレベルでも、個人のレベルでも、効率的であることは重要だが、効率だけでは問題は解決しない。戦略性を持ち、限られた時間の使い方によって成果を大きくしていく努力をする必要がある。特に、プロジェクトのように有期性を前提にしている仕事では、この発想は大切である。
しかし、意外とこれは難しい。時間は無限の資源のような錯覚に陥ってしまうからだ。
もうひとつ、時間に関する問題で重要な問題は、創造性との兼ね合いである。時間の制約は創造性を損ねるのか、それとも、増幅するのか?明確な答えはないが、まったくの無関係ではなさそうである。
この本では、このような時間に関する問題を集めている。ハーバードビジネスレビューであるので、読んですぐに役立つというのはあまり期待しないほうがよいが、プロフェッショナルとして、自分なりに時間に対する「スタンス」を明確に持つためには非常に役に立つ論文が7編掲載されている。
お奨め!
==========
![]() 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!


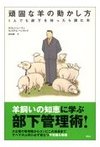



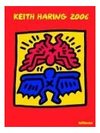
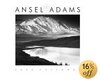







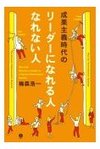




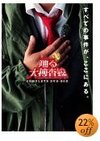


最近のコメント