【補助線】ディライトを提供できるのはプレミアムはプロジェクト
◆プレミアムとは
先日、パソナテック様のITプレミアムという事業のオープニングのセミナーの講師をした。事業内容はパソナテックのホームページを見て戴きたいのだが、こういう分野にプレミアムという概念が持ち込まれるようになったかと思い、多少、驚いた。
ベンツに乗って99円ショップに行くという比喩ではないが、最近の消費財(BtoC)の市場傾向として、二極化と、高級(プレミアム)と低級の使い分けという消費者行動が見られるようになってきたという指摘がよくされる。その中で中級だけが苦戦している。
この市場傾向はしばらく続くと思われるが、問題はプレミアム市場で日本企業はまったくの無力だということだ。プレミアム市場を圧巻しているのは海外企業で、ついでにいえば低級品市場ではもう中国にかなわない。そんな市場構造の中で、中級品のニーズがある海外市場で好況感がでているというのが今の日本企業だろう。
そんな中で、昨年、ローランド・ベルガー会長と早稲田大学教授という二足のわらじをはく遠藤功さんが、「では、どうすれば日本発のプレミアム商品を作れるのか?」をテーマに「プレミアム戦略」という本を書かれた。
「プレミアム戦略」
この本の中で遠藤氏はプレミアムを
「プレミアム」=「機能的価値」+「情緒的価値」
と定義している。
◆プレミアム商品の作り方
そして、海外のプレミアムブランドは、「物語」や「ストーリー」などを駆使し、情緒的価値を作り上げているのに対して、日本のブランドには情緒的価値が希薄であると指摘している。
これまで、中級市場をメインにやってきた企業がプレミアム市場で成功するのは至難の業であるが、今後はなんとかやりきらなくてはならないのだろう。最近の取組で、このような取り組みで最も目につくのはやはり、レクサスである。海外では中級ブランドとして成功を収めているLexusを2005年に日本ではプレミアムブランドとしての展開を始めた。競合ターゲットは、BMW、メルセデス、アウディといったところだ。この取り組みの中では、立派なショールームを作り、きちんとした対応をするととにも、従来にはないメンテナンスサービスを提供遠藤氏の指摘する物語を重視している。
さて、ここで注目したいのは、この情緒的価値は消費材に限ったことかという話だ。
◆生産財におけるプレミアム
生産財では、当然ながら、機能的な価値を徹底的に追及する。機能的価値がその商品を使う顧客のビジネスの生産性に直結するためだ。ところが情緒的価値がないかというと決してそんなことはない。たとえば、信用である。
みなさんの会社にもいると思うが、顧客からの指名されるプロジェクトマネジャーというのは必ずいる。これは機能的価値が評価されているようにも思えるが、マネジメントは技術と比べると複雑であり、技術者が指名されるよりははるかに情緒的価値が高い。
ある企業が、この点に注目をし、指名されるプロジェクトマネジャーのコンピテンシーやスキルに着目し、プロジェクトマネジメント標準の中にプロセス、および、コンピテンシーとして含めたところ、要件定義の問題が発生したプロジェクトが当初の70%から、20%まで削減できたという事例がある。
これこそ、プレミアムである。このシリーズでずっと述べてきているディライトとプレミアムというのは強い関係がある。
ディライトを提供できるのはプレミアムはプロジェクトなのだ。
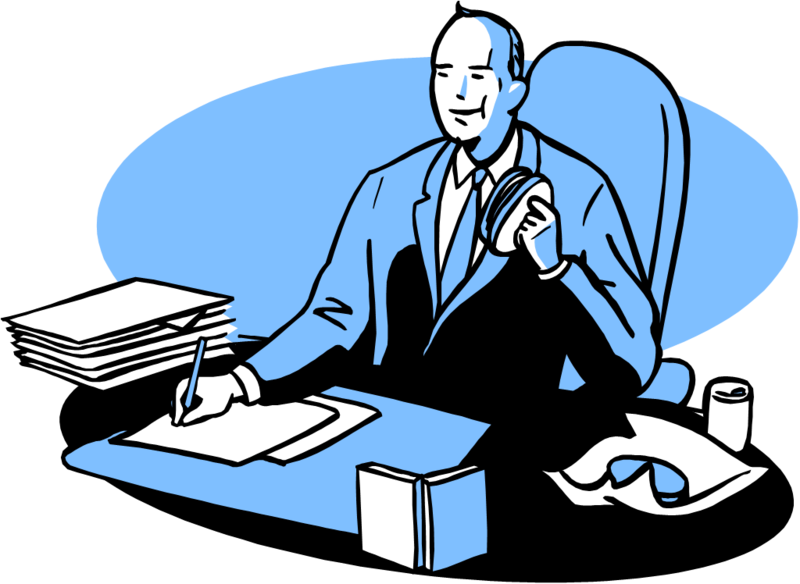
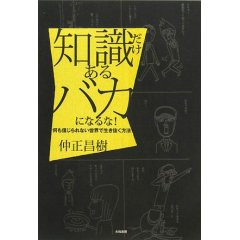

最近のコメント