【補助線】プロジェクト・エグゼクティブ
こういう言葉が、あちこちで見られるようになってきた。PM養成マガジンでも、「エグゼクティブ版」を作った。
非常に単純に定義すれば、プロジェクト(マネジメント)エグゼクティブは、経営的な立場、あるいは組織的な立場で、プロジェクトマネジメントやプロジェクトを統制する立場の人である。例えば、プロジェクト予算の決定権を持つ人、デッドラインに決定権を持つ人といった意味合いである。つまりは、上位組織のマネジャーだということになる。
しかし、そもそもエグゼクティブとは何かと考え出すと話はややこしくなる。ドラッカー博士の本に「経営者の条件」という本がある。多くの著作を残したドラッカー博士の代表作といえる論文集だ。この論文のオリジナルタイトルは「The effective executive」である。
日経BP社の谷島宣之さんにお聞きした話だが、多くのドラッカー作品を翻訳した上田 惇生先生によると、会社役員などをさす言葉ではなく、「人(上司)に言われたこと以上の仕事をする人は新人であろうとエグゼクティブという」というところにドラッカーの真意があるという。従って、日本語では、「できる人」という言葉が適切なのではないかというのが上田先生の解釈だそうだ。
コウビルドには、executiveは
An executive is someone is employed by a "business" at a senior level. Executives decide what the business should do, and ensure that is done.
と説明されている。この説明の中のキーワードはsenior levelである。同じく、
The senior people in an organization or profession have the highest and most important jobs.
とある。
この説明をみればドラッカー博士や上田先生の言っていることはよくわかる。
さて、では、プロジェクトエグゼクティブとはどういう人か?プロジェクトに関して、言われた以上のことをやる人ということになる。この意味は多様である。
・言われた目標以上の成果を達成する人
・言われたスコープの範囲を超えて活動する人
となる。プロジェクト作業はともかく、プロジェクトマネジメントの作業は自分が担当範囲だといわれている範囲を超えないとなかなかうまく行かない。一般的なプロジェクトにおいて、プロジェクトマネジメントを行っているのは、プロジェクトマネジャー、プロジェクトスポンサー、プロジェクトマネジメントオフィス、シニアマネジャー、プロジェクトメンバーである。プロジェクトマネジメントがスムーズにいくためには、これらのプレイヤーのそれぞれが、自分の担当範囲を超えて、言われた以上のことをやる必要がある。
そのような動きができるプロジェクトステークホルダ(PMBOKでいうところの意味)をプロジェクトエグゼクティブというのだろう。
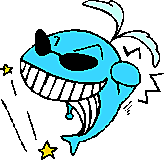

最近のコメント