【補助線】なぜ、日本には女性PMが少ないのか(その2)
PMI東京の女性事務局長・永谷裕子さんに先月からメルマガの記事を書いていただいている。
ITプロジェクトでのDiversity
http://www.pmstyle.biz/column/list.htm
今月の記事の中で、ご自身の欧米でのコミュニティの参加経験から、日本は女性プロジェクトマネジャーが少なく、それを増やすにはどうすればよいかを提案されている。
第2回「ジェンダー(男性・女性)の課題」
http://www.pmstyle.biz/column/diversity/diversity2.html
実は、永谷さんにこの連載をお願いしたきっかけは、1年くらい前になにかの打ち合わせのついでに、ジェンダーダイバーシティの話をしたことだった。
その後で、ブログにこんな記事を書いていた。
なぜ、日本には女性PMが少ないのか
https://mat.lekumo.biz/ppf/2006/08/post_08b3.html
記事は単なる問題提起だが、この問題に対する見解を書いてみる。
プロジェクトマネジャーが少ない原因は大きく分けると2つある。ひとつは、そもそもプールにいないことであり、もうひとつはプールにいても選ばれないことである。永谷さんも書かれているが、前者の問題は組織としての問題であり、現場マネジメントとしては人事施策の効果を待つしかない。
ここでは、後者の選ばれないという問題について考えてみる。女性がプロジェクトマネジャーに選抜されない理由は大きくは3つあると思われる。
(1)プロジェクトスポンサーが使わない
(2)本人がやりたがらない
(3)顧客やエグゼクティブが歓迎しない
の3つ。
(1)はまさにジェンダーダイバーシティの問題であるが、プロジェクトマネジメントにおいては、この問題は解消されている。プロジェクトマネジャーの選抜の仕組みができていれば、これは問題にならない。むしろ、(2)や(3)の問題が絡むのでややこしい。
(2)の問題が意外と多い。ただし、この問題も女性だから云々という問題ではない。男性でもプロジェクトマネジャーになりたがらない人は少なくない。その意味で、これも男女に関係なく、プロジェクトマネジャーになりたいような環境を作っていくことが先決である。これも、まずは、プロジェクトマネジメントをプロジェクト、組織ともきちんと行うことが先決であろう。
もちろん、その段階で女性特有の問題が出てくる可能性がないとはいえないが、今はその段階ではない。
(3)もっとも厄介なのは、実は(3)ではないかと思う。このような場面に今まで何度も遭遇してきた。この問題は根が深い。実は、組織のダイバーシティが最も問われるのはこのような局面ではないかと思う。ダイバーシティのある組織は、顧客やエグゼクティブに対して、リスクをとってでもスポンサーシップを持ってサポートしていく。
そう考えると、結局のところ、現場でのダイバーシティの問題は、リスクをとりたがらないという問題に帰着するのではないかと思われる。
今日は、こんなところにしておく。
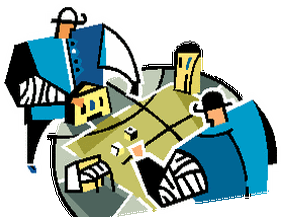
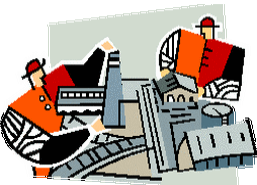

最近のコメント