【補助線】「万人の万人による戦い」は不要か?
学習院大学の内野崇先生の著書「変革のマネジメント」の中に次のような指摘がある。
組織における階層、ルール、ならびに、ルーチン等によって人間は自然状態における「万人の万人による戦い」をまぬがれ(内外のリスクを回避)、その時々の状況および偶発性のみに左右される意思決定を行うことが可能になります
表現が難しいが、難しいことを言っているわけではない。要するに、組織の階層がなかったり、あるいはルールがなければ、組織の成員はすべてのことを全部自分で処理し、問題を解決しなくてはならないが、組織階層やルールによってこれが回避され、節目のところだけをマネジメントしておけば済むようになっているというのが内野先生の言われていることだ。
これは、組織に標準を導入する最も本質的な目的である。
ところが、必ずしも、これを良しとしない文化がある組織が多い。組織も、その成員も、「万人の万人による戦い」をしなくては気がすまないのだ。これはルールに限らず、ものづくりなどでも同じような文化があることが多い。原理的な部分から検証していかないと気がすまない。「使えるものは使う」というのは最終手段であって、できるだけ自力で作ってみる。したがって、恐ろしく時間がかかる。
ただし、これを非効率的だといって否定するというのは少し、違う。トップダウンですべてをものごとを動かしていく覚悟であれば、それでもよいが、このやり方を否定するとボトムアップ力が弱ってくる。つまりは足腰が弱ってくるのだ。
バブル経済の時代にこのようなやり方を否定してきた。ちょうど、今、否定してきたツケが回ってきている時代だと思うが、やはり、機運としては、もう一度、再構築する必要があるという認識が強い。
ちょっと河岸を変えて、ITの世界に目を移すと、この議論は米国でパッケージソフトウエアが登場してきた80年代から延々と続いている。パッケージを使うか、一から作るかという議論だ。この議論にしても、一から作る、あるいはカスタマイズをすることへの非難めいた意見の矢面に立ちながら、カスタマイズをすることをやめようという気配はない。
この議論の本質は、何を目的にしているかにある。米国人にとってはソフトウエアは単なる道具である。問題は道具を使ってどのくらいの付加価値を生むかにあると考えている。
しかし、日本人は「使いこなす」ことを目的にしている。神は細部に宿るという発想があるのだ。つまり、細部にこだわらない限り、価値創造はできないと思っている。この違いはどちらが正しいという次元の違いではない。両方ともそれで成果をあげているからだ。
マネジメントでも同じだ。神は細部に宿ると考えている人は多い。そのような人は、標準に乗っかることは良しとしない。というよりも、「万人の万人による戦い」によって初めて価値創造ができると考えているのだ。
あなたはどう思いますか?

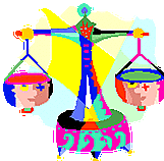
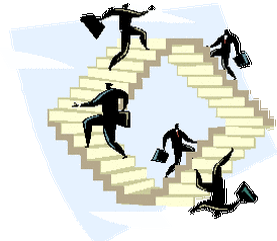
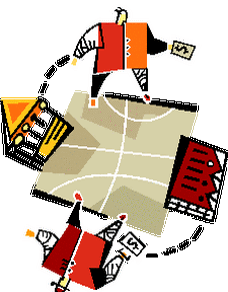
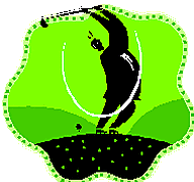

最近のコメント