◆プロジェクトマネジメントにおけるコンプライアンス
米国のプロジェクトマネジメントの本を読んでいると「コンプライアンス」という言葉がよく出てくる(ちなみに、PMBOKにはコンプライアンスという概念は今のところない)。
この言葉は、一般的な用語としては法令遵守などの企業倫理という意味で使われるが、プロジェクトマネジメントの中では多少異なるニュアンスでも使われる(もちろん、企業倫理という意味でも使われるが)。
異なるニュアンスとは、「標準」などの組織内のプロジェクトマネジメントに関するルール遵守という意味で使われる。
◆監査
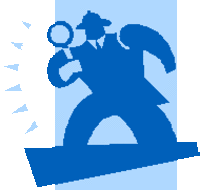 少し話が飛ぶが、コンプライアンスの基盤になるのは「監査」活動である。会計監査、システム監査、環境監査、技術監査、システム監査、セキュリティ監査、品質監査、プロジェクト監査など、いろいろなものに対して適用される活動である。
少し話が飛ぶが、コンプライアンスの基盤になるのは「監査」活動である。会計監査、システム監査、環境監査、技術監査、システム監査、セキュリティ監査、品質監査、プロジェクト監査など、いろいろなものに対して適用される活動である。
監査論の定番書である八田先生の
「監査論を学ぶ」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4495169734/opc-22/ref=nosim
によると監査は
=====
監査とは経済活動と経済事象についての主張と確立された基準との合致の程度を確かめるために、これらの主張に関する証拠を客観的に収集・評価するとともに、その結果を利害関係をもつ利用者に伝達する体系的な過程である
=====
と定義されている。監査というと会計というイメージがあるが、経済活動、経済事象の捉え方によっては、ビジネスの活動はすべて監査の対象になるといってもよい。
では、どうして監査が必要になるのだろうか?
これにはいくつかのポイントが言われているが、最も基本であり重要なものが
「利害の対立」
である。
例えば、企業と株主の場合、情報(決算書)をめぐって利害の対立が発生する可能性がある。利益が多くなれば配当を多くせざるを得ないからだ(もちろん、これを対立にするかどうかはマネジメントの問題だが、本質的な対立要素を含んでいる)。そこで、発信側としては、できるだけ利益を少なく発信したい。粉飾決算といった一線を踏み越える組織も出てくる。
このように、情報の発信者(この場合企業)と受信者(この場合株主)の間に情報をめぐる利害の対立の可能性がある場合には、「第三者」が入って監査を実施し、その情報が適切なものかどうかを明らかにされる必要がある。これが監査の必要性であり、組織として発信する情報の健全性を確保することがコンプライアンスだといってよい。
◆プロジェクト監査とは
さて、このような基本的な枠組みを理解した上で、プロジェクトにおける監査というものについて考えてみたい。まず、この監査の枠組みになぞらえると、プロジェクトの場合は誰が情報発信者で、誰が情報受信者なのか。
情報発信者=プロジェクト(プロジェクトマネジャー)
は分かりやすい。問題は情報受信者である。情報受信者として真っ先に出てくるのは
情報受信者=プロジェクトの成果物を受け取る顧客(社内外)
ということになると思われる。また、エグゼクティブも情報受信者になるだろう。微妙なのは、上位組織のマネジャー(ラインでプロジェクトを行うならラインマネジャー)である。上位組織のマネジャーは多くの場合、プロジェクトスポンサーになることが多い。
ラインマネジャーはプロジェクトスポンサー
http://pmos.jp/pmstyle/pmcoe/pmcoe4.html
従って、プロジェクトチームに片足突っ込んだ存在であるし、スポンサーとしてプロジェクトに対して何らかの統制を行うことも可能である。しかし、実際にはここが情報受信者になっているケースが多い。これはプロジェクトマネジメントの問題点の一つである。これについてはまた、いずれ触れる。
◆監査がプロジェクトマネジメントを成功させる
そのような環境の中で、プロジェクト監査は、プロジェクトマネジメントの状況を第三者的に分析する。その視点はいくつかある。
まず、最初は冒頭に述べたコンプライアンスの視点である。つまり、組織の標準として定められたとおりの手順、基準、ルール、ツールに従って計画が作られているか、進捗が報告されているかといった点である。また、マネジメント判断の中で、メトリクスが遵守されているかどうかも問題になる。ここを担保しなくては監査活動は成立しない。
その上で、プロジェクトマネジメント成果物(計画や進捗ドキュメント)が公正なものであるかどうかである。つまり、進捗報告が規則どおりに行われ、かつ、内容に虚偽がないかどうかをチェックする。
ここが担保されないとプロジェクトマネジメントはできない。プロジェクトの「前提条件」の一つは、プロジェクト作業の担当者が「正しく」にプロジェクトマネジャーに状況を報告し、また、プロジェクトマネジャーが「正しく」に上位マネジャーにプロジェクトの状況を報告することである。この前提条件も監査では分析視点になる。
これで、形式的な健全性は保証されたことになる。この先は標準化がどれだけ進んでいるかによって変わる。標準化の究極の姿は標準手法、ツール、ルール、メトリクスなどに準じて進めていれば健全性が保証されることである。品質など、特定に分野においてはこの形は実現されつつある。
しかし、マネジメント全般になると少し、難しい部分がある。そこで、ある程度、マネジメントの内容に踏み込んだ視点からプロジェクトマネジメントの健全性のチェックが行われるようになる。
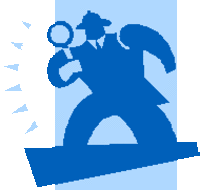



最近のコメント