【補助線】「計画する」とはどういう行動か
この問題、結構、重要なのに考えられていない。
計画することをデスクワークだと考えているプロジェクトはだいたい失敗する。
計画をするとは段取りをすること
である。つまり、計画の対象になる作業を実施する準備をすることである。
こんな例を考えてみて欲しい。
システムの受注開発をする。「計画書」に顧客から仕様が出てくると書く。その計画に基づいて、顧客にそのように対応してもらえるようにお願いをする。当然、顧客には顧客の都合があるので、素直にはウンを言わないが、そこを何とかしながら計画を実行していく。これをステークホルダマネジメントだという。ステークホルダマネジメントの甲斐なく、顧客からはお願いした通りのアウトプットは出てこない。結果として、スケジュールが遅れる。
このような状況はよくあるだろう。どこに、問題があるのだろうか?おそらく、多くの人はステークホルダマネジメントの問題をいうのだと思う。
しかし、このトラブルの本当の問題は、「計画ができていない」ところにある。計画を作るというのは、計画書に書くことのすべてについて、裏づけを取るという作業である。
どうもリスクマネジメントを導入するようになって、裏づけを取らずに、書いたことが実行できないのはリスクだと扱いたがる傾向がある。これはトンでもない間違いだ。
例えば、上の例で、顧客との間で、顧客側の具体的なスケジュールも含めて、合意をし、その通りにやってくれるという確約を取る。これは計画作業に他ならない。段取りだといってもよい。それでも、顧客の方に不測の事態が発生し、できないかもしれない。これがリスクだ。
確かに、ステークホルダマネジメントだとか、コミュニケーションマネジメントだとかが必要だというのはその通りなのだが、本当に必要なのは、計画の実行の中ではなく、計画を作るところである。
このような考え方で、pmstyle のプロジェクトマネジメント(PMBOK準拠)はコミュニケーション計画を立ち上げプロセス群の中で、ステークホルダ分析を行うと同時に策定すべきだとしている。
これがプロアクティブなプロジェクトマネジメントである。
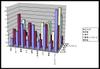

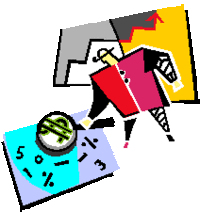

最近のコメント