7つの習慣を具体的に実践する
 スティーブン・コヴィー(フランクリンコヴィージャパン訳)「ビジネスに活かす12のストーリー―「7つの習慣」実践ストーリー<1> 「7つの習慣」実践ストーリー-希望とインスピレーションあふれる- (1)」、キングベア出版(2006)
スティーブン・コヴィー(フランクリンコヴィージャパン訳)「ビジネスに活かす12のストーリー―「7つの習慣」実践ストーリー<1> 「7つの習慣」実践ストーリー-希望とインスピレーションあふれる- (1)」、キングベア出版(2006)
お奨め度:★★★
コヴィーの7つの習慣を12のストーリーで説明している本。7つの習慣は、
主体性を発揮する
目的を持って始める
重要事項を優先する
Win-Winを考える
理解してから理解される
相乗効果を発揮する
刃を研ぐ
というリストを見る分には、「お~、そうだ」と思う。
しかし、本を真剣に読んでみても、なかなか難しいものがある。書いてある内容が難しく、ぴんとこないという人が多いのだ。

スティーブン・コヴィー、ジェームス・スキナー(川西茂訳)「7つの習慣―成功には原則があった!」、キングベアー出版(1996)
昨年、このツール集が出た。フランクリンコヴィージャパンでは、7つの習慣を実行するためのツールを開発して、販売しているが、これを書籍として一般公開したものだ。
 スティーブン・コヴィー「7つの習慣 演習ノート―ビジネス、プライベート、家庭で、効果的な人生を送るための 成功への原則がよくわかる!」、キングベア出版(2006)
スティーブン・コヴィー「7つの習慣 演習ノート―ビジネス、プライベート、家庭で、効果的な人生を送るための 成功への原則がよくわかる!」、キングベア出版(2006)
これをいろいろな人に紹介してみたが、やはり、ファシリテータがいないとツールを使いこなすのは難しいようである。
そこで、今回の本ということになろう。
12のストーリーで説明しようとしているが、いずれもショートショートであるので、これで具体的なイメージを持つのは難しいだろう。
ただし、同じ境遇にあれば、ぴんとくる可能性は多い。タイトルからも分かるようにこれからもシリーズ化をしていくようなので、そのうち、自分の抱えている問題に一致するものがでてくるかもしれない。気楽に待つとよいだろう。
==========
![]() 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!










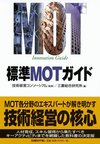

















最近のコメント