プロダクトストラテジー
 マイケル・E・マクグラス(菅正雄, 伊藤武志 訳)「プロダクトストラテジー~最強最速の製品戦略」、日経BP社(2005)
マイケル・E・マクグラス(菅正雄, 伊藤武志 訳)「プロダクトストラテジー~最強最速の製品戦略」、日経BP社(2005)
お奨め度:★★★★1/2
戦略、マーケティングマネジメント、技術マネジメントのバランスがよく取れたプロダクトマネジメントの本。米国のビジネススクールの定番テキスト。
マイクロソフト、IBM、デル、インテル、シスコ、アップル、ゼロックスなどグローバルなハイテク企業は、どうやって競争力のある製品を生み、育てたのかという切り口で、ベストプラクティスとなる戦略パターンを提示している。
製品戦略に留まらず、タイミング、計画立案、コンティンジェンシープラン、マーケティングや資金面での検討事項、などといった製品戦略に付随する様々なプロセスについても言及されているので、非常に実践的な内容になっている。
テキストとして書かれているので、それなりに知識がある人が読むと、説明が冗長であり、まどろっこしい部分があるが、初心者が最初に読み、なおかつ、それなりに深い知識を得るには絶好の本である。
特に、戦略、マーケティングマネジメント、技術マネジメントのバランスについて適切な知識が得られると思うので、プロダクトマネジャーになる人にお奨めしたい本である。













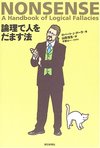



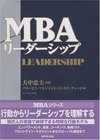






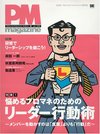


最近のコメント