プロジェクトマネジメント向き問題対処法

お奨め度:★★★★
カウンセリングでは、「問題にとらわれないで、如何に解決に向かうかに焦点を当てる」アプローチは基本の一つである。
最近ではマネジャーを対象にしたビジネスコーチングでも注目されるようになってきた。これは問題解決の対極にあるともいえるアプローチで、どうなりたいか、何を手に入れたいかといった未来のイメージを作るプロセスを先行させ、そこから、具体的な行動を変化させていくアプローチである。
このアプローチをマネジメントに取り入れようというのがこの本の主張である。
ソリューションフォーカスアプローチには3つの哲学がある。
・壊れていないものを直そうとしない
・うまく行っていることを見つけ、それを増やす
・うまく行っていないなら違うことをやる
問題解決志向のアプローチからすれば、ある意味で現実逃避のアプローチにも見えるので批判をする人も多い。しかし、確実にこのようなアプローチが有効な分野がある。それはプロジェクトマネジメントである。プロジェクトマネジメントで問題解決というのはずいぶん重視されている。確かに、次のプロジェクトでの再発を防ぐということを考えた場合には問題解決志向のアプローチは重要だ。しかし、プロジェクトの成功だけを考えるのであれば、問題分析に時間をかけるよりは、ソリューションフォーカスでいろいろと試行錯誤を繰り返していく方がはるかに現実的である。
その意味で、ソリューションフォーカスはプロジェクトマネジャーの必須スキルの一つだろう。
この本では基本的進め方の解説、事例を使ったイメージ作りなどを徹底的に行っているので、必ず、自分のやり方を見つけることができるのではないかと思う。
プロジェクトマネジャーの方、ぜひ、読んでみてほしい。
==========
![]() 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!
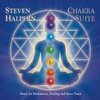
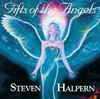

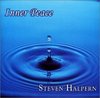




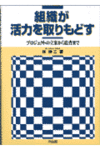



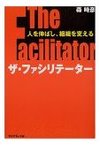





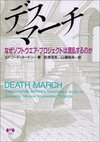
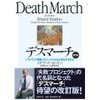


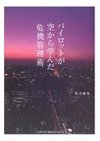







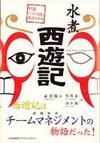

最近のコメント