イノベーションをマネジメントする
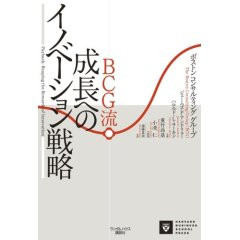 ジェームズ・アンドリュー、ハロルド・サーキン(重竹尚基、遠藤真美、小池仁訳)「BCG流 成長へのイノベーション戦略」、ランダムハウス講談社(2007)
ジェームズ・アンドリュー、ハロルド・サーキン(重竹尚基、遠藤真美、小池仁訳)「BCG流 成長へのイノベーション戦略」、ランダムハウス講談社(2007)
お薦め度:★★★★
この本が指摘し、かつ、答えを準備している問題は非常に重要な部分である。
日本ではイノベーションはマネジメントするものではなく、言い方は悪いが、「アイディア」と「運」だと思っている人が多い。この議論でよく引き合いに出されるのが、20年前にウォークマンを作ったソニーはなぜ、iPodを作り得なかったかという話だ。実は、本書にもこの話は触れられているので、興味ある人は読んでみてほしい。
日本ではと書いたが、この傾向は欧米でも同じような傾向があった。あまりにも、説明できない(不確実な)ことが多く、体系的にマネジメントできるものではないと考えられてきた。
この傾向が変わる契機になったのが「クリステンセンのイノベーションのジレンマ」ではないかと思う。このあたりから、日本でも著名なものでも、クリステンセンの「破壊的イノベーション」、ムーアの「キャズム」、キム氏&モボルニュは「ブルーオーシャン」など、ロジャースが提示したイノベーションモデルでは説明できないような現象を説明するモデルが多くでてきた。
そのような中で、この本はボスコンの体系的なイノベーションマネジメントの手法を紹介するものである。投資マネジメントをキャッシュカーブというフレームワークで合理的に行っていくことによって、不確実性に対処し、最適なゴールを見つけ出し、到達することができるというものだ。
商品開発を担当している人にはぜひ読んでほしいと思うが、この本は単にイノベーションにとどまらず、「マネジメントの価値」を考えさせられる本である。その意味で、すべてのマネジャーにお薦めしたい1冊である。
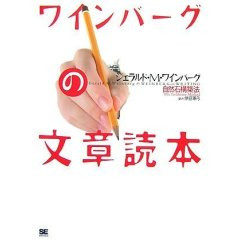
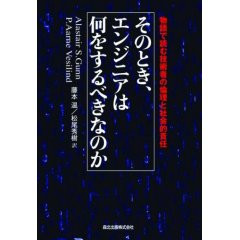
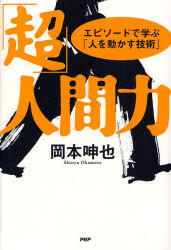

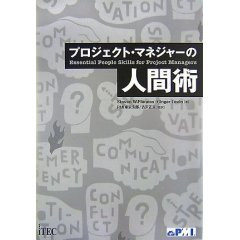
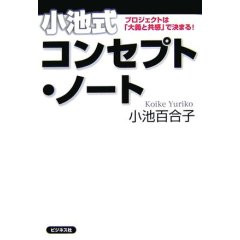
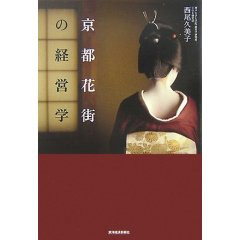
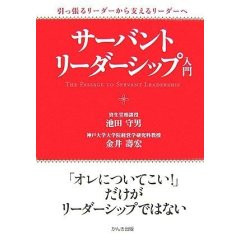
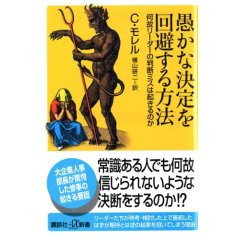
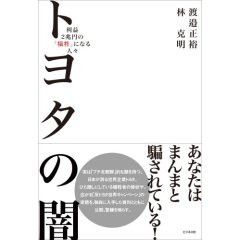
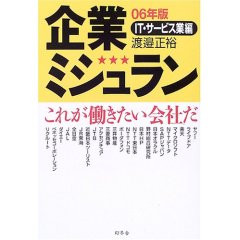
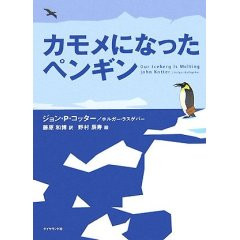
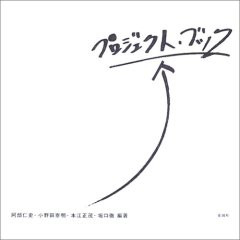
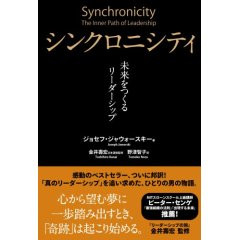
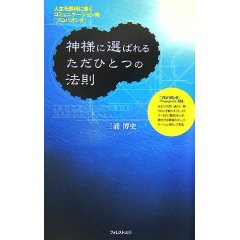
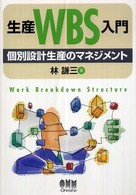
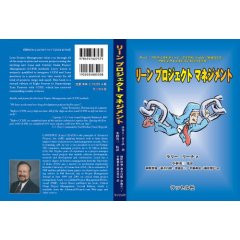
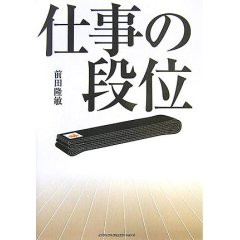
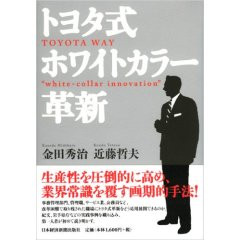
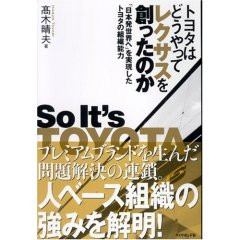


最近のコメント