「主客一体」がビジネスの基本
2008年第1号です。本年もよろしくお願いいたします。 今年のスタートはこの本から。
リクルートワークス編集部「おもてなしの源流 日本の伝統にサービスの本質を探る」、英治出版(2007)
お薦め度:★★★★1/2
リクルートワークスが「おもてなし」とは何かを考えるために、旅館、茶道、花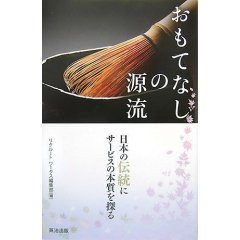 街、祭など「おもてなしの場」を調査し、その道の第一人者の話を聴いた連載「おもてなしの源流」を書籍化したもの。ワークスの連載のときから興味深く読んでいたが、改めて、書籍化され、まとめて読んでみると本質がはっきりしてくる。
街、祭など「おもてなしの場」を調査し、その道の第一人者の話を聴いた連載「おもてなしの源流」を書籍化したもの。ワークスの連載のときから興味深く読んでいたが、改めて、書籍化され、まとめて読んでみると本質がはっきりしてくる。
欧米流のサービスは主と客が分離され、その関係構築に主眼を置く。これに対して、この本があぶりだしている日本のもてなしは、主客の立場が入れ替わることさえ許容し、主と客が共にその場をつくる「共創」の関係を持つことを基本としている。
これは旅館、茶道、花街、祭など、いずれにおいてもその傾向がはっきり見られる。そして、このスタイルを評価し、それを求めて欧米の人々がやってくるという。
非常に興味深い話である。
本書はサービスマネジメントの本として位置づけられているのだと思うが、これらはおそらく、すべてのビジネスにおける主客関係の基盤になっていると思われる。
たとえば、メーカに頼んでものをつくることを考えてみてほしい。メーカとユーザが協力することは比較的あたりまえだととらえられてきた。そうして初めて、ユーザは自分たちが役立つものを手に入れることができると考えらてきたのだ。
これに対して、欧米では、まず、契約ありき。契約で主客と明確にし、それぞれの領分をきちんと守ることによって、メーカは良いものを作ることができ、ユーザは役立つものを作ることができると考えられてきた。
この根底には、専門性に対して社会的な敬意を払い、たとえスポンサーといえどもその専門領域に手を突っ込むべきではないというプロフェッショナリズムがある。
今、日本もまさにこの方向に向かっている。
職人というと、自分の技術に自信を持ち、顧客はそれを対価として受け入れてくれるようなイメージがある。しかし、これは誤ったイメージではないかと思う。鮨屋で「おれの握ったすしが食えねえのか」の世界があるというが、京都のある(有名)鮨屋の店主にそんなのは職人ではないという話を聞いた。職人とは、「相手に悟られないように相手のニーズを聞き出し、そこに洞察を加えて客を満足させることができる」ものだという。ゆえに、無愛想な客と愛想のよい客で、出す鮨の品質が違うのもやむなしだそうだ。だから、客も作法をわきまえている必要があるし、品質を維持するためにわきまえない客は断る。だから、一見さんは断るのだという。これは花街にも通じる話だ。
少なくとも日本流のプロフェッショナルとはこれ、つまり、客と一緒に場を作れる人ではないのか?
そんなことを考えさせてくれる一冊である。



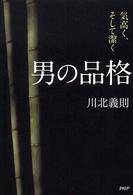

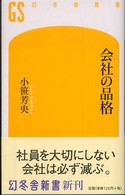
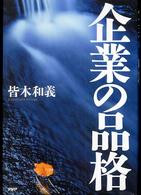
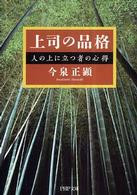
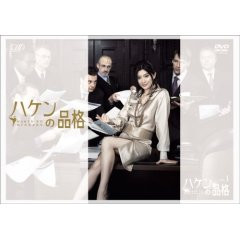
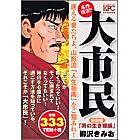
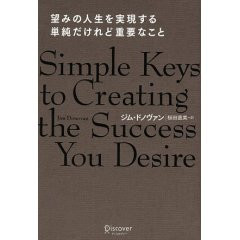
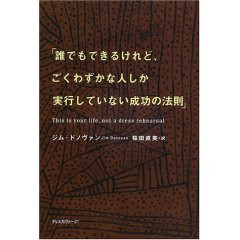
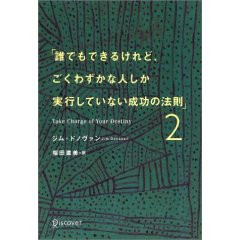
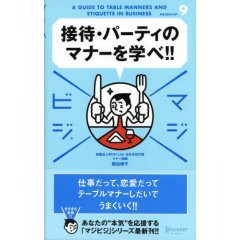
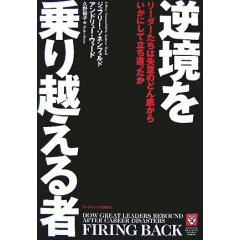
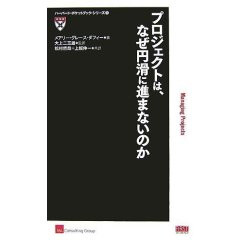
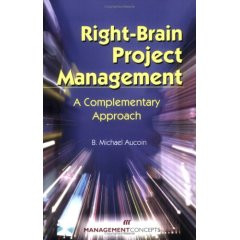

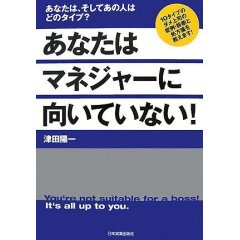
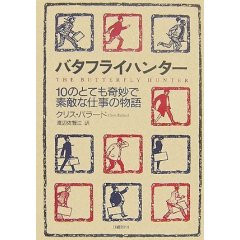

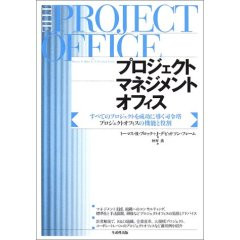
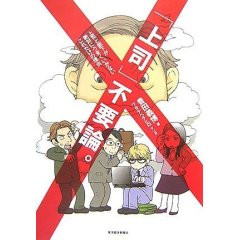
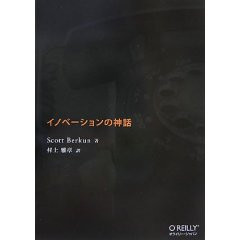
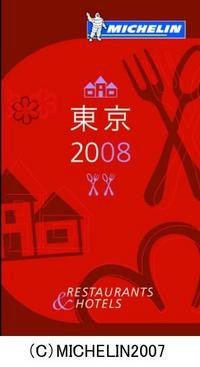
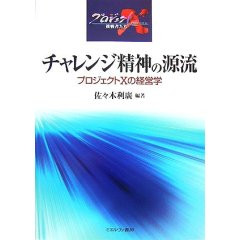
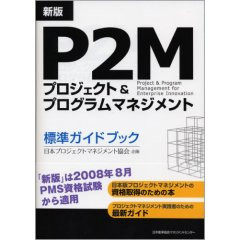
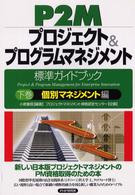
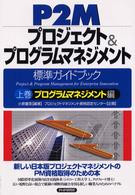

最近のコメント