続・PMOリーダーがPMを変える
◆30%以上の赤字の責任は組織の責任
SI企業のマネジャーと話をしていると彼らが口を揃えていうことに、
「プロジェクトマネジメントが定着してきて、小規模なプロジェクトの納期遅れ、予算超過のプロジェクトの割合は劇的に減った。しかし、それらの努力をすべて帳消しにするような大規模プロジェクトの赤字は依然としてなくならない。 どうしたものだろう」
どうしたものだろう」
という実情がある。もちろん、彼らも手をこまねいているわけではない。原因を分析してみれば、このような大きな赤字プロジェクトもリスクが発見されていなかったとか、まあ、プロジェクトマネジメント導入前に小さな失敗をしていたプロジェクトと同じような原因が並ぶのだ。そこで、なぜ、成功したり、失敗したりするのかという疑問になる。
これはもはや狭い意味でのプロジェクトマネジメントの問題ではない。
◆大きな失敗がなくらならい3つの理由
この問題の大きな理由は3つくらいある。
一番目の理由は、プロジェクトの建て直しの仕方である。プロジェクトマネジメントの基本的な考え方は是正である。つまり、プロジェクトの実績状況が悪くなってきたときに、計画(ベースライン)を変えなくて済むようにアクティビティを変更していく。一言でいえば、問題解決である。
ところが、この種の問題解決はうまく行かないことがある。ベースラインを変えないというのがこの問題解決の制約条件であるが、その制約条件がクリアできる範囲に答えがないことがあるのだ。その場合、制約条件そのものを外してやる必要がある。ゼロベースで如何にしてプロジェクトの目的を達成するかを検討しなおし、目標(計画)設定をしなおす必要がある。
問題は、この判断だ。この判断は体系的に行う必要がある。スケジュールとコスト、品質といった指標だけを見て判断をするのは危険である。プロジェクトマネジャーの状態、チームの雰囲気、メンバーの様子、コミュニケーションの状態、ステークホルダの態度(信用状況)、といったものも見て総合的に判断をしなくてはならない。これは、リカバリーマネジメントでは「リカバリーデシジョンパッケージ」と呼ばれる。
よくある失敗は、例えばスケジュールが30%くらい遅れているときに、チームやステークホルダの状況を見ないで、計算上だけでリカバリーをしてしまうことだ。これが大きな失敗を引き起こす。
この仕組みづくりはPMOの重要な役割である。
二番目の理由はプロジェクトガバナンスの混乱である。ここで、もっとも問題になるのがプロジェクトスポンサーである。プロジェクトスポンサーは、片足プロジェクトチームに足を突っ込んでおり、片足はプロジェクトチームの外にいるステークホルダの役割を果たすプロジェクトガバナンスの安定のために極めて重要な役割である。例えば、プロジェクトマネジャーの任命責任を持つラインマネジャーのような立場の人だ。
ところがトラブルが起こってしまうと、プロジェクトスポンサーが(何とかしようと)混乱して、自らがプロジェクトのガバナンスを不安定にしてしまう。例えば、プロジェクトマネジャーの頭越しにメンバーに対して指示をするとか、顧客と折衝するなどだ。
さらに、悪いことに、プロジェクト全体の司令塔がいなくなることが多い。プロジェクトマネジャーは現実的な顧客やメンバー対応に追われ、スポンサーもガバナンスを持っているという意識はない。結果として、ガバナンス不在のような状態になる。
このようなケースでは、ガバナンスの所在を明確にし、それを適切な人に移行していく。このガバナンスマネジメントはPMOの重要な役割の一つである。
3つ目がエグゼクティブスポンサー(例えば、事業部長)の戦略的判断のミスである。仮に、一つのプロジェクトが組織の年間の利益を吹っ飛ばしてしまうのだとすれば、集中すべきプロジェクトは明確だ。極論すれば、小規模プロジェクトで赤字を出してもいいので、大規模プロジェクトに集中する必要がある。SIなどでいえば、小規模なプロジェクトは少なくとも日本のトップSI企業が受注すべきではない。組織論的に言って、5千万円のプロジェクトを5億円のプロジェクトを同一組織でやることには無理がある。これはリスクマネジメントを考えてみると良く分かる。このようなアンバランスがあると、組織として持つ複数プロジェクトのリスク評価ができなくなる。
このような芸当をやってのけるには、プロジェクトのカテゴライズとカテゴリーごとのマネジメントスキームの確立が不可欠である。この仕事もはやり、PMOの仕事である。
◆PMOの果たすべき役割は大きい
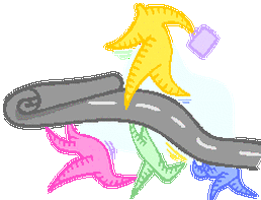 このように冒頭の問題に対して、PMOの果たすべき役割は多い。ここで注目したいことは、これらの仕事は支援の仕事には違いないが、受動的な支援、つまり、依頼されて支援するような類のものではない。むしろ、プロジェクトマネジャーと立場は異なるものの、組織としてのプロジェクトマネジメントの先頭に立って、全体を動かしていくような仕事である。
このように冒頭の問題に対して、PMOの果たすべき役割は多い。ここで注目したいことは、これらの仕事は支援の仕事には違いないが、受動的な支援、つまり、依頼されて支援するような類のものではない。むしろ、プロジェクトマネジャーと立場は異なるものの、組織としてのプロジェクトマネジメントの先頭に立って、全体を動かしていくような仕事である。
今回は、トラブルのケースを考えてみたが、PMOがプロアクティブに動くことによってプロジェクトマネジメントがスムーズにいく部分が多い。これこそ、PMOリーダーの仕事である。
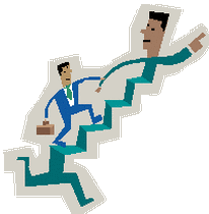
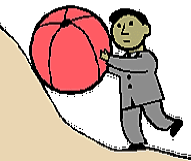
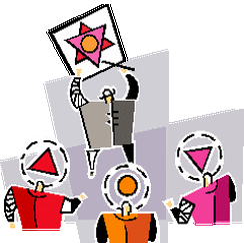
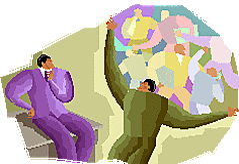

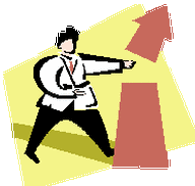

最近のコメント