なぜか柔軟に対応できる戦略を策定する経営企画スタッフ、ヒット商品を連発するマーケッタ、失敗しないプロジェクトマネジャーなど、不確実性のある分野で、非常にうまく、やっている人たちがいる。この人たちに共通するのが、シナリオプラニングを駆使したプラニングである。
最近、(プロジェクト)コンサルティングの中でシナリオプラニングを紹介する場面が増えてきたので、とりあえず、本を整理してみた。
そういう人材を目指す人のために、シナリオプラニングの本を紹介しよう。
 キース・ヴァン・デル・ハイデン(西村行功、グロービス訳)「シナリオ・プランニング「戦略的思考と意思決定」、ダイヤモンド社(1998)
キース・ヴァン・デル・ハイデン(西村行功、グロービス訳)「シナリオ・プランニング「戦略的思考と意思決定」、ダイヤモンド社(1998)
お奨め度:★★★1/2
まず、最初は日本で最初に紹介されたシナリオプラニングの本。
この本はシェルにおけるシナリオプラニングの活用を詳細に説明した本である。背景編ー基礎編ー実践編ー制度編の4部構成になっており、実践的なのだが、抽象度が高い。目前のニーズがないと読了するのはつらいと思う。ただ、かなり、自分の仕事のやり方を考えないと読めないと思うので、最初に読む本としては、この本がよいかもしれない。
 ピーター・シュワルツ(垰本一雄、 池田啓宏訳)「シナリオ・プランニングの技法」、登用経済新報社(2000)
ピーター・シュワルツ(垰本一雄、 池田啓宏訳)「シナリオ・プランニングの技法」、登用経済新報社(2000)
お奨め度:★★★★
シナリオプラニングというのが思考法のように捉えている人も多いが、単なる思考法ではないと思う。おそらく、哲学に近い部分が相当ある。未来とはなにか、不確実性とは何かということを中心に相当考えることがある。その意味で、この本はシナリオプラニングの本質を知るのに良い本。タイトルは技法となっているが、決して技法ではなく、方法論をきちんと述べた本である。
 西村行功「シナリオ・シンキング―不確実な未来への「構え」を創る思考法」、ダイヤモンド社(2003)
西村行功「シナリオ・シンキング―不確実な未来への「構え」を創る思考法」、ダイヤモンド社(2003)
お奨め度:★★★★1/2
シナリオプラニングに関する一番のお奨め本はこの本。上に述べたように本質的に複雑で、抽象的な計画方法であるシナリオプラニングについて、実に分かりやすく、事例をふんだんに使って説明されている。
また、ある程度、プロセスに落とし込んでいるので、実践的な本になっている。とりあえず、シナリオを作ってみようという人にはこの本をお奨めしたい。
 池田和明、今枝昌宏「実践 シナリオ・プランニング―不確実性を利用する戦略」、登用経済新報社(2002)
池田和明、今枝昌宏「実践 シナリオ・プランニング―不確実性を利用する戦略」、登用経済新報社(2002)
お奨め度:★★★★
もう一冊、違った意味で実践的な本を紹介しておく。
実際に戦略策定の中で、実際にどのようにシナリオをプラニングを使いたいかを知りたい人にお奨めの一冊。コンサルティングの中で使っていると思われる、基本概念、構築ステップから、戦略への落し込み、実施体制・スケジュールまでをかなり詳細に解説した一冊。また、日本企業を念頭においた事例も掲載されている。この本も役立つだろう。コンサルタントの人にはこれがお奨め。
 ポール・シューメーカー(鬼澤忍訳)「ウォートン流シナリオプランニング」、翔泳社(2003)
ポール・シューメーカー(鬼澤忍訳)「ウォートン流シナリオプランニング」、翔泳社(2003)
お奨め度:★★★
最後にもう一冊。日本のMBAコースで戦略策定を定型的な手法を使って実施することを教えているコースは少ないと思うが、欧米のMBAコースでは普通に入っている(ちなみに、戦略策定の方法論としてのシナリオプラニングと、戦略実行の方法論としてのプロジェクトマネジメント)。
じゃあ、どんな内容を教えているのかと気になる人にはこの本をお奨めした。ただし、内容的には、上の2冊と較べて、実用性に乏しいが、体系的。知識としてシナリオプラニングを押さえておきたい人には適切な内容の一冊といえるかもしれない。
ということで、どんな目的にシナリオプラニングにアプローチするかによってどの本をお奨めしたいかが決まる。2冊も3冊も読んで何か収穫があるようにも思わないので、とりあえず、自分の目的に適した本を読んでみよう。








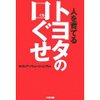









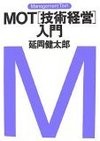


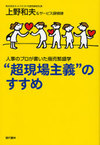

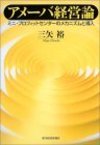
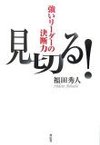




最近のコメント