システム思考で「匠に呪縛」から解放されよう!
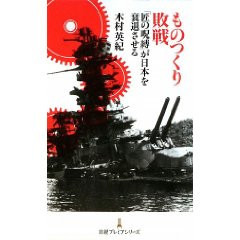 木村 英紀「ものつくり敗戦―「匠の呪縛」が日本を衰退させる」、日本経済新聞出版社 (2009/03)
木村 英紀「ものつくり敗戦―「匠の呪縛」が日本を衰退させる」、日本経済新聞出版社 (2009/03)
お奨め度:★★★★★
日本の技術が苦手なのか、「理論」、「システム」、「ソフトウエア」を3つだという仮説に基づく、システム思考を中核に据えた技術マネジメント論。
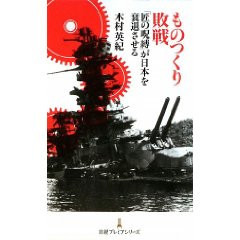 木村 英紀「ものつくり敗戦―「匠の呪縛」が日本を衰退させる」、日本経済新聞出版社 (2009/03)
木村 英紀「ものつくり敗戦―「匠の呪縛」が日本を衰退させる」、日本経済新聞出版社 (2009/03)
お奨め度:★★★★★
日本の技術が苦手なのか、「理論」、「システム」、「ソフトウエア」を3つだという仮説に基づく、システム思考を中核に据えた技術マネジメント論。
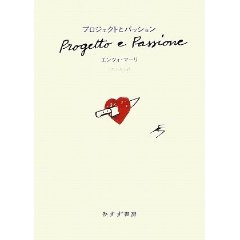 エンツォ・マーリ(田代 かおる訳)「プロジェクトとパッション」、みすず書房(2009)
エンツォ・マーリ(田代 かおる訳)「プロジェクトとパッション」、みすず書房(2009)
お奨め度:★★★★★
イタリアの巨匠エンツォ・マーリのプロジェクトデザイン論。
エンツォ・マーリは伝説的なモダンデザインの工房「ダネーゼ」とのコラボレーションを開始して、世界中に名を覇せた工業デザイナーである。日本では無印良品のデザイナーとして有名である。この本は自身のプロジェッティスタとしての考えをまとめ、後輩に伝えることを目的として書かれたプロジェクト哲学の書である。こういう本を書いてくれる人がいるというのがイタリアだと思わせる一冊。
■■■■■■【目次】■■■■■■
第1章 斧の一撃のものがたり
第2章 三つの地平線
第3章 必要、そしてまた必要
第4章 自然の方法論
第5章 学生へのいくつかの助言
■■■■■■■■■■■■■■■■
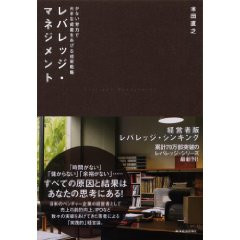 本田 直之「レバレッジ・マネジメント―少ない労力で大きな成果をあげる経営戦略」、東洋経済新報社(2009)
本田 直之「レバレッジ・マネジメント―少ない労力で大きな成果をあげる経営戦略」、東洋経済新報社(2009)
お奨め度:★★★★1/2
帯に「経営者版レバレッジ・シンキング」とあるとおり、レバレッジ・シンキングをマネジメントの中で行うとこうなるというのを書いた本。レバレッジシンキングで展開された考えることによって、労力、時間、知識、人脈にレバレッジをかけて好循環を生み出すという発想が原点になった一冊。
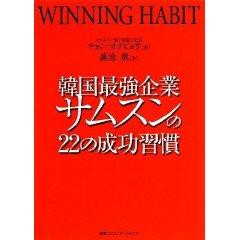 チョン・オクピョウ(蓮池薫訳)「韓国最強企業サムスンの22の成功習慣」、阪急コミュニケーションズ(2008)
チョン・オクピョウ(蓮池薫訳)「韓国最強企業サムスンの22の成功習慣」、阪急コミュニケーションズ(2008)
お薦め度:★★★★★
サムスンの伝説のマーケッタとして知られる、チョン・オクピョウがサムスン流の勝つ企業への変身の秘訣を6章22項目にまとめた本。ひとつひとつが非常に濃い内容で、サムスンの急成長が納得できる。また、蓮池薫さんが翻訳をしているが、翻訳の質が極めて高く、書かれている内容がどんどん吸収できるような感じになる。
 Peter Merholz、Brandon Schauer、David Verba、Todd Wilkens(高橋 信夫訳)「Subject To Change -予測不可能な世界で最高の製品とサービスを作る」、オライリージャパン(2008)
Peter Merholz、Brandon Schauer、David Verba、Todd Wilkens(高橋 信夫訳)「Subject To Change -予測不可能な世界で最高の製品とサービスを作る」、オライリージャパン(2008)
お奨め度:★★★★★
Adaptive Path社の事例を元に、今、多くの企業が直面する「予測不可能な世界で最高の製品とサービスを作る」という問題を真正面から取り上げている。なぜか150ページ強の本に仕上げているが、紹介記事を書くために読み終えるのに4時間もかかってしまった。しかし、4時間でこれだけの内容を読めるというのは、たいへんなことである。そのくらい、よい本。
 小林 英二「マジマネ5 部下の「やる気」を育てる! 」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2008)
小林 英二「マジマネ5 部下の「やる気」を育てる! 」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2008)
お奨め度:★★★★★
新任マネジャーやリーダー向けのマネジメントシリーズ「マジマネ」の5巻。内発的動機付けの重要性を語り、動機付けの方法を具体的に説明している。また、内発的動機と外発的動機の使い分けについても、説明している。
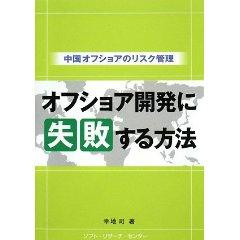 幸地 司「オフショア開発に失敗する方法―中国オフショアのリスク管理」、ソフト・リサーチ・センター(2008)
幸地 司「オフショア開発に失敗する方法―中国オフショアのリスク管理」、ソフト・リサーチ・センター(2008)
お奨め度:★★★★
中国オフショア開発のハンドブック。長く「中国ビジネス入門」というオフショア開発をテーマにしたメルマガを発行し、メルマガ発行のために豊富な取材やサーベイをしている著者らしく、事例や調査データを豊富に掲載するととにも、その背景にある理論を紹介するととにも、問題の具体的な解決策を紹介している。おそらく実践を意識して書かれた本だと思うが、学習にも、読み物としてもと、いろいろなニーズに応えられそうな一冊である。
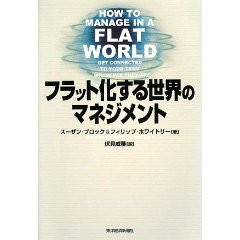 スーザン・ブロック、フィリップ・ホワイトリー(伏見威蕃訳)「フラット化する世界のマネジメント」、東洋経済新報社(2008)
スーザン・ブロック、フィリップ・ホワイトリー(伏見威蕃訳)「フラット化する世界のマネジメント」、東洋経済新報社(2008)
お薦め度:★★★★★
米国に限らず、日本でも業務のグローバル化はどんどん進んでいる。グローバル化の本質はフラット化にある。この点はトーマス・フリードマンが「フラット化する世界」で指摘している。
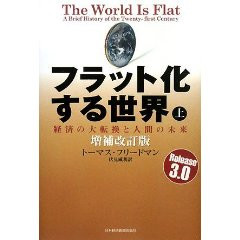 トーマス・フリードマン(伏見威蕃訳)「フラット化する世界(上)、増補改訂版 」、日本経済新聞社(2008)
トーマス・フリードマン(伏見威蕃訳)「フラット化する世界(上)、増補改訂版 」、日本経済新聞社(2008)
この本は、フラット化された世界のマネジメントについて、成功例を参考にしながら、ポイントをまとめている。
グローバルな業務をしているマネジャーには必須といえる一冊。
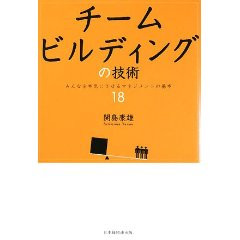 関島 康雄「チームビルディングの技術―みんなを本気にさせるマネジメントの基本18」、日本経団連事業サービス(2008)
関島 康雄「チームビルディングの技術―みんなを本気にさせるマネジメントの基本18」、日本経団連事業サービス(2008)
お奨め度:★★★★★
最近、チームビルディングの本が増えてきた。片っ端から読んでみているのだが、チームビルディングは多面性があり、著者の専門的な視点に偏った説明になっていて、どうも、「盲人が象を語っている」ような感じの本ばかりだった。ということで、これというお奨め本が見当たらなかったが、やっと、象を象として説明している本に出会ったような気がしている一冊。
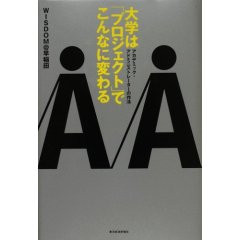 WISDOM@早稲田「大学は「プロジェクト」でこんなに変わる―アカデミック・アドミニストレーターの作法」、東洋経済新報社(2008)
WISDOM@早稲田「大学は「プロジェクト」でこんなに変わる―アカデミック・アドミニストレーターの作法」、東洋経済新報社(2008)
お薦め度:★★★★
プロジェクトとは何だったのかを改めて思い出させてくれる一冊。早稲田大学で、さまざまな変革をプロジェクトとして行っていくために作られたプロジェクトマネジメントのテキストを書籍化した一冊。
最近のコメント