戦略的なプロジェクトのマネジメント
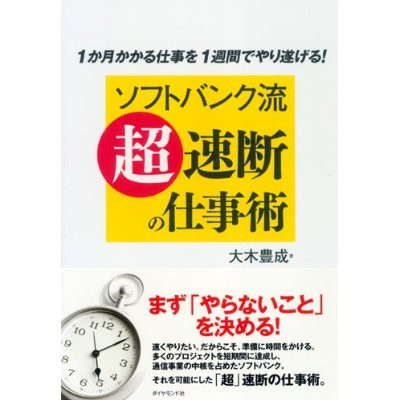 大木 豊成「ソフトバンク流「超」速断の仕事術―1か月かかる仕事を1週間でやり遂げる!」、ダイヤモンド社(2009)
大木 豊成「ソフトバンク流「超」速断の仕事術―1か月かかる仕事を1週間でやり遂げる!」、ダイヤモンド社(2009)
お奨め度:★★★★1/2
久しぶりにプロジェクトマネジャーやプロジェクトスポンサーが読む価値のあるプロジェクトマネジメントの本に出会った。ソフトバンクグループで活躍されている大木豊成氏が、経験に基づき書いた「短納期」、「大規模」なプロジェクト推進方法論。
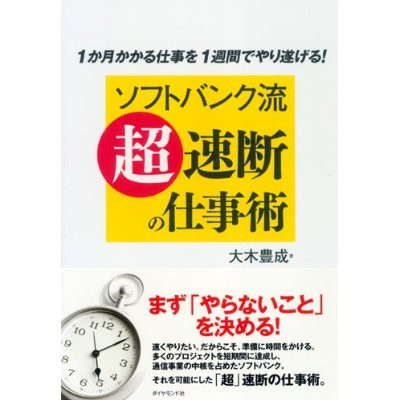 大木 豊成「ソフトバンク流「超」速断の仕事術―1か月かかる仕事を1週間でやり遂げる!」、ダイヤモンド社(2009)
大木 豊成「ソフトバンク流「超」速断の仕事術―1か月かかる仕事を1週間でやり遂げる!」、ダイヤモンド社(2009)
お奨め度:★★★★1/2
久しぶりにプロジェクトマネジャーやプロジェクトスポンサーが読む価値のあるプロジェクトマネジメントの本に出会った。ソフトバンクグループで活躍されている大木豊成氏が、経験に基づき書いた「短納期」、「大規模」なプロジェクト推進方法論。
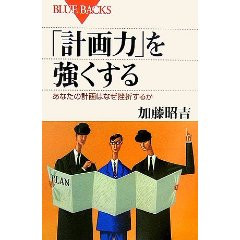 加藤 昭吉「「計画力」を強くする」、講談社(2007)
加藤 昭吉「「計画力」を強くする」、講談社(2007)
お奨め度:★★★★★
「優れた計画を立案し、その通りに 実行したり実行させる能力」と定義した計画力を高める方法を体系的に整理した一冊。
ブルーバックスとしてコンパクトにまとめられており、おそらく読者が知りたい肝心の部分が明確に書かれていないような印象を受けるが、計画力を強くするためには、その部分を自分でいろいろと工夫しながら考え抜き、試行錯誤しろということだろう。むしろ、計画法のフレームワークとしてみれば、よくまとめられた一冊だ。
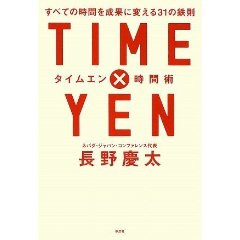 長野慶太「TIME×YEN 時間術 (タイムエン時間術) すべての時間を成果に変える31の鉄則」、草思社(2009)
長野慶太「TIME×YEN 時間術 (タイムエン時間術) すべての時間を成果に変える31の鉄則」、草思社(2009)
お奨め度:★★★★★
時間管理に成果の管理を統合し、具体的な方法論にまで展開した、時間術の本。これまでの時間術本とは一線を画する一冊。
僕は時間術の本は読まない主義であるが、にも関わらず、共感を持って読め、みさなんにお奨めしたい一冊。
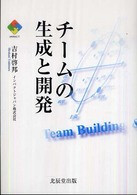 吉村 啓邦「チームの生成と開発」、北辰堂出版(2009)
吉村 啓邦「チームの生成と開発」、北辰堂出版(2009)
お奨め度:★★★★★
チームマネジメントのバイブルといわれる
ジョン・カッツェンバック、ダグラス・スミス(吉良 直人、横山 禎徳訳)「「高業績チーム」の知恵―企業を革新する自己実現型組織」、ダイヤモンド社(1994)
という本がある。この本は300ページ以上ある本だ。ジョン・カッツェンバックなどによって確立されているチームマネジメント論をベースに、自らの新しい知見と実践論を交え、発展させ、200ページ強の本にまとめた密度の濃いチームマネジメント論。
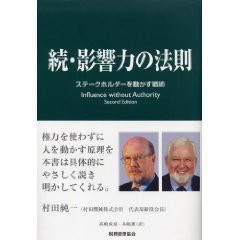 アラン・コーエン、デビッド・ブラッドフォード(高嶋 薫、高嶋 成豪訳)「続・影響力の法則―ステークホルダーを動かす戦術」、税務経理協会(2009)
アラン・コーエン、デビッド・ブラッドフォード(高嶋 薫、高嶋 成豪訳)「続・影響力の法則―ステークホルダーを動かす戦術」、税務経理協会(2009)
お奨め度:★★★★★
2007年に同じ訳者で翻訳出版された「影響力の法則」は、原書「Influnence without Autohrity」の1章~9章を訳したもの。残りの10章~17章を翻訳したのが本書と訳者の前書きに書いてあるのだが、なぜか本書は7章構成。まあ、細かいことは気にしないということで。
また、本書には訳者による影響力の法則ミニセッション的なページが冒頭にもうけられているので、一同、前書を読まなくても読めるようになっている。
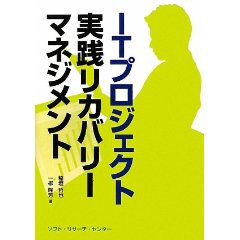 稲垣 哲也、一柳 隆芳「ITプロジェクト実践リカバリーマネジメント」、ソフトリサーチセンター(2009)
稲垣 哲也、一柳 隆芳「ITプロジェクト実践リカバリーマネジメント」、ソフトリサーチセンター(2009)
お奨め度:★★★★
ITプロジェクトのプロジェクトマネジメントの肝要を、成熟度に合わせたリカバリーという視点から整理した一冊。作りとしては、プロジェクトマネジメントの基本的なことを知っている人が、もう少し、専門的な知識を深めるとともに、自分のプロジェクトマネジメントのやり方を振り返り、考えるためにお奨めしたい。
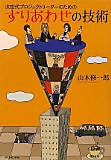 山本 修一郎「次世代プロジェクトリーダーのためのすりあわせの技術」、ダイヤモンド社(2009)
山本 修一郎「次世代プロジェクトリーダーのためのすりあわせの技術」、ダイヤモンド社(2009)
お奨め度:★★★★
今年になって、すりあわせをテーマにした本が2冊出版された。
そのうちの一冊がこの本。この本は、新規ビジネス開発をテーマに、その中核となるシステムの開発を行う様子を物語仕立てで描いたもので、その中で「すりあわせ家」が専門家の対立や協同をうまく調整しながらプロジェクトを成功に導いていくというもの。
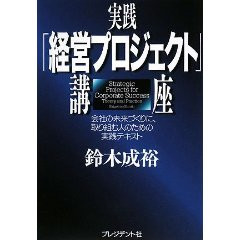 鈴木 成裕「実践「経営プロジェクト」講座―会社の未来づくりに、取り組む人のための実践テキスト」、プレジデント社(2008)
鈴木 成裕「実践「経営プロジェクト」講座―会社の未来づくりに、取り組む人のための実践テキスト」、プレジデント社(2008)
おすすめ度:★★★★★
偶然、書店で見つけて、一気に読んだ。こんな本があるとは知らなかった。
「プロジェクト」を経営でどのように活用し、それを成功させるには、どのようなマネジメント、組織、リーダーシップ、人材が必要かをタイトルの通り、実践的に説明している。
現代経営技術研究所というコンサルティング会社の経営者が、これまでに行ってきた数百の経営プロジェクトに基づき執筆した書籍で、研修テキストとして活用することを目的に書かれたようだが、単独の書籍としても十分に役立つ説明がされており、いわゆるテキスト本ではない。
 石川 和幸「チームマネジメントがうまくいく成功のしかけ」、中経出版(2009)
石川 和幸「チームマネジメントがうまくいく成功のしかけ」、中経出版(2009)
お奨め度:★★★★1/2
チームマネジメントとプロジェクトマネジメント。相性がよさそうなのだが、実は、結構、取り合わせが難しい。プロジェクトマネジメントのライフサイクルと、チームのあり方について明確な関連付けがされていないためだ。
この背景にはチームマネジメントに対する位置づけがある。PMBOK(R)では、チームマネジメントはパフォーマンスマネジメントの手段であって、MUSTではない。スコープマネジメントの方法にもよるが、チームが形成されていなくでもできるように分担するのが計画するという仕事である。
しかし、この議論には見過ごしてはならない前提がある。
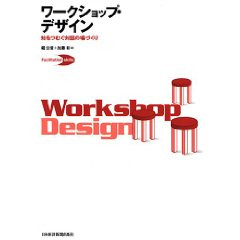 堀 公俊、 加藤 彰「ワークショップデザイン――知をつむぐ対話の場づくり」、日本経済新聞出版社(2008)
堀 公俊、 加藤 彰「ワークショップデザイン――知をつむぐ対話の場づくり」、日本経済新聞出版社(2008)
お奨め度:★★★★1/2
ワークショップという言葉を日常的に耳にするようになってきた。ワークショップはすばらしいという効能もだんだん言われるようになってきた。そこで、やろうと思うと、「さて、、、」となるのではないかと思う。イメージはなんとなくあるが、具体的にどうすればよいか全くわからないので、戸惑う。こんな話も時々、聞くようになった。
そこで、この本。ワークショップのプログラムに焦点を当て、どのように設計するかから、ちょっとした小技(アクティビティ)まで、体系的にまとめられている。
最近のコメント