
ピーター・M. センゲ:「最強組織の法則―新時代のチームワークとは何か」、徳間書店(1995)
お奨め度:★★★★★
組織学習のバイブル。組織がシステムであることを正視させる本。組織論の分野でも大きな影響を与えている1冊である。
この本では、学習する組織では
自己マスタリー(personal mastery)
メンタル・モデルの克服(mental models)
共有ビジョン(shared vision)
チーム学習(team learning)
の5つの原理と、これらを統合するシステム思考(systems thinking)の5つの原理が必要だと述べている。
組織論として、ひとつの理論だが、ビジネスシステムという概念で企業やビジネスを見た場合、本書のような視点で組織を捉える意味は大きく、また、発展性がある。90年代終わりからずっとビジネス、とりわけ組織に大きな影響を与えてきた1冊であるが、真価がはっきりするのはむしろ、これからかもしれない。
ビジネスマンとしては、ぜひ、読んでおきたい1冊である。
また、この本には、2冊のフィールドブックがある。
 一冊は5つの法則を如何に適用していくかを解説した本である。
一冊は5つの法則を如何に適用していくかを解説した本である。
ピーター・センゲ(柴田昌治訳)「フィールドブック 学習する組織「5つの能力」 企業変革を進める最強ツール」、日本経済新聞社(2003)
フィールドブックであるので、5つの原則が何を言っているのかが具体的な行動像を通じてよく分かる。もちろん、フィールドブックとして実際に使えるようなレベルのものである。
もう一冊は、5つの原則を実行するために、組織にはどのような変革課題があるかを解説し、その課題を解消するためのフィールドブックがある。上のフィールドブックとの関係としては問題解決編 という位置づけになっている。
という位置づけになっている。
ピーター・センゲ(柴田昌治、牧野元三、スコラコンサルト訳)「フィールドブック 学習する組織「10の変革課題」―なぜ全社改革は失敗するのか?」、日本経済新聞社(2004)
学習する組織の構築の具体的なヒント、フィールドワークの指針も得られる貴重な本だ。必ず併せて読みたい。
(初稿:2005年3月2日)
==========
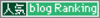 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!
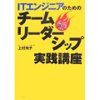
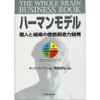
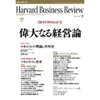





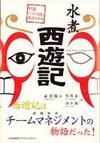





最近のコメント