組織コミットメントの構造
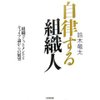 鈴木 竜太「自律する組織人―組織コミットメントとキャリア論からの展望」、生産性出版(2007)
鈴木 竜太「自律する組織人―組織コミットメントとキャリア論からの展望」、生産性出版(2007)
お奨め度:★★★★1/2
新進気鋭の組織論の研究者が、一般の人に向けて書いた組織コミットメント論。組織論の専門家でなくてもわかる言葉で、非常に研究者らしい視点からかかれており、一般的な啓蒙書に比べると考えさせられる部分が多い。
帯に以下のような質問がある。
・希望に溢れた新入社員のコミットメントが2~3年で低下し、その後、持ち直すのはなぜか
・いやな会社でも長く居れば居るほど、転職しづらく感じるのはなぜだろうか
・チームで勝利するためには、スタメンのやる気ではなく、補欠選手のモチベーションを上げるのが有効なのはなぜか
・成果主義を徹底すると、職場の生産性が落ちてしまうのはなぜだろうか?
といった興味半分で知りたいことは、深刻な問題まで解く鍵がコミットメントにあるというのがこの本で紹介されるさまざまな研究からわかる。特にキャリア論から、コミットメントについて考察している。
人事担当者だけではなく、マネジャーやプロジェクトマネジャーならぜひ、読んでおきたい一冊だ。


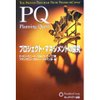
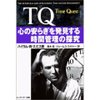
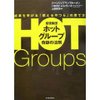
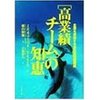
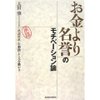

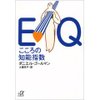







最近のコメント