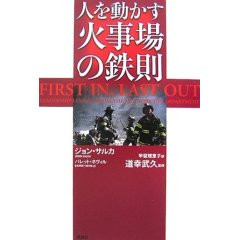 ジョン・サルカ、バレット・ネヴィル(道幸武久監修、甲斐理恵子訳)「人を動かす 火事場の鉄則」、講談社(2007)
ジョン・サルカ、バレット・ネヴィル(道幸武久監修、甲斐理恵子訳)「人を動かす 火事場の鉄則」、講談社(2007)
お奨め度:★★★★1/2
2004年に9・11テロの際にニューヨーク消防局のリーダーであったジョン・サルカが1冊の本を出して話題になった。日本でも、ビジネス誌で紹介されているのを見たことがある。
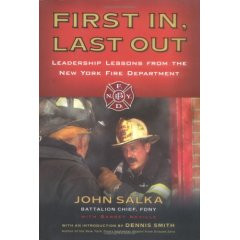 John Salka、Barret Neville「First In, Last Out: Leadership Lessons from the New York Fire Department」、Portfolio(2004)
John Salka、Barret Neville「First In, Last Out: Leadership Lessons from the New York Fire Department」、Portfolio(2004)
という本である。文字通り、最初に飛び込んで最後まで残るという行動規範(プロデュースした道幸氏の言葉では率先垂範)に基づくリーダーシップについて述べた本だ。
この本、読みたかったのだが、思わぬ形で翻訳が出た。翻訳というのは正しくないかもしれない。今、話題の新進気鋭のビジネスプロデューサ 道幸 武久氏が、単なる翻訳としてではなく、自らとのコラボレーション本としてプロデュースしたのだ。
消防士のように極限で、迅速な判断を要求される業務では、一人ひとりがリーダーシップを持たなくてはならない。リーダーや、マネジャーだけがリーダーシップを持っていても、全体は回っていかない。ジョン・サルカ氏のリーダーシップ論は、そのようなリーダーシップ論であり、そのような伝統的なリーダーシップがニューヨーク消防局にはあったので、多くの人を死なさずに助けることができた。
このようなリーダーシップこそ、プロジェクトを成功させるリーダーシップである。
このリーダーシップ論に共感する道幸 武久氏も、負けずと持論を展開し、全体として非常によくまとまった本になっている。この本の構成はオリジナルの本に章単位で道幸氏の章が混じっているような構成になっている。実は、最初、余計なものが入っている(失礼!)と思って、オリジナルの部分だけを選って読んだ。そのあとで、全部を通して読んだが、全部読んだ方がよい本だということがわかった。道幸氏の企画力はさすがである。
この本はいわゆるリーダーに読んで欲しい本なのだが、それ以上に、メンバーの立場で仕事をしている人と、管理職の立場で仕事をしている人にぜひ、読んで欲しい一冊である。
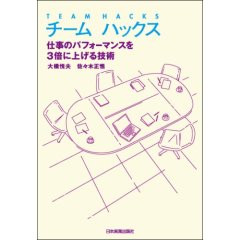 大橋悦夫、佐々木正悟「チームハックス 仕事のパフォーマンスを3倍に上げる技術」、日本実業出版社(2007)
大橋悦夫、佐々木正悟「チームハックス 仕事のパフォーマンスを3倍に上げる技術」、日本実業出版社(2007)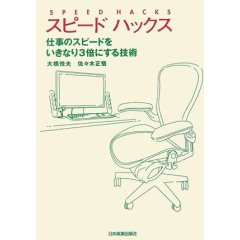
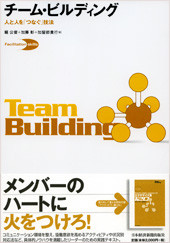
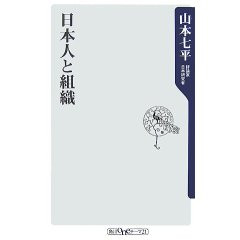
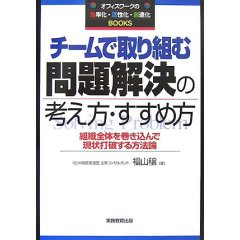
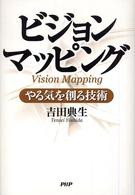
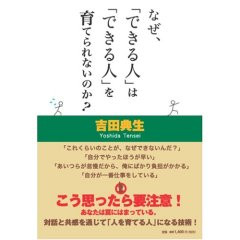
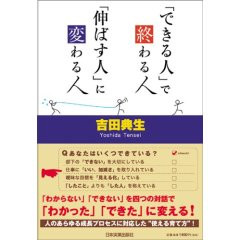
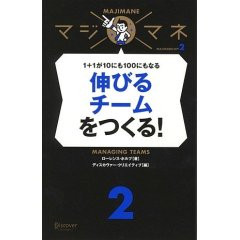
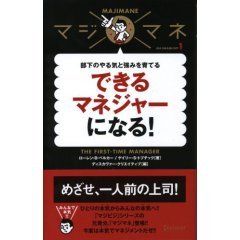
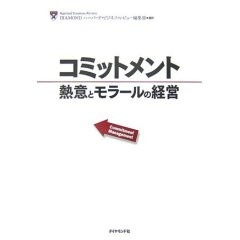
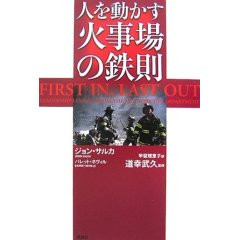
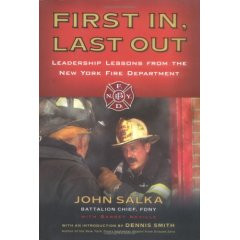


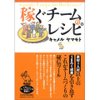

最近のコメント