 ヘンリー・ミンツバーグ(池村千秋訳)「MBAが会社を滅ぼす マネジャーの正しい育て方」、日経BP社(2006)
ヘンリー・ミンツバーグ(池村千秋訳)「MBAが会社を滅ぼす マネジャーの正しい育て方」、日経BP社(2006)
お奨め度:★★★★1/2
ご存知、ポーターなどと並ぶマネジメントのグルであるミンツバーグのマネジャー育成論。ミンツバーグは単なる机上の理論を振りかざすタイプの学者ではなく、論理的な言論の一方で、「マネジャーの仕事」という一級のエスノグラフィーを書いているくらい、現場に精通している。そのミンツバーグのマネジャー育成論なので、非常に期待して読んだが、期待に反しなかった。
現在のMBA方式によるマネジャーについて客観的な評価をし、マネジャー育成のあるべき姿を模索している。マネジメントに必要な要素を
・アート
・サイエンス
・クラフト
という三角形で表し、この3つが補完することがマネジメントの成功要素だとした上で、現在のMBAの教育をクラフトが完全に抜け落ち、かつ、アートに関しては重要を認識するものの教育プログラムとして何もできていないという評価をしている。
この評価をベースにしてマネジャー育成理論を展開しているが、その中で、面白い問題提起が2つある。
一つは、マネジャーの育成のためには行動が必要なのか、行動を省察する機会が必要なのかという問題提起。ミンツバーグの答えは後者である。マネジャー育成の目的を「行動させる」ことではなく、「行動の質を高めること」だとしている。
この問題提起は面白い。MITのピーターセンゲの組織学習論以来、マネジャーの育成にはアクションラーニングが不可欠なものだと考えられるようになってきている。アクションとラーニングという2つの極めて重要な課題をこなすのは難しく、行動と学習の混同をやめにすべきかも知れないと述べている。
もう一つの注目すべき指摘は、マネジャー育成の対象者である。マネジャー育成のための教育は現役のマネジャーに限定すべきであると述べている。理由は理解レベルと、意欲なのだが、ちょっと驚くべき見解である。
そのようなことも踏まえて、新しいマネジャー教育に対して5つの定石を示している。
定石1:マネジメント教育の対象は現役マネジャーに限定すべきである
定石2:教室ではマネジャーの経験を活用すべきである
定石3:優れた理論はマネジャーが自分の経験を理解するのに役立つ
定石4:理論に照らして経験をじっくり振り返ることが学習の中核をなす
定石5:コンピテンシーの共有はマネジャーの仕事への意識を高める
定石6:教室での省察だけではなく、組織に対する影響からも学ぶべきである
定石7:以上のすべての経験に基づく省察のプロセスを折り込むべきである
定石8:カリキュラムの設計、指導は、柔軟なファシリテーション型に変える
そして、この本ではこの定石に基づき、よくできた育成プログラムの紹介と、具体的な教育の概念設計を示している。
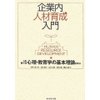 中原淳 (編集)、荒木淳子、北村士朗、長岡健、橋本諭「企業内人材育成入門」、ダイヤモンド社(2006)
中原淳 (編集)、荒木淳子、北村士朗、長岡健、橋本諭「企業内人材育成入門」、ダイヤモンド社(2006)
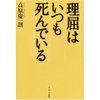
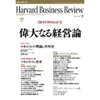
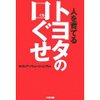
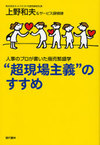





最近のコメント