ビジネス・プロフェッショナル
 大久保幸夫「ビジネス・プロフェッショナル―「プロ」として生きるための10話」、ビジネス社(2006)
大久保幸夫「ビジネス・プロフェッショナル―「プロ」として生きるための10話」、ビジネス社(2006)
お奨め度:★★★★
リクルートワークス研究所の大久保所長の新著。ワークス研究所ではここ何年か、プロフェッショナルを共通研究テーマにしている。個別のテーマの成果は都度「Works」で発表されているが、その集大成のような本。
新しい概念として、「ビジネス・プロフェッショナル」という概念を提案している。プロフェッショナルという言葉の最も狭い定義は、職業独占をしている資格を持つ人だと思う。例えば、建築士のような資格である。
これに対して、一番広い定義は、「その道のプロ」といった言い方がされるような人を指す言葉で、何か、課題を自己責任において、相手が満足できるようなレベルで達成できる人のことだろう。ビジネス・プロフェッショナルという概念はどちらかというとこれに近い。例えば、プロのサラリーマンという言い方があるが、そのような感じだ。
さて、この本だが、冒頭に述べたようなワークス研究所の研究の集大成のような位置づけになっているので、プロフェッショナルを目指す個人に向けた話と、プロフェッショナルな組織を作る人事系の人に向けた話がごちゃ混ぜになっているような感じがある。
個別には、どちらの側面からも非常によくまとまっており、説得力があるので、どちらの分野の人にもぜひ読んで欲しいのだが、その点をきちんと整理して読んでいく必要がある。
特にお奨めしたいのが、個人の方には第3話~第8話。これは、大久保所長が2年暗い前に書かれた
 「仕事のための12の基礎力~「キャリア」と「能力」の育て方~」、日経BP社(2004)
「仕事のための12の基礎力~「キャリア」と「能力」の育て方~」、日経BP社(2004)
を視点を変えて、補強したような内容になっている。分かりやすさという点では、こちらの本を併せて読まれた方がよいかもしれない。
人事系の人へお奨めしたいのは、第1話と第9話である。
プロフェッショナリズムというのは本来組織が雇用者に対して求めるものではない。利用すべきものであり、そのための仕組みがプロフェッショナル制度である。その当たりをもう一度、考えながら読んでみて欲しい。
==========
![]() 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!







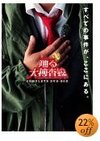
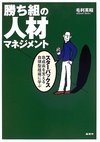




最近のコメント