ドラッカー「マネジメント」の本質が理解できる、エンターテイメント
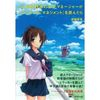 岩崎 夏海「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」、ダイヤモンド社(2009)
岩崎 夏海「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」、ダイヤモンド社(2009)
お奨め度:★★★★1/2
放送作家から、ビジネスのマネジャーへという異色のキャリアを持つ著者が、ドラッカーの「マネジメント」を高校野球という舞台で実践する様子をエンターテイメントとして書いた一冊。
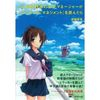 岩崎 夏海「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」、ダイヤモンド社(2009)
岩崎 夏海「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」、ダイヤモンド社(2009)
お奨め度:★★★★1/2
放送作家から、ビジネスのマネジャーへという異色のキャリアを持つ著者が、ドラッカーの「マネジメント」を高校野球という舞台で実践する様子をエンターテイメントとして書いた一冊。
 ディック・ルー、ケン・ブランチャード、ポール・メイヤー(門田 美鈴訳)「なぜ、ノウハウ本を実行できないのか―「わかる」を「できる」に変える本」、ダイヤモンド社(2009)
ディック・ルー、ケン・ブランチャード、ポール・メイヤー(門田 美鈴訳)「なぜ、ノウハウ本を実行できないのか―「わかる」を「できる」に変える本」、ダイヤモンド社(2009)
人々をうまく動機づけ、動かす方法について、単純な真実を成功を収めた作家がいた。作家の本はみんながいいと思い、100万部以上売れた。しかし、作家には一つだけ困ったことがあった。「あなたの本はすべて読んでます。とても気に入っています」という読者に、「それであなたの行動はどう変わりましたか?」と聞くとほとんどの人が返答に困ることだ。
分かっているのに、行動できない
本書の著者は、「1分間マネジャー」を初めとする、「1分間シリーズ」の大ヒットで知られる、ケン・ブランチャードであり、自身がとく、知識を行動に変えるための秘訣をまとめた一冊。
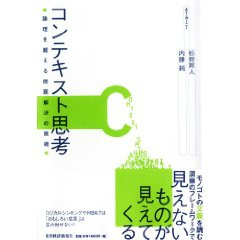 杉野 幹人、内藤 純「コンテキスト思考 論理を超える問題解決の技術」、東洋経済新報社(2009)
杉野 幹人、内藤 純「コンテキスト思考 論理を超える問題解決の技術」、東洋経済新報社(2009)
お奨め度”:★★★★★
モノゴトの裏にある物理的に認識できない「コンテキスト」を能動的に洞察する「コンテキスト思考法」を提唱し、独自の思考モデルによる具体的な思考プロセスを例示を使いながら解説した一冊。コンテキスト思考法により、「おもしろい成果」が期待できるというのが著者の主張である。
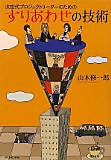 山本 修一郎「次世代プロジェクトリーダーのためのすりあわせの技術」、ダイヤモンド社(2009)
山本 修一郎「次世代プロジェクトリーダーのためのすりあわせの技術」、ダイヤモンド社(2009)
お奨め度:★★★★
今年になって、すりあわせをテーマにした本が2冊出版された。
そのうちの一冊がこの本。この本は、新規ビジネス開発をテーマに、その中核となるシステムの開発を行う様子を物語仕立てで描いたもので、その中で「すりあわせ家」が専門家の対立や協同をうまく調整しながらプロジェクトを成功に導いていくというもの。
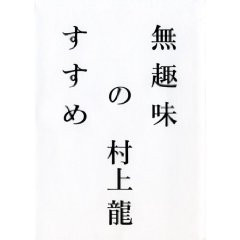 村上龍「無趣味のすすめ」、幻冬舎(2009)
村上龍「無趣味のすすめ」、幻冬舎(2009)
お奨め度:★★★★★
大学のときに、「限りなく透明に近いブルー」を読んでいっぺんにファンになった。
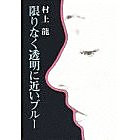 村上 龍「限りなく透明に近いブルー」、講談社(1976)
村上 龍「限りなく透明に近いブルー」、講談社(1976)
天才だと思った。そして、
村上 龍「コインロッカー・ベイビーズ」、講談社(1980)4061168649
で完全にはまった。
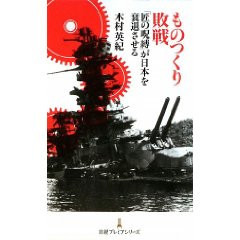 木村 英紀「ものつくり敗戦―「匠の呪縛」が日本を衰退させる」、日本経済新聞出版社 (2009/03)
木村 英紀「ものつくり敗戦―「匠の呪縛」が日本を衰退させる」、日本経済新聞出版社 (2009/03)
お奨め度:★★★★★
日本の技術が苦手なのか、「理論」、「システム」、「ソフトウエア」を3つだという仮説に基づく、システム思考を中核に据えた技術マネジメント論。
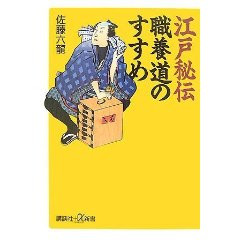 佐藤 六龍「江戸秘伝 職養道のすすめ」、講談社(2007)
佐藤 六龍「江戸秘伝 職養道のすすめ」、講談社(2007)
お奨め度:★★★★★
職養道とは、「職を養う道」のことで、江戸時代に年季明けで独立していく職人たちに、師や親方が授けた職業上の心得の集大成である。
江戸時代に、日用品や食料品を売る「生業」と呼ばれる仕事で一応の信頼を得ることは難しいことではなかった。実際にものを売るからだ。これに対して、医者や髪結い、大工、左官、易者など、「九流之術師」と呼ばれる仕事では、初対面相手から信頼を得ることは難しく、そのために各職業には「職養道」と呼ばれる仕事の上の心得が伝えられていたという。職養道は口述だったので、明治維新の近代化の波に飲まれて衰退し、戦後は完全に消滅したと思われていたが、橘哲州という占術家によって継承されており、橘哲州と箱根で一夜をともに過ごすことになった著者が話を聞き、あまりのおもしろさに著者の主催する運命学の教室で、「怪しげな職業の人間が相手の信用を得るための手練手管」として教えているそうだ。
それを書籍化したのが本書である。
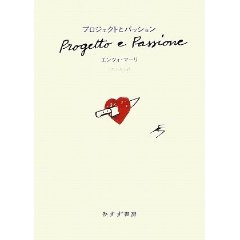 エンツォ・マーリ(田代 かおる訳)「プロジェクトとパッション」、みすず書房(2009)
エンツォ・マーリ(田代 かおる訳)「プロジェクトとパッション」、みすず書房(2009)
お奨め度:★★★★★
イタリアの巨匠エンツォ・マーリのプロジェクトデザイン論。
エンツォ・マーリは伝説的なモダンデザインの工房「ダネーゼ」とのコラボレーションを開始して、世界中に名を覇せた工業デザイナーである。日本では無印良品のデザイナーとして有名である。この本は自身のプロジェッティスタとしての考えをまとめ、後輩に伝えることを目的として書かれたプロジェクト哲学の書である。こういう本を書いてくれる人がいるというのがイタリアだと思わせる一冊。
■■■■■■【目次】■■■■■■
第1章 斧の一撃のものがたり
第2章 三つの地平線
第3章 必要、そしてまた必要
第4章 自然の方法論
第5章 学生へのいくつかの助言
■■■■■■■■■■■■■■■■
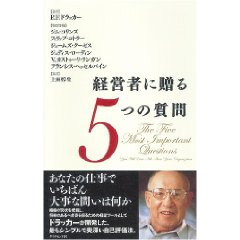 P.F.ドラッカー著、特別寄稿:ジム・コリンズ、フィリプ・コトラー、ジェームズ・クーゼス、ジュディス・ローディン、カストゥーリ・ランガン、フランシス・ヘッセルバイン(上田惇生訳)「経営者に贈る5つの質問」、ダイヤモンド社(2009)お奨め度:★★★★★
P.F.ドラッカー著、特別寄稿:ジム・コリンズ、フィリプ・コトラー、ジェームズ・クーゼス、ジュディス・ローディン、カストゥーリ・ランガン、フランシス・ヘッセルバイン(上田惇生訳)「経営者に贈る5つの質問」、ダイヤモンド社(2009)お奨め度:★★★★★
15年前に、ドラッカーの冠をつけた財団「ピーター・F・ドラッカーNPO財団」(現在はリーダー・トゥー・リーダー財団に改称)ができたときに、その存在意義を問うためにドラッカーが発した5つの質問を紹介した本。
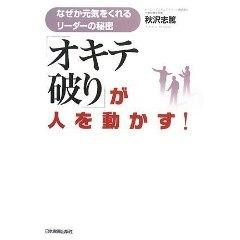 秋沢 志篤「 「オキテ破り」が人を動かす」、日本実業出版社(2008)
秋沢 志篤「 「オキテ破り」が人を動かす」、日本実業出版社(2008)
お奨め度:★★★★★
まだ、年を振り返るには多少早いが、今年は酒井穣さんの「課長の教科書」の大ヒットに始まって、ミドルマネジメントの本がたくさん出版された。僕は神戸大学の金井壽宏先生のゼミナールに参加したが、そのときに先生が言われていたことを思い出している。正確ではないが、「ミドルマネジャーは組織によって立場が違うし、人によってキャリアが違う。モデル化するよりも、フィールドワークから何かを学ぶことが重要」といったニュアンスのことである。
最近のコメント