日本のプロマネの最大の問題に対する処方箋
 峯本展夫「プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル―論理と知覚を磨く5つの極意」、社会経済生産性本部(2007)
峯本展夫「プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル―論理と知覚を磨く5つの極意」、社会経済生産性本部(2007)
お奨め度:★★★★1/2
日本でもPMPの数が2万人に近づき、この5年くらいの間に日本企業のプロジェクトマネジメントは格段に進歩し、欧米に近づいたという「説」がある。
しかし、実は、プロジェクトマネジメントについては、処方箋を間違っていたのでないかという思いもある。多くの日本企業は、プロジェクトマネジメントをプロセスとコンピテンシー(スキル)の問題として捉えてきた。そして、そのための薬を飲んできた。この薬がまったく、効かなかったわけではない。ある程度効いた。だから、冒頭に紹介したような見解がある。
ただ、症状を軽減するための薬であって、病巣を根治するための薬ではなかった。そんな印象が強い。この本は、病巣を根治するための処方箋である。
キーワードはプロフェッショナル、そして、プロフェッショナル責任である。この本ではまず、第1部でプロフェッショナルが持つべき責任について、PMIの提示した5つのプロフェッショナル責任をベースにして説いている。特に、インテグリティーについて正面から取り上げているプロジェクトマネジメントの本はたぶん最初だし、日本人になじみの薄い2つの責任概念(アカウンタビリティとレスポンシビリティ)を取り上げ、違いを明確にしている点は評価できる。ちなみに、メルマガでもこの議論をしているので、併せてお読みください(笑)。
アカウンタビリティとレスポンシビリティ
http://www.pmos.jp/honpo/note/note131.htm
次に第2部では、プロフェッショナル責任を果たすために、プロフェッショナルに必要な「近くのものを遠くからみる」というものの見方を説いている。その極意として、全体をとらえる、変化をとらえる、待つ、見えないものに挑む、前提を疑うの5つ。まさに、プロフェッショナルマネジメントの極意だといえる。この5つはぜひ、マスターしたい。
5つの極意のテーマのまとめ方はたいへん、「美しい」し、それ自体に価値があるといってもよいだろう。最近、プロジェクトマネジメントにおいても、ビジネスキャッチフレーズ的なものが目立つようになってきたが、峯本さんの言葉は、これらとは一線を隠した奥深さがある。峯本さん自身が、これらのテーマに挑戦しつづけていらっしゃるようだが、その表れだろう。
また、内容的にも、「リバース・スケジュール」、「前提条件のマネジメント」などは優れたアイディアだ。
第3部はPMBOKとPMBOKガイドという内包と外延を考え、PMBOKをどのように理解し、どのように適用していけばよいかを議論している。この議論もなかなか、面白い。プロジェクトマネジメントをプロセスとコンピテンシーだと思わせる一因になったのはいうまもなくPMBOKである。しかし、第3部の議論を読んでいると、知覚的に解説されていることで、そうではないことがよくわかり、PMBOKプロジェクトマネジメントの本質が見えてくるように思う。
全体的な感想としては、日本でもこういう本が出てくるようになったことは感慨深い。プロフェッショナルを自認するプロジェクトマネジャーの方は、ぜひ、峯本さんがこの本で展開している議論を真摯に受け止め、責任のあいまいさという日本組織の壁に挑戦してほしいと思う。

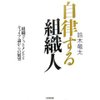


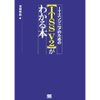

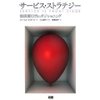
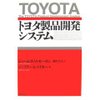

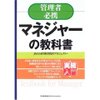
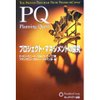
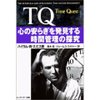
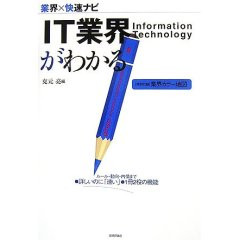
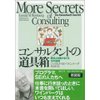

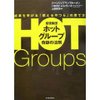
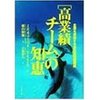

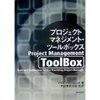

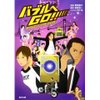
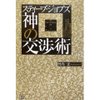
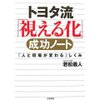



最近のコメント