企業を発掘し、育てる
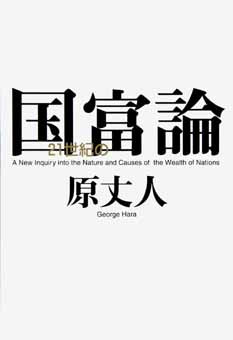 原丈人「21世紀の国富論」、平凡社(2007)
原丈人「21世紀の国富論」、平凡社(2007)
お奨め度:★★★★1/2
原丈人さんは日本ではあまり知られていないが、米国ではたいへん注目されている実業家で、ボーランド、SCO、ピクチャーテル、ウォロンゴング、トレイデックスなどの企業の経営と育成を手がけて来られた方だ。ボーランド時代にはビルゲイツのライバルといわれ、またネットの時代になると、早くからドットコム企業のビジネスモデルは成功しないと断言し、ドットコム企業には一切投資をしなかったキャピタリストとしても有名である。
最近では、ポストコンピュータの産業育成の視点から日本や韓国の企業でも事業育成に携わられている。
その原丈人さんが日本の産業を念頭において書かれたポストコンピュータ産業育成論。4章までは、グローバルな視点からの産業論が展開されており、最後の5章で日本への提言がある。
原丈人さんの育成論の基本は企業への愛情に溢れている。いわゆるベンチャーキャピタルとは一線を画している。むしろ、ベンチャーキャピタルやストックオプションのあり方に対して、批判的で、ベンチャーキャピタルは、長期のリスクをとっても、企業を時間をかけて丁寧に育てるべきだという点で一貫している。日本の企業の現在的な育成にはぴったりの育成論ではないかと思う。
詳しい話はこの本を読んでみてほしいのだが、ぼくは比較的早くから原丈人さんというビジネスマンに関心を持っていた。きっかけは、大学院の金井壽宏先生のゼミで、11人のミドルにインタビューをして活動を紹介する「創造するミドル」という本の輪読があった。この本の中で、原丈人さんは「ベンチャーを創造する―会社と会社をつなげてきたひと」というセッションで紹介されている。
金井壽宏、沼上幹、米倉誠一郎編「創造するミドル―生き方とキャリアを考えつづけるために」、有斐閣(1994)
原丈人さんはビジネスマンになる前は考古学の研究者だったそうで、考古学の発掘とベンチャーの発見・育成は同じだという考えに感銘を受けた。この本は、まさにこういう視点で書かれた産業育成、事業育成論が展開されている。
分析する視点は鋭く、独自性があり、丁寧に育てるという原丈人さんのスタンスに興味をもたれる方はぜひ読んでみてほしい。
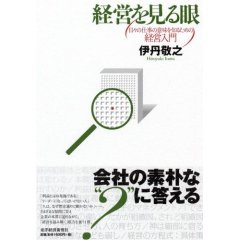
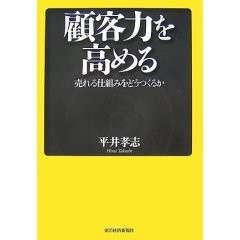
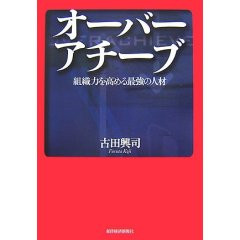
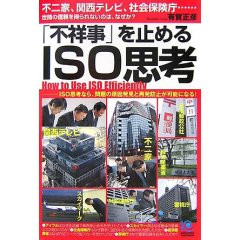
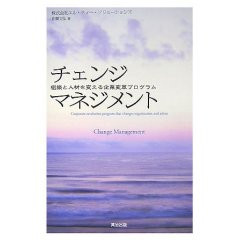
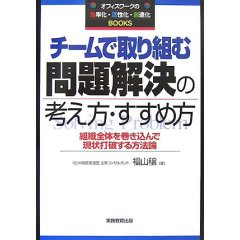
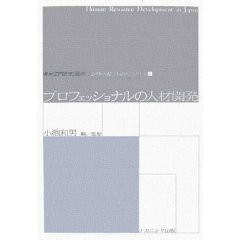
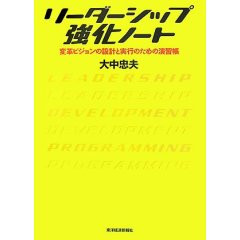
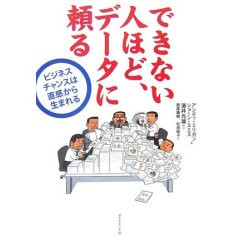
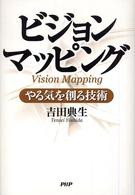
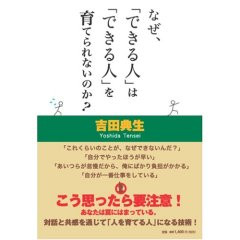
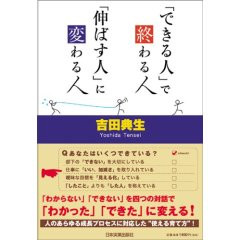
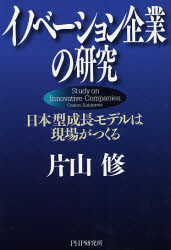

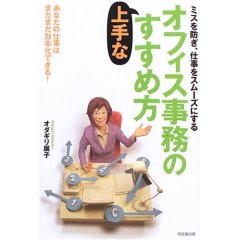
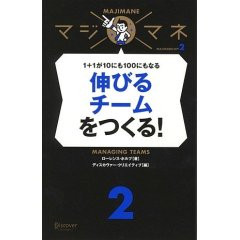
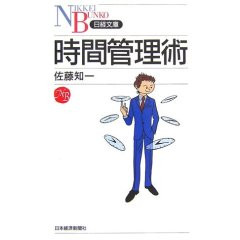
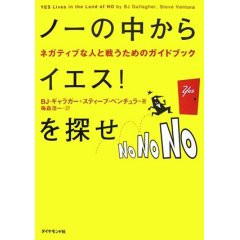
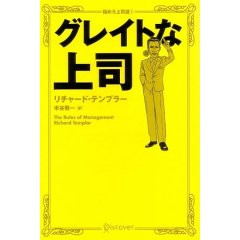
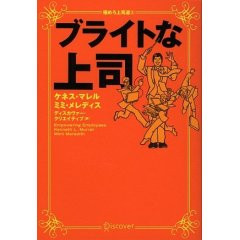
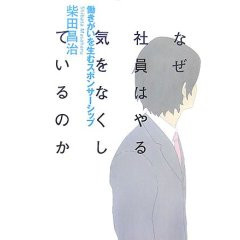
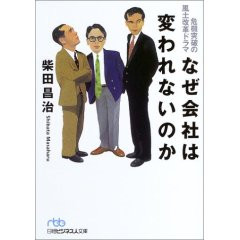
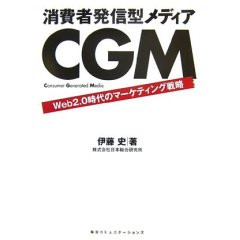

最近のコメント