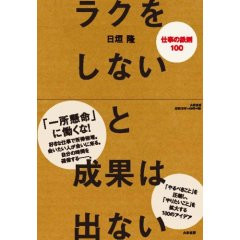 日垣 隆「ラクをしないと成果は出ない」、大和書房(2008)
日垣 隆「ラクをしないと成果は出ない」、大和書房(2008)
お薦め度:★★★★1/2
僕は、「ハウツー本」が嫌いだ。大きな市場があるのはよく分かるし、そこに出版社が参入するのも自由だが、読む気にもならない。メルマガに対して、もう少し、ハウツーを具体的に教えろという読者の声も多いが、無視している。メルマガにしろ、本にしろ、そんなことを書く気にならないからだ。
そもそも、ハウツー本に出てくる原理は、もう、カーネギー、オズボーン、デミングの時代に語りつくされているのだ。ところが、ハウツー本がなくならない理由は、その適用は、時代(仕事の環境)によって違う、業界によって違う、事業によって違う、仕事によって違う、人によって違う、など、原理から導かれるハウツーは無限といってもよいくらいある。
これは出版する側の論理であって、逆に読者の視点からいえば、このような違いがあるので、ハムスターの回し車のごとく、延々とハウツー本を読み続けなくてはならない。某出版社の人に聞いた話だが、ハウツー本を買う人は何冊も買い続けるというから、この指摘は当たっていると思う。速読法の本を何冊も買うという笑えないジョークもある。
ということで、ハウツー本はあまり読まないのだが、例外がある。それは、規範が明確に書かれているものだ。ハウツー本も書かれていることに規範があれば、応用が効く。そのような本は比較的読んでいると思う。
最近だと、
先読み力で人を動かす
御社の「売り」を小学5年生に15秒で説明できますか?
などは実によいハウツー本だと思う(これをハウツー本だと書くと著者は怒るかもしれないけど)。
さて、多少言葉の過ぎるイントロになったが、これはすごいと思う本を見つけた。それがこの本。この本の行動規範は、「ラクをすること」である。極めてタフな行動規範である。
組織の中で仕事をする、独立する、生活するなどいろいろな状況を考えて、「ラクをするため」にどうすればよいかのハウツーを惜しげもなく書いている。ただし、そう簡単にはできないものが多い。全般的な発想を一言でいえば、ものごとをシンプルしろといっているので、イナーシャが大きいものが多いのだ。
その意味で、この本が示しているハウツーは行動規範としての奥行きがあるものが多く、ゆえにハウツー本フリークからはハウツーではなく、理想を書いているだけだと厳しい評価がされる。
しかし、本当のハウツーというのはこういうものだと思う。
それにしても、「夢をかなえるゾウ」以来、柳の下にドジョウはいないかと言わんばかりの、段ボール箱に絵をかいたような装丁はどうにかならないものかね。。。
 横田尚哉「ワンランク上の問題解決の技術《実践編》 視点を変える「ファンクショナル・アプローチ」のすすめ」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2008)
横田尚哉「ワンランク上の問題解決の技術《実践編》 視点を変える「ファンクショナル・アプローチ」のすすめ」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2008)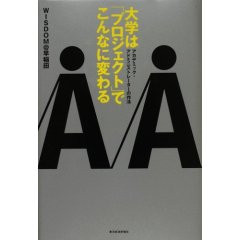
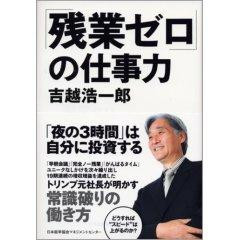
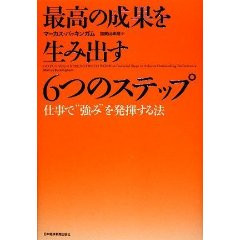
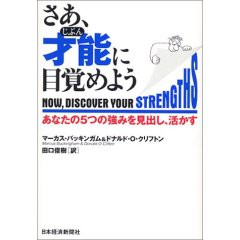
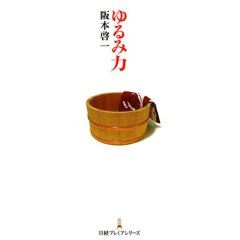
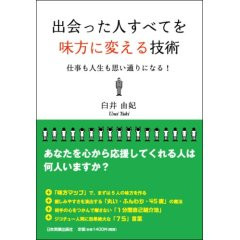
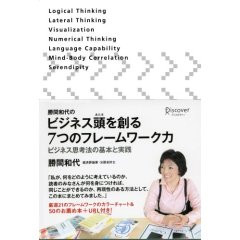
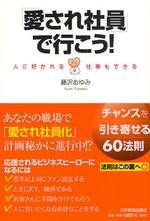
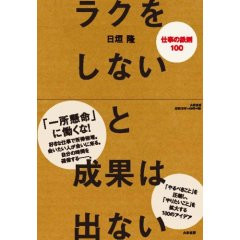

最近のコメント