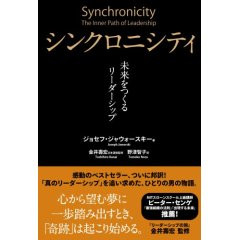 ジョセフ・ジャウォースキー(金井壽宏監修、野津智子訳)「シンクロニシティ 未来をつくるリーダーシップ」、英治出版(2007)
ジョセフ・ジャウォースキー(金井壽宏監修、野津智子訳)「シンクロニシティ 未来をつくるリーダーシップ」、英治出版(2007)
お奨め度:★★★★1/2
この記事で500エントリーになる。500エントリー目に残しておいた本を紹介しよう。「シンクロニシティ 未来をつくるリーダーシップ」。
ジョセフ・ジャウォースキーという「アメリカンリーダーシップフォーラム(ALF)」というリーダーシップ開発の団体を立ち上げた人物が、自叙伝の形で述べているリーダーシップの旅についてかいた本。
もともと、弁護士で、若くして法律事務所を立上げ、成功した著者は、リーダーシップの状況に問題意識を持ち、社会的起業家としてALFの立上げを決意する。それに集中していく中で、どんどん、離婚をし、ALFを立ち上げるまで、シンクロニシティに身を任せ、紆余曲折の中を進んでいく。その中で、自身、リーダーシップをめぐる旅をし、いろいろな人と出会い、いろいろなことを学び、仲間に巻き込んでいく。その中に、この本と一緒に英治出版が翻訳を出版したデヴィッド・ボームがいる。
デヴィッド・ボーム(金井真弓訳)「ダイアローグ 対立から共生へ、議論から対話へ」、英治出版(2007)
ALFが軌道に乗ったころ、シナリオプラニングと出会い、請われて、シェルグループのシナリオプラニングのリーダーとなる。その後、この本には出てこないが、金井先生の解説によるとMITの組織学習でコアメンバーとしての役割を果たし、現在はジェネロンコンサルティングを率いて、U理論を世に知らしめることに尽くしているとのこと。
この本の後の活動は、こちらの本を読めばよいだろう(超・難解!)
ピーター・センゲ、オットー・シャーマー、ジョセフ・ジャウォースキー、ベティ・フラワーズ(野中郁次郎, 高遠 裕子訳)「出現する未来」、講談社(2006)
非常に不思議な読後感の残る本である。僕は、この本は金井先生が話題にされているのを何度かお聞きしたし、ジョセフ・ジャウォースキー氏のリーダーシップの旅の根幹を成している、サーバントリーダーシップ、ダイアローグ、U理論という概念を齧っていたので、リーダーシップの本として読んだ。難しい本なので、どれだけ、ジョセフ・ジャウォースキー氏がこの本に託したメッセージが読めているかはよくわからないが、感じるものは多々あった。
ただ、これを前提なしに読めば、副題にある「未来を作るリーダーシップ」というのはきっとピンと来ないのではないかと思う(もちろん、僕なんかに較べるとはるかに洞察力に優れた人はそんなことはないだろうが)。そんなときに、リーダーになりたいと思うあなたが、偶然、このブログ記事を読んだことの意味をかんがえてみて欲しい。ここにも、この本でいうところのシンクロニシティ(共時性;因果関係では説明できない、偶然にもほぼ、時を同じくして生じる事象があること)があるのかもしれない。
併せて、お奨めした本が2冊ある。1冊は、この本で金井先生が紹介されているが、野田さんという方がリーダーシップの旅について書かれた本。
野田 智義、金井 壽宏「リーダーシップの旅 見えないものを見る」、光文社(2007)
もう1冊は、表現の手法は違うが、同じような視点から大規模な調査をした結果をまとめたこの本。
ビル・ジョージ、ピーター・シムズ(梅津祐良訳)「リーダーへの旅路―本当の自分、キャリア、価値観の探求」、社会経済生産性本部(2007)
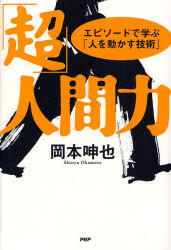 岡本呻也「 「超」人間力」、PHP(2007)
岡本呻也「 「超」人間力」、PHP(2007) 同じ著者のこの本もよい。同じようなテーストだが、こちらはインタビューなどを中心に人間力の抽出をしている。その意味で、「超」人間力の原点はこの本にあるのかもしれない。
同じ著者のこの本もよい。同じようなテーストだが、こちらはインタビューなどを中心に人間力の抽出をしている。その意味で、「超」人間力の原点はこの本にあるのかもしれない。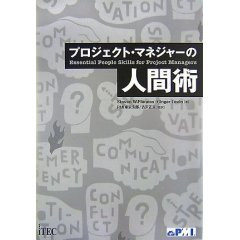
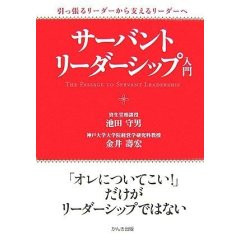
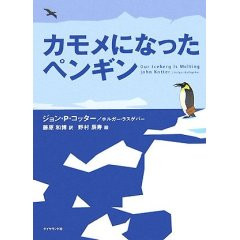
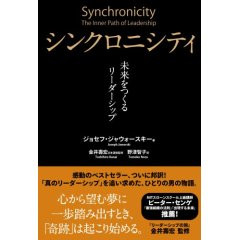
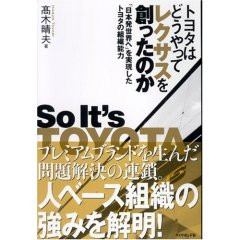
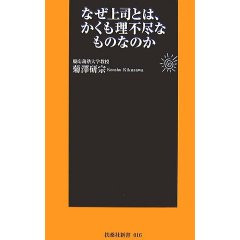
 「命令違反」が組織を伸ばす
「命令違反」が組織を伸ばす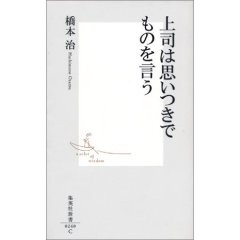
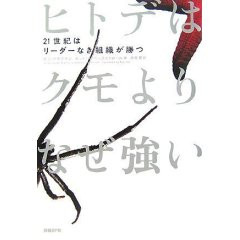
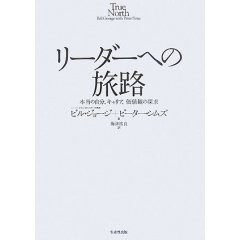
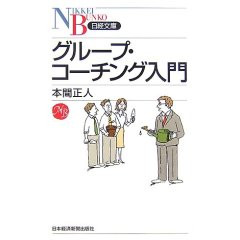

最近のコメント