ドラッカーを実践する
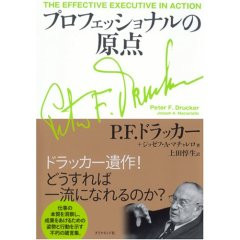 ピーター・ドラッカー (著)、ジョゼフ・マチャレロ(上田惇生訳)「プロフェッショナルの原点」、ダイヤモンド社(2008)
ピーター・ドラッカー (著)、ジョゼフ・マチャレロ(上田惇生訳)「プロフェッショナルの原点」、ダイヤモンド社(2008)
お薦め度:★★★★★
原題:The Effective Exective in Action
ドラッカーの最大の理解者であり、ドラッカーの教えを30年に渡り、教えてきたジョゼフ・マチャレロ教授がドラッカーの言葉を原題のテーマで、95のアドバイスに再構成した本。
この本を理解するためには、この本で最初の項目に取り上げられているドラッカーの言葉を知っておくとよい。
「経営者の条件」に書かれている言葉で
今日の組織では、自らの知識あるいは地位ゆえに組織の活動や業績に実質的な貢献をなすべき知識労働者は、すべてエグゼクティブである
という一節である。エグゼクティブという言葉は、通常、組織上の役職を示す言葉として使われるが、ドラッカーは上の抜粋の通り、別の意味で使っており、そこにこの本全体を貫くスタンスがある。このような前提で読むべき本である。
さて、本書は成果を上げる人のバイブルとしてまとめられたもので、
(1)時間をマネジメントする
(2)貢献に焦点を合わせる
(3)強みを生かす
(4)重要なことに集中する
(5)効果的な意思決定を行う
という5つの習慣を身につけるために書かれている。ゆえにこれまで、何冊かある、ドラッカー語録のような本とは多少違った趣がある。
それは上の5つについていくつかのポイントが示されている中で
・とるべき行動
・身につけるべき姿勢
の2つの視点から、コンピテンシーの強化についての記述があり、これを意識することによって習慣化できるようなつくりになっている点だ。これこそ、マチャレロ教授がドラッカー学を教えてきたノウハウだといえよう。
ひとつ例をあげておく。上にのべたようにこの本の第1章の1項目目は
「なされるべきことをなす」
というエグゼクティブであれというアドバイスなのだが、ここでの行動と姿勢は
【とるべき行動】
自らの組織においてなされるべきことは何か?自らがなすべきことは何か?
【身につけるべき姿勢】
常になされるべきことから考えることを癖にする。手本となる人はいるか?
といったもの。
ドラッカーの膨大な著作は秀逸なものばかりだが、実践ということでいえば、この一冊に勝る本はないだろう。購入し、擦り切れるまで使いこんでほしい!
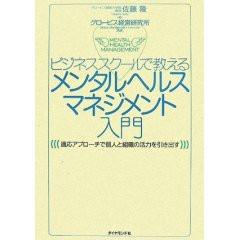
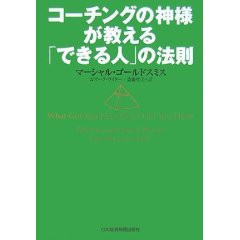
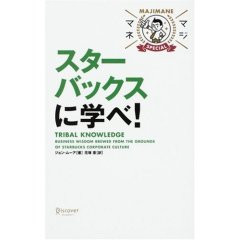
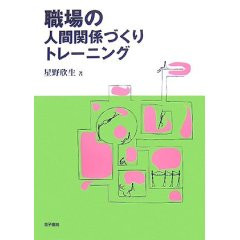
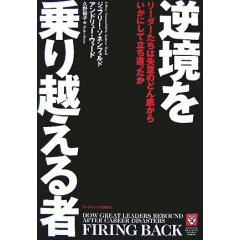
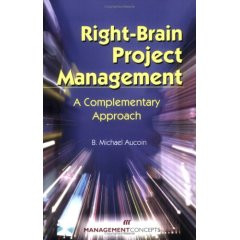
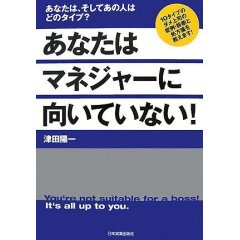

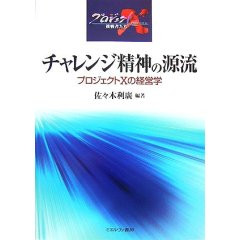

最近のコメント