日本のソフトウエアエンジニアリグの夜明けはくるか
 情報処理推進機構ソフトウェア・エンジニアリング・センター、日経コンピュータ「ソフトウェア開発データ白書―IT企業1000プロジェクトの定量データを徹底分析」、日経BP社 (2005)
情報処理推進機構ソフトウェア・エンジニアリング・センター、日経コンピュータ「ソフトウェア開発データ白書―IT企業1000プロジェクトの定量データを徹底分析」、日経BP社 (2005)
お奨め度:★★★★
米国ではソフトウエア開発の実態を定量的分析した本は、何冊もあるし、名著もあるが、日本ではおそらく、初めての本。
その米国では、ソフトウエアエンジニアリングでは、CMMで有名なカーネギーメロン大学のSEI(Software Engineering Institute)が頂点にある。ビジネススクールでいえば、ハーバードみたいな存在。
ちなみに、中国で、ソフトウエア産業が歴史が浅い割には、やたらとCMMで高レベルの企業が多いのは、ここに留学して帰国したエンジニアの力が大きいといわれている。
日本でも、昨年、日本版SEIを目指すIPAのソフトウェア・エンジニアリング研究機関「ソフトウェア・エンジニアリング・センター」(SEC)ができた。まだまだ、未知数だが、期待されている。
そのSECが中心になり、10社を超えるシステム・インテグレータから、およそ1000プロジェクト分のソフトウェア開発に関する定量的なデータを収集。そのデータを工期、生産性、品質に関して徹底分析し、「工期と生産性・品質の関係」、「適切な工期とは何か」、「品質と外注率の関係」など分析するとともに、課題を提起している。
分析はともかく、データとしては非常に面白いし、ソフトウエア以外の分野でも参考になる部分がある。
日本のソフトエンジニアリングの夜明けがくるか、、、きてほしいなあ!
とりあえず、期待をこめて、今月の1冊は、この本にする。












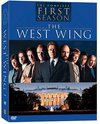





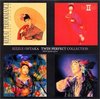


最近のコメント