適材適所の法則
 本間正人「適材適所の法則 コンピテンシー・モデルを越えて」、PHP研究所(2005)
本間正人「適材適所の法則 コンピテンシー・モデルを越えて」、PHP研究所(2005)
 本間正人「適材適所の法則 コンピテンシー・モデルを越えて」、PHP研究所(2005)
本間正人「適材適所の法則 コンピテンシー・モデルを越えて」、PHP研究所(2005)
 三菱総合研究所+阪本大介「イノベーションリーダーマネジメント―経営に“継続的な”イノベーションを実現させる新しいマネジメントの手法」、アーク出版(2005)
三菱総合研究所+阪本大介「イノベーションリーダーマネジメント―経営に“継続的な”イノベーションを実現させる新しいマネジメントの手法」、アーク出版(2005)
 キャサリン・フィッツジェラルド, ジェニファー・ガーヴェイ・バーガー, 日本能率協会コンサルティング「エグゼクティブ・コーチング」、日本能率協会マネジメントセンター(2005)
キャサリン・フィッツジェラルド, ジェニファー・ガーヴェイ・バーガー, 日本能率協会コンサルティング「エグゼクティブ・コーチング」、日本能率協会マネジメントセンター(2005)
お奨め度:★★★1/2
エグゼクティブ・コーチングというのはあまり耳慣れない言葉かもしれないが、企業が成長してゆくために、より効果的な経営のオペレーションを実施できるよう経営者や、経営スタッフが受けるコーチングのことである。
コーチングを受けることによって考え方を多様化し、コミュニケーションの方法を変え、さらには、習慣や、コミュニケーション・スタイルを変革しながら、ハイパフォーマンスな経営のトップやチームとなることが目的である。
この本は、そのための具体的な方法を体系的に書いた本である。内容的には
エグゼクティブ・コーチングの展望
エグゼクティブ・コーチングの実践
組織におけるエグゼクティブ・コーチングのマネジメント
エグゼクティブ・コーチングの課題
特定のコーチング場面についての解説
などがカバーされており、実際に使える内容になっている。
エグゼクティブ・コーチングは、プロジェクトマネジメントに対するコーチングとしても使える。むしろ、一般的なコーチングよりは有効である。PMO、母体組織のマネージャーなどはぜひ読んでいただきたい1冊である。
アメリカの本らしい、プラクティカルな1冊だ。
 Bruce T. Barkley, James H. Saylor「Customer-Driven Project Management: Building Quality Building Quality into Project Processes」、McGraw-Hill Companies(2001)
Bruce T. Barkley, James H. Saylor「Customer-Driven Project Management: Building Quality Building Quality into Project Processes」、McGraw-Hill Companies(2001)
お奨め度:★★★★1/2
顧客を重視したプロジェクトの進め方の体系的方法論を述べている。
プロジェクトの品質を顧客満足の視点から捉え、プロジェクトの品質を請うj表させる方法についてケースを中心にして説明している。
この本の面白い点は、プロジェクトの顧客をさまざまな視点から捉えている点にある。プロダクトの品質は客観的なものである。しかし、プロジェクトの品質は必ずしもそうではない。顧客の評価、スポンサーの評価、上司の評価などさまざまな価値観が錯綜するからである。それらに対して、統一的なアプローチをすることはきわめて重要な課題であり、本書はそれをしている。
プロジェクトマネジメントのバイブルの1冊。
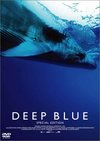 ディープ・ブルー スペシャル・エディション、東北新社(2005)
ディープ・ブルー スペシャル・エディション、東北新社(2005)
お奨め度:★★★★1/2
海洋ドキュメンタリーの大傑作
7年かけて、7000時間の映像を撮り、それを168分の映画に編集している。
とにかく、見てみよう!感動の一言に尽きる
 ハワード・ガードナー(朝倉和子訳)「リーダーなら、人の心を変えなさい」、講談社(2005)
ハワード・ガードナー(朝倉和子訳)「リーダーなら、人の心を変えなさい」、講談社(2005)
お奨め度:★★★1/2
リーダーシップの本質はここにあるのではないだろうか?
さまざまなタイプのリーダーシップが、決心する、成長する、夢をかなえるなど、さまざまな形で人の心に影響を及ぼしていく。
考えさせられる本だ。
 忰田進一「図解・創造的仕事の技術」、ソフトバンクパブリッシング(2004)
忰田進一「図解・創造的仕事の技術」、ソフトバンクパブリッシング(2004)
お奨め度:★★★1/2
企画、提案、問題解決などの必要な発想を、非常に分かりやすく書いてある。図がよい。こういう図を描きたいな。
内容は基本的なことから、結構、高度なノウハウだと思われることまでが並んでいる。しかし、ばらつき感はない。確かに、レベルは違っていても同時に抑えておくべきことが並んでいる。
たとえば、アイディアを出す仕事のヒント(3章)
思い込みは自分の首をしめる
考えてから動け
時間配分
質問は技術、質問はつくるもの
要約で頭が切り替わる
全体と部分を同時にみる
といった感じ。この本のヘソは
知恵の生産(2章)
か!?
 トム・ピーターズ、ロバートウォーターマン(大前研一訳)「エクレセント・カンパニー」、英治出版(2003)
トム・ピーターズ、ロバートウォーターマン(大前研一訳)「エクレセント・カンパニー」、英治出版(2003)
★★★★1/2
ビジネス書ではまれに見るベストセラー。巨匠「トム・ピーターズ」の出世作。
エクセレントカンパニーの条件は何か?他の企業がやっていないのに、エクセレントカンパニーだけがやっていることは何か?ベストプラクティスを示している。
20年前(1983年)の本であるが、英治出版により復刊された。拍手!
三菱重工に勤務していた時代に始めてよみ、大学院でもテキストとして読み、何度か読んだ。久しぶりに読んでみて思ったのは、今、成功している企業を見ると、このような特徴が見つからないなということだっだ。
多様化しているのかもしれない。一方で、トム・ピーターズがこの本を書いたのは大変なブレークスルーだと思うが、そのようなブレークスルーを生み出しそうなコンサルタントやジャーナリスト、学者がいないようにも思う。ドラッカーは別格としても、トム・ピーターズの時代にはブレークスルーと呼べる仕事をしているビジネスアドバイザー(グル)が何人かいる。
5年ほど前に「経営革命大全」という画期的な本が出版された。マネジメントの「グル」79名の大まかな業績を紹介した本だ。詳しくはこちらを読んでみてほしい。
このレベルの30代のビジネスアドバイザーというと、ぱっと思う浮かぶ人がいないのも事実である。ひょっとすると、MIcrosoft、Yahoo!、Amazon、DELLにはすごい原則が隠れているのかもしれない。
 ジョセフ・H. ボイエット、ジミー・T. ボイエット(金井壽宏、大川修二訳)「経営革命大全」、日本経済新聞社(1999)
ジョセフ・H. ボイエット、ジミー・T. ボイエット(金井壽宏、大川修二訳)「経営革命大全」、日本経済新聞社(1999)
お奨め度:★★★★
画期的な本だと思う。まずは、数。79名のグル(権威者)というのすごい数だ。これだけを取り上げながら、ばらつき感がなく、章ごとにまとまっている。
単にグルの主張の紹介ではなく、著者が問題を設定し、それに対してグルがどのような解決策を示しているかという視点から纏められていて、非常に現実の場面で役に立つ。とりあえず、困った問題に出会ったら、当該テーマの部分を読んで、役に立ちそうな説を展開しているグルを探し、その人の本を読んでみればいいからだ。
この本の問題点はドラッカー博士の扱いだろう。さまざまな分野で金字塔のような業績を残しているにもかかわらず、あまり、それがうまく扱えていないように思った。まあ、こういう枠を作ると明らかに別格だから仕方ないか、、、
ビジネス書の杜 4月の月間ベストセラーです。今月は販売数は微増ですが、なぜか、ばらけています。
PMBOK3版は早くも100冊を超えました。すごい!です。
あまりたくさん売れた本がなかったおかげで、好川の著書が2位に返り咲きました(笑)
【2005年4月ベスト5】
(→)第1位 A Guide To The Project Management Body Of Knowledge: Official Japanese Translation (19)
(↑)第2位 プロジェクトマネージャーが成功する法則―プロジェクトを牽引できるリーダーの心得とスキル (16)
(-)第3位 世界一わかりやすいプロジェクト・マネジメント(6)
(↓)第4位 ソフトウエア企業の競争戦略 (5)
(→)第4位 チームリーダーの教科書―図解 (5)
(↑)第4位 セクシープロジェクトで差をつけろ! トム・ピーターズのサラリーマン大逆襲作戦 (2)(5)
==========
![]() 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!
 楡周平「再生巨流」、新潮社(2005)
楡周平「再生巨流」、新潮社(2005)
お奨め度:★★★★1/2
帯にある「このプロジェクト、死んでも成功させる」というフレーズが気になり、読んでみた。経済小説。
佐川急便をモデル化した運送会社スバル運輸で、豪腕ゆえに、新規事業開発事業部という新設ポストに左遷された主人公吉野公啓が、アスクル(小説中ではプロンプト)に対抗するビジネスモデルを構築するプロジェクト小説。アスクルは文具店を代理店としているが、このモデルでは、街の電気屋さんを代理店とし、文具だけでなく、日用雑貨、電気製品などを総合的に取り扱うネットワークの構築を行う。
このビジネスモデルは昔から話題に上ることが多いものだが、相当、具体的にかかれており、それだけでもなかなか読み応えがある。
この小説の真骨頂は、プロジェクトマネジメントである。商社からスバル運輸に転職した主人公は立ち上げ屋のイメージがあり、立ち上がるといなくなってしまうタイプの人間。それが左遷の原因にもなる。この小説で描かれているプロジェクトでも立ち上げ前のプロセスが詳細に書かれているが、最後は社主に直談判して実現にこぎつけた総額90億円の投資プロジェクト。運用ベースに乗るまで逃げるわけに行かない。その中で、人を育てるということを知る。
ステークホルダマネジメント、チームマネジメント、リーダーシップ、リスクマネジメントの教科書ともいえるくらいよくできたストーリーになっている。まさに、プロジェクトマネジメントのすべてがここにある。プロジェクトマネジメントを「説明」するために、いくつかの小説が書かれたが、さすが本職。それらとは比べ物にならない出来だ!
ビジネスモデルの構築の中で、SIがスケジュールが間に合わないとごねるシーンがある。ここに対しても非常に明確な解答を与えている。まあ、楡氏の得意分野ではあるが、、、
エンディングは書かないが、プロジェクトマネジメントというより、マネジメントのすべてがここにあるといってもよいかもしれない。
==========
![]() 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!
 東洋エンジニアリング「プロジェクトマネジメント 成功するための仕事術―プロジェクトをリードする精鋭たちの経験とナレッジを集大成」、日本能率協会マネジメントセンター(2003)
東洋エンジニアリング「プロジェクトマネジメント 成功するための仕事術―プロジェクトをリードする精鋭たちの経験とナレッジを集大成」、日本能率協会マネジメントセンター(2003)
お奨め度:★★★★
プロジェクトマネジメントありきではなく、仕事ありきで、その中でプロジェクトマネジメントが如何に役立つかを議論している。非常に貴重な本である。
残念ながら、プラントエンジニアリングを前提に書かれており、それが議論の幅を狭めていると思われる部分があるが、6~7割の話は、どのような仕事でも通用する話であり、その意味でビジネスマンの必読書である。
バージニア・アンダーソン、ローレン・ジョンソン「 システム・シンキング~問題解決と意思決定を図解で行う論理的思考技術」、日本能率協会マネジメントセンター(2001)
システム・シンキング~問題解決と意思決定を図解で行う論理的思考技術」、日本能率協会マネジメントセンター(2001)
お奨め度:★★★★
システム思考の教科書。
システム思考を具体的な例を示しながら、ツールごとに解説している。非常に分かりやすい本である。
時系列変化グラフ
因果ループ図
アーキタイプ
この本のよいのは、システムとは何かという解説が非常に明確である点。この解説により、システム思考がなぜ必要か、なぜ、発案されたかが明確に分かるようになっている。
なお、この本だけでも、十分に例はあるが、実際にシステム思考を使えるようになるためには、本書と姉妹編のトレーニングブックを使って、実際に手を動かしてみるのがお奨め。
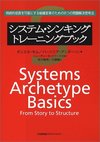 ダニエル・キム、バージニア・アンダーソン「システム・シンキングトレーニングブック」、日本能率協会マネジメントセンター(2002)
ダニエル・キム、バージニア・アンダーソン「システム・シンキングトレーニングブック」、日本能率協会マネジメントセンター(2002)
==========
![]() 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!
 トム・ピーターズ(仁平和夫)「セクシープロジェクトで差をつけろ!」、ティビーエスブリタニカ(2000)
トム・ピーターズ(仁平和夫)「セクシープロジェクトで差をつけろ!」、ティビーエスブリタニカ(2000)
お奨め度:★★★★1/2
プロジェクトが面白くない、やらされている、いやいややっている。
仕事が面白くない
そんな人は、この本を読んでみよう!「エクセレントカンパニー」で名を馳せたビジネスコンサルティングの巨匠「トム・ピーターズ」のプロジェクトマネジメント論!
==========
![]() 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!
 プレストン・G.スミス、ガイ・M.メリット(澤田美樹子訳)「実践・リスクマネジメント―製品開発の不確実性をコントロールする5つのステップ」、生産性出版(2003)
プレストン・G.スミス、ガイ・M.メリット(澤田美樹子訳)「実践・リスクマネジメント―製品開発の不確実性をコントロールする5つのステップ」、生産性出版(2003)
お奨め度:★★★★1/2
PMIのアワードを受賞し、リスクマネジメントの定番になるかもしれない本。内容は難しい。しかし、それはリスクマネジメントというのはそんなに簡単なことではないと思うことができる1冊。何だこれと思うような概念がたくさんある。しかし、よく考えてみると理にかなっている。この繰り返し。
読み通すには時間がかかるが、この本を一冊読めば、製品開発におけるリスクマネジメントは格段に進歩するだろう。
==========
![]() 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!
 R.H.バックマン(日本ナレッジ・マネジメント学会翻訳委員会訳)「知識コミュニティにおける経営」、シュプリンガー・フェアラーク東京(2005)
R.H.バックマン(日本ナレッジ・マネジメント学会翻訳委員会訳)「知識コミュニティにおける経営」、シュプリンガー・フェアラーク東京(2005)
お奨め度:★★★★
米バックマン・ラボラトリーズ元会長によるナレッジ・マネジメントの解説書である。興味深いのは、ナレッジマネジメントの解説をしているのだが、単に仕組みやナレッジマネジメントの方法論の話にとどまらず、ナレッジコミュニティを経営するという視点から話を展開している。このため、バーチャルチームの話なども出てくる。もちろん、内容的には自社(化学メーカ)の事例であるので、説得力はある。
プロジェクトをナレッジコミュニティとして運営していきたいという方向性を考えているマネージャーにとってはこの上ない参考書になるだろう。
 遠藤功「現場力を鍛える 「強い現場」をつくる7つの条件」、東洋経済新報社(2004)
遠藤功「現場力を鍛える 「強い現場」をつくる7つの条件」、東洋経済新報社(2004)
お奨め度:★★★1/2
遠藤氏は「現場」を体系的に語れる貴重な存在である。この本も期待にたがわない。
この本の中で、現場力について
企業のオペレーションを担う現場が持つ組織能力のこと。具体的には、現場自らが問題を発見し、解決する能力を指す。この組織能力には企業間格差があり、現場力の高い企業は持続力のある競争力を確保している
という定義をされている。この能力が弱くなってきているというのがこの本の背景であり、現場力を強くするための7つの条件が説明されている。
現場力を鍛えた先に待っているものは、オペレーションエクセレンスである。遠藤氏はオペレーションエクセレンスについて
の中でかなり突っ込んだ議論をしているので、こちらも併せて読んでみるとよいだろう。
オペレーションエクセレンスと現場力は、矛盾している部分もある。そのあたりをきちんと整理しながら読んでいく必要がある。
==========
![]() 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!
 大工舎宏, 平山賢二「経営の「突破力」現場の「達成力」―経営と現場を結ぶ4つの実践手法」、日本プラントメンテナンス協会(2004)
大工舎宏, 平山賢二「経営の「突破力」現場の「達成力」―経営と現場を結ぶ4つの実践手法」、日本プラントメンテナンス協会(2004)
お奨め度:★★★1/2
「収益構造展開」「KPIマネジメント」「目標/方策マトリクス」「スコアカード」
という4つのツールを使って、経営と現場を結ぶ実践的手法を解説している。
これらのツールにより、「勝てる目標」を設定し、それを現場で達成する方法が示されている。
現場では、経営の利益に対する考え方が分からない中で、利益に対する意思決定を求められるケースが多い。バランススコアカード系の手法は経営からアクティビティに展開するツールとしては有効だと思うが、逆方向の流れ、つまり、現場から経営へのフィードバックができにくい。
ここで提案されている手法は、その点において優れている。
 三浦優子「〈図解〉あの新“勝ち組”IT企業はなぜ儲かるのか?」、技術評論社(2005)
三浦優子「〈図解〉あの新“勝ち組”IT企業はなぜ儲かるのか?」、技術評論社(2005)
お奨め度:★★★1/3
ホリエモン本の中においてあったので手にとってみたら、これが以外(失礼)と大当たり。いわゆる勝ち組IT企業を取り上げて、その企業の活動を4ページ程度で紹介しているが、非常に良質の分析がされており、ビジネスモデル大全といったような趣の本に仕上がっている。
これが1000円は安い!このブログは価格に関係なく、書籍を評価したいと思っているので、上のような評価だが、価格を入れるなら文句なく★★★★★。
それにしても、日本のIT企業もかんばっているなあとつくづく思う。ガンバ!
 サニー・ベーカー+キム・ベーカー+G・マイケル・キャンベル(中嶋秀隆, 香月秀文訳)「世界一わかりやすいプロジェクト・マネジメント」、総合法令(2005)
サニー・ベーカー+キム・ベーカー+G・マイケル・キャンベル(中嶋秀隆, 香月秀文訳)「世界一わかりやすいプロジェクト・マネジメント」、総合法令(2005)
お奨め度:★★★★1/2
訳者あとがきに、訳者の中嶋・香月氏が一昨年のPMIの年次大会で、いろいろな国のコンサルタントとプロジェクトマネジメントの実用書の極め付きの1冊という話をしたら、この本になったというエピソードが書かれている。そのくらいすばらしい本だと思う。
この本で著者の説いているプロジェクト成功の12の黄金律がある。この黄金律をみて、なるほど、と思えたら、この本から得られるものは多いだろう。
1. 成果物について合意を得る
2. 最良のチームを育てる
3. しっかりしたプロジェクト計画書を作り、更新を怠らない
4. 本当に必要な資源を判断する
5. 現実的なスケジュールを作る
6. できないことはやらない
7. 常にヒトを大切にする
8. 正式な支援を取り付け、継続して確認する
9. 変更を躊躇しない
10. 現状を周知する
11. 新しいことに挑戦する
12. リーダーとなる
==========
![]() 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!
最近のコメント