不合理が競争力を生み出す
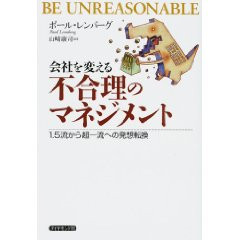 ポール・レンバーグ(山崎康司訳)「会社を変える 不合理のマネジメント―1.5流から超一流への発想転換」、ダイヤモンド社(2008)
ポール・レンバーグ(山崎康司訳)「会社を変える 不合理のマネジメント―1.5流から超一流への発想転換」、ダイヤモンド社(2008)
お奨め度:★★★★★
型に始まり、型を破る
マネジメントには常識がある。しかし、常識にとらわれている限り、平均的な成果を超える成果を挙げることはままならない。この本は、型の破り方を「体系的」に教えてくれる。
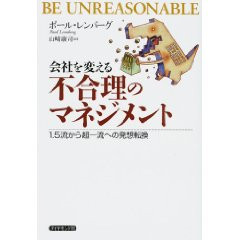 ポール・レンバーグ(山崎康司訳)「会社を変える 不合理のマネジメント―1.5流から超一流への発想転換」、ダイヤモンド社(2008)
ポール・レンバーグ(山崎康司訳)「会社を変える 不合理のマネジメント―1.5流から超一流への発想転換」、ダイヤモンド社(2008)
お奨め度:★★★★★
型に始まり、型を破る
マネジメントには常識がある。しかし、常識にとらわれている限り、平均的な成果を超える成果を挙げることはままならない。この本は、型の破り方を「体系的」に教えてくれる。
PMstyle会員向けのメルマガを出し終え、今日の仕事は完了。そのあとに多少気になっていた本に目を通す。
社団法人日本能率協会「隠れた力を引き出す会社」、日本能率協会マネジメント 出版情報事業(2008)
【感想】
企業ものとしてはすごく面白い本。気づきもあるし、元気を与えてくれる。
何年か、くすぶっていた感があるが、成果主義はもうだめだろう。
市場だけではなく、組織ももっと管理すべきだという時代がくるような予感。だからといって、この本で取り上げられたような企業がそんなに増えるとは思えない。マネジメントとしては、やっぱり、「イロモノ」のような気がする。
朝から雨の日曜。オフィスで雑用を片付けやら、メルマガの執筆やらしていたら、ペリカン便でアマゾンからの荷物が到着。
あけてみると、何冊かの中に、お待ちかねの天外伺朗さんの新作が入っていた。
●「非常識経営の夜明け 燃える「フロー」型組織が奇跡を生む」、講談社(2008)
天外さんの本は、必ず何度かよみかえすので、とりあえず、さっと目を通そうと作業を中断して、読書モードに。
1ページ目はサッカー全日本の岡田監督が天外さんのセミナーに行ってよかったって話。ジャパンがフロー(スポーツなのでゾーン?)になった試合というのは、最近、記憶にないけど、、、全日本でなければ、マイアミの奇跡。でも、もう10年も前の話だ。
2ページ目。「人間性経営学シリーズ」によせて...とある。表紙をみるとシリーズ第2巻とある。えっ、第1巻は?と思って読み進んだのだが、どうもはっきりしない。アマゾンで検索してもそれらしきものはない。
文中のニュアンスから察すると
天外伺朗「マネジメント革命 「燃える集団」を実現する「長老型」のススメ」、講談社(2006)
ではないかと推測される。
むう、ナゾだ。誰か知っていたら教えて!
内容は、期待を裏切らず。もちろん、紹介記事を書く予定。1ヶ月くらい前に読んだ
チクセント・ミハイ「フロー体験とグッドビジネス―仕事と生きがい」、世界思想社教学社(2008)
ともう一度一緒に読んでみたい。そういえば、こちらも紹介記事を書き出して、途中でほったらかしになっている、、、
あと、企画絡みで、
○吉田誠一郎「クレドが考えて動く社員を育てる!」、日本実業者(2008)
を読んだ。
クレドそのものは、リッツカールトンの専売特許になっているようだが、一般的な概念。この本ではジョンソンアンドジョンソンも有名って書いてあったが、知らなかった。
本としては自社の宣伝なのか、クレドについて書きたいのかよく分からない。宣伝でないって言うなら、デメリットも書くべきだな。微妙。たくさんのクレドが載せてあるのが値打ち。
土曜日だったのと、東京から京都まで新幹線の移動があったので、今日は2冊の本を読んだ。
●ポール・レンバーグ(山崎康司訳)「会社を変える 不合理のマネジメント―1.5流から超一流への発想転換」、ダイヤモンド社(2008)
【感想】
イノベーションにこういうきり方があるのかと感心した。そんなに変わったことが書いてあるわけではないが、面白い。後日、紹介文を書こう。
○町田勝彦「オンリーワンは創意である」、文藝春秋(2008)
【感想】
話のねたになるところは何箇所かあった。ただ、シャープの企業モノは出尽くし感があるなあ。。。
ビジネス書の杜で紹介している本が年間約100冊。年間に読んでいる本は、年によって差がありますが、300~400冊。
 ジョン・ケイドー(花塚恵訳、勝間和代監修)「ブレイン・ティーザー ビジネス頭を創る100の難問」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2008)
ジョン・ケイドー(花塚恵訳、勝間和代監修)「ブレイン・ティーザー ビジネス頭を創る100の難問」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2008)
お奨め度:★★★★
電車の中で、携帯電話のゲームをやったり、クロスワードをやったりしている人をよく目にするが、ビジネスマンならこの本で暇つぶしをしよう。
・水平思考(ラテラルシンキング)
・論理思考
・数字力を使う論理思考
・確率のパズル(ベルヌイ推定)
・フェルミ推定
・ビジネスケース
の6ジャンルが1ジャンル1章で構成されている。
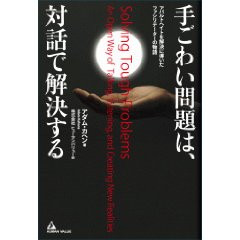 アダム・カヘン(高間邦男監修、ヒューマンバリュー編訳)「手ごわい問題は、対話で解決する」、ヒューマンバリュー(2008)
アダム・カヘン(高間邦男監修、ヒューマンバリュー編訳)「手ごわい問題は、対話で解決する」、ヒューマンバリュー(2008)
お薦め度:★★★★1/2
問題には2種類ある。ひとつは技術的な問題解決のように、答えを探す問題である。答えがあるかどうかは分からないが、答えはあるものだとして答えを探す。そして、もうひとつは答えを作る問題である。これは最初から答えがあるわけではない。問題の当事者が納得するような答えを作っていかなくてはならない。マネジメントやビジネスにおける問題はほとんど後者である。
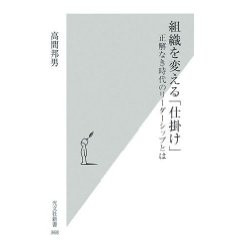 高間邦男「組織を変える「仕掛け」」、光文社(2008)
高間邦男「組織を変える「仕掛け」」、光文社(2008)
お奨め度:★★★★1/2
ヒューマンバリューの高間邦男さんが、自社で実践している活動を中心にして、新しい組織マネジメントやリーダーシップのあり方、また、そこに向けての組織変革について全体像を示した一冊。
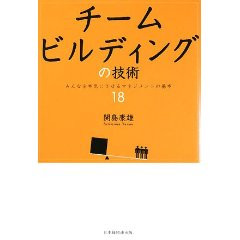 関島 康雄「チームビルディングの技術―みんなを本気にさせるマネジメントの基本18」、日本経団連事業サービス(2008)
関島 康雄「チームビルディングの技術―みんなを本気にさせるマネジメントの基本18」、日本経団連事業サービス(2008)
お奨め度:★★★★★
最近、チームビルディングの本が増えてきた。片っ端から読んでみているのだが、チームビルディングは多面性があり、著者の専門的な視点に偏った説明になっていて、どうも、「盲人が象を語っている」ような感じの本ばかりだった。ということで、これというお奨め本が見当たらなかったが、やっと、象を象として説明している本に出会ったような気がしている一冊。
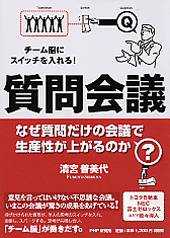 清宮普美代「質問会議 なぜ質問だけの会議で生産性が上がるのか?」、PHP研究所(2008)
清宮普美代「質問会議 なぜ質問だけの会議で生産性が上がるのか?」、PHP研究所(2008)
お奨め度:★★★★1/2
21世紀に入ってから注目されるようになってきたアクションラーニングについて、マイケル・マーコード博士の手法を「質問会議」と名づけ、平易に、事例を交えて紹介した一冊。
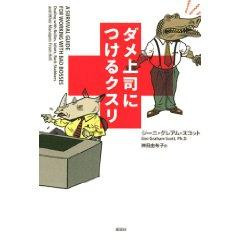 ジーニ・グレアム・スコット(神田 由布子訳)「ダメ上司につけるクスリ」、講談社(2008)
ジーニ・グレアム・スコット(神田 由布子訳)「ダメ上司につけるクスリ」、講談社(2008)
お薦め度:★★★1/2
ジーニ・グレアム・スコットは米国では50冊以上の本を出している評判の文筆家であり、影響を持つコンサルタントでもある。本書はジーニ・グレアム・スコットの初の邦訳。
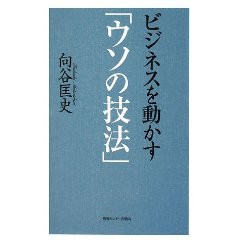 向谷匡史「ビジネスを動かす「ウソの技法」 」、情報センター出版局(2008)
向谷匡史「ビジネスを動かす「ウソの技法」 」、情報センター出版局(2008)
お薦め度:★★★★1/2
ヤクザの行動をビジネスに活かすというテーマで、さまざまな本を書いている向谷匡史氏の新作。コンプライアンスの強化が望まれている時代にぎょっとするようなタイトルの本である。ただし、内容は帯にもあるとおり、A級のコミュニケーション術を学べる一冊。
 横田尚哉「ワンランク上の問題解決の技術《実践編》 視点を変える「ファンクショナル・アプローチ」のすすめ」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2008)
横田尚哉「ワンランク上の問題解決の技術《実践編》 視点を変える「ファンクショナル・アプローチ」のすすめ」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2008)
お薦め度:★★★★1/2
1947年にGE社で考案された発想法であるファンクショナルアプローチを用いた問題解決手法について、実践を意識しながら、解説した一冊。ファンクショナルアプローチは、機能、目的、ベネフィットに注目し、あるべき姿を達成するためのギャップは何かを考え、そのギャップを埋める方策を考えていくという方法。
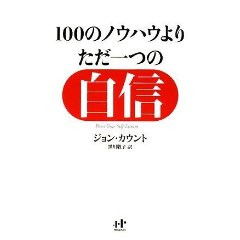 ジョン・カウント(黒川敬子)「100のノウハウよりただ一つの自信 ゆるぎない「自分」をつくる77の心理技術」、ナナ・コーポレート・コミュニケーション(2008)
ジョン・カウント(黒川敬子)「100のノウハウよりただ一つの自信 ゆるぎない「自分」をつくる77の心理技術」、ナナ・コーポレート・コミュニケーション(2008)
お奨め度:★★★★★
本屋にいけば、所狭しと積まれている啓蒙書。平積みされている本には○万部突破とかポップがついている、いわゆるベストセラーも少なくない。なぜ、こんなに売れるのだろうか?この本を読んでいるうちになるほどと思った。
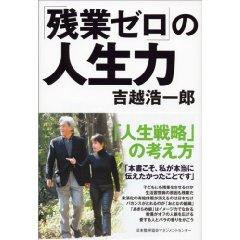 吉越 浩一郎「 「残業ゼロ」の人生力」、日本能率協会マネジメント 出版情報事業(2008)
吉越 浩一郎「 「残業ゼロ」の人生力」、日本能率協会マネジメント 出版情報事業(2008)
お薦め度:★★★★
ベストセラー「「残業ゼロ」の仕事力」の吉越 浩一郎氏の第2弾。前書の背景であり、また、結末であるともいえる1冊。
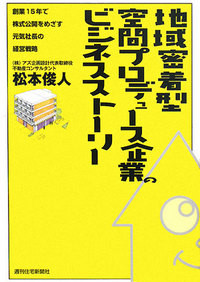 松本 俊人「地域密着型空間プロデュース企業のビジネスストーリー―創業15年で株式公開をめざす元気社長の経営戦略」、週刊住宅新聞社(2008)
松本 俊人「地域密着型空間プロデュース企業のビジネスストーリー―創業15年で株式公開をめざす元気社長の経営戦略」、週刊住宅新聞社(2008)
お薦め度:★★★★
創業し、戦略的な事業をやるというのがどういうことかを、経営者自らの経験を分析し、徹底的に教えてくれる好書。
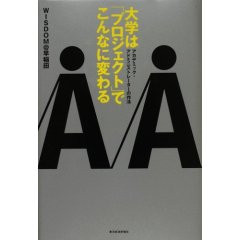 WISDOM@早稲田「大学は「プロジェクト」でこんなに変わる―アカデミック・アドミニストレーターの作法」、東洋経済新報社(2008)
WISDOM@早稲田「大学は「プロジェクト」でこんなに変わる―アカデミック・アドミニストレーターの作法」、東洋経済新報社(2008)
お薦め度:★★★★
プロジェクトとは何だったのかを改めて思い出させてくれる一冊。早稲田大学で、さまざまな変革をプロジェクトとして行っていくために作られたプロジェクトマネジメントのテキストを書籍化した一冊。
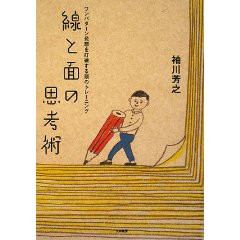 袖川芳之「線と面の思考術 自分の頭で考える道具を手に入れよう」、大和書房(2008)
袖川芳之「線と面の思考術 自分の頭で考える道具を手に入れよう」、大和書房(2008)
お薦め度:★★★★★
「点と線」といえば、松本清張氏の初めての長編小説。書かれたのは1957年である。松本清張氏の代表作というよりも、日本の推理小説の最高傑作にひとつだ。昨年は、50周年だったわけだが、テレビ朝日の50周年の事業としてビートたけしの主演で初めてドラマ化され、話題になった。
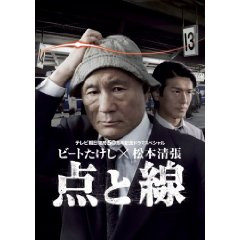 「ビートたけし×松本清張 点と線」、ジェネオン エンタテインメント(2008)
「ビートたけし×松本清張 点と線」、ジェネオン エンタテインメント(2008)
「点と線」は点ではなく、線に注目することによって、事件を解決する推理小説。今となってはよくあるトリックだが、当時は画期的な発想の転換だったことは想像に難くない。
最近のコメント