今日から、ビジネス書の杜第45回書籍プレゼントを開始。第45回はアイコーチの幸地さんの「オフショアに失敗する方法」。プレゼント応募はこちらから。
ソフトリサーチセンターからの出版で、このネーミングは同じ出版社の中村文彦さんの「ITプロジェクトを失敗させる方法」を思い出させるタイトルだ。日本人は失敗から学ぶことを好むことを考えたタイトルだろうが、マネジメントでは、失敗から学ぶことなどあまりないと思う。先日、紹介した「不合理性のマネジメント」の中で、ポール・レンバーグが面白いことをいっている。次のようなこと。
常に根本原因が存在するというのはフロイト心理学派の言い出したことだが、人の逸脱行動が性的関係やトラウマで説明されるという考えのおかげで、こうなった原因を解明できればその問題を修復でき、二度とこうならないと信じてしまう。しかし、根本原因は、効果的な解決策については何の説明もしておらず、したがって何の行動にも結びつかない。グレイゴリー・ベイトソンこのような分析をは「説明的原理」と呼んでいる。
少なくともマネジメントにおいては、失敗から学ぶことは、「説明的原理」であることが多いと思う。
まあ、それはさておき、本は幸地さんの活動の集大成になっているよい本だ。視野が広く、マメな幸地さんの人柄も出ている構成である。
さて、前書きが長くなったが、今日の読書日記。
これも以前ブログで紹介したが、財務会計の画期的な書籍
デイビッド・メッキン(國貞 克則訳)「財務マネジメントの基本と原則」、東洋経済新報社(2008)
を翻訳された國貞克則さんが、東洋経済新報社から「悩めるマネジャーのためのマネジメントバイブル」という本を出された。
次回のプレゼントはこの本の予定。すでに流し読みしていたが、今日は記事を書くためにきっちりと読んだ。最初に読んだときはあまりピンとこなかったが、、よく読めば共感する部分は多い。
よく考えながら読まないと、何を言わんとしているのか分からないところが多くあるが、まあ、マネジャー向けの本なので、「少しは考えろ!」っていう著者からのメッセージなんだろう。
近いうちに記事を書きます。お楽しみに!
つぎ、久しぶりにヤン・カールソンの「真実の瞬間」を読んだ。仕事のため。この本、最初に読んだのは、神戸大学の大学院でサービスマーケティングの講義の教材。もう10年以上前だが、そのあと、何度読んだか分からない。何度、読んでもインスパイアされる。今日も、ちょっとしたひらめきがあった。
ヤン・カールソン(堤猶二訳)「真実の瞬間―SAS(スカンジナビア航空)のサービス戦略はなぜ成功したか」、ダイヤモンド社(1990)
色あせないどころか、世の中はヤン・カールソンの実践に向かっている。にも関わらず、単純なことなのにできない。(サービス)イノベーションというのはそういうものかもしれない。
ひらめきといえば、昨晩、茂木先生の
茂木健一郎「ひらめきの導火線」、PHP社(2008)
を読んだ。トヨタとノーベル賞を結びつけて考えるって、相当な編集能力だ。茂木先生の本は、没頭してしまうとあまり面白くない。構想を味わいながら読むと面白い。この本は、その典型だろう。
まだ、続く。こちらも仕事ネタだが、中川邦夫さんの問題解決本「全体観」の上下を一挙に呼んだ。高い本なので、気にしつつも、今まで手を出していなかった本。この人は一体どういう頭の構造をしているのだろう。これに尽きる。すごい!
問題解決本が乱刊されているので、一度、僕なりの整理の記事を書こうと思うが、僕のナンバー1は
佐藤 允一「新版 図解・問題解決入門―問題の見つけ方と手の打ち方」、ダイヤモンド社(2003)
である。この本は新装版で、もともとは1884年に出版された
佐藤 允一「問題構造学入門―知恵の方法を考える」、ダイヤモンド社(1984)
なので、25年前に出版された本。
何が気に入っているかというと、現代的な問題解決本は、考えるパターン、つまり、ソリューションを与えようとしている。言い換えれば、考えない問題解決を究極の姿としている。この本は、考えるための規範を与えている点。まあ、今のご時勢では売れないと思うが、この本で問題解決のコツをつかんだ人は強いと思う。
中川さんの本も、ひょっとすると佐藤さんの本に近い存在になるかもしれない。
中川 邦夫(コンテンツ・ファクトリー編、中川学イラスト)「問題解決の全体観 上巻 ハード思考編」、コンテンツ・ファクトリー(2008)
中川 邦夫(コンテンツ・ファクトリー編、中川学イラスト)「問題解決の全体観 上巻 ソフト思考編」、コンテンツ・ファクトリー(2008)
土曜日の夜につれずれなるままに、綴ったが、今日の日記はここまで。
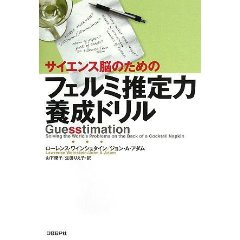
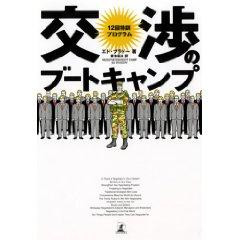
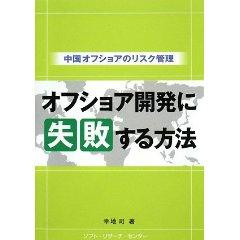
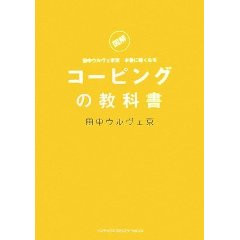
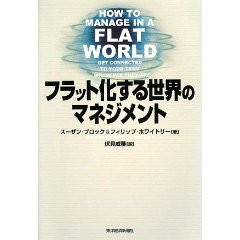
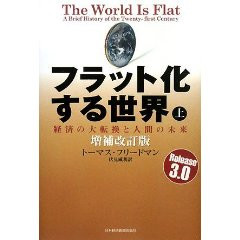
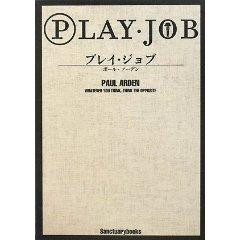
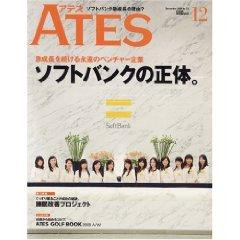

最近のコメント