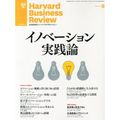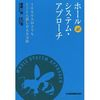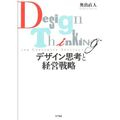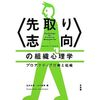【プロデューサーの本棚】イノベーションを実行する―挑戦的アイデアを実現するマネジメント
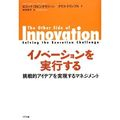 ビジャイ・ゴビンダラジャン、クリス・トリンブル(吉田 利子訳)「イノベーションを実行する―挑戦的アイデアを実現するマネジメント」、エヌティティ出版(2012)
ビジャイ・ゴビンダラジャン、クリス・トリンブル(吉田 利子訳)「イノベーションを実行する―挑戦的アイデアを実現するマネジメント」、エヌティティ出版(2012)◆イノベーションのイメージと実態
イノベーションという言葉が頻繁に使われるようになって、どうもイメージに踊らされている感がある。その中で最たるものは、よいアイデアが出てきたらイノベーションは成功したも同然だというイメージだ。
このイメージは違うというのはちょっと考えれば分かる。たとえば、商品を考えてみよう。これまでになかった商品のアイデアが生まれた。この商品がイノベーションになるには、商品を作るための技術開発、生産方法、流通方法など、さまざまなハードルを越えなくてはならない。それらに比べると、商品自体のアイデアを作りだすのはそんなに難しいことではないかもしれない。
言い換えると、よいアイデアというのはイノベーションとして実現され、成功した素のアイデアであり、アイデア自体を絶対的に評価できるものではない。僕は一時、公的機関の目利きの仕事をしていたことがあるが、目利きというのはアイデア自体の評価ではなく、実現方法の評価に近い。
さらにいえば、イノベーションとして成功するには、生産能力が鍵になるかもしれないし、流通能力が鍵になるかもしれない。つまり、あるアイデアを実現できるかどうかが、その組織の基本能力に依存することはよくあることだ。たとえば、ホンダが1994年に、生活創造車という新しいコンセプトで、オデッセイという車を開発した。乗用車ベースのミニバンとして、セダン同等の運動性能を持ち、なおかつセダンよりも広い室内空間を売りにしていたが、ワンボックスカーと比べて特長的である車高の低い形状にしたのは生産ラインの制約があったからだという。オデッセイの場合、組織能力の制約がよい方に作用したわけだが、画期的な商品を開発できても生産できなければイノベーションは起こらない。
この本では、組織既存業務の遂行能力を「パフォーマンスエンジン」と呼んでいるが、パフォーマンスエンジンとどのような関係性を持つかは、イノベーションの成功に大きな影響を与える。
全く新しいコンセプトの商品を開発して、新しい工場とサプライチェーンを作り、新しい流通ネットワークを作っていくということが皆無ではないが、ベンチャーの初期を除けば極めて稀である。
その意味で、イノベーションを既存の事業と切り離して行えるというのは幻想である。この本では、イノベーションを組織の中でどのように行っていけばよいかについて、いくつかの成功事例を分析しながら、体系的にまとめている。