【プロデューサーの本棚】フィールドワークの技法―問いを育てる、仮説をきたえる
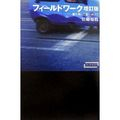 昨日、メルマガにフィールドワークに関する記事を書いていて、本を調べていたら、佐藤郁哉先生の名著、「フィールドワーク」の増訂版が出版されていることに気付いた。もう6年前の本だが、、、
昨日、メルマガにフィールドワークに関する記事を書いていて、本を調べていたら、佐藤郁哉先生の名著、「フィールドワーク」の増訂版が出版されていることに気付いた。もう6年前の本だが、、、
佐藤 郁哉「ワードマップ フィールドワーク―書を持って街へ出よう」、新曜社; 増訂版(2006)
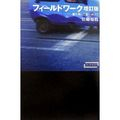 昨日、メルマガにフィールドワークに関する記事を書いていて、本を調べていたら、佐藤郁哉先生の名著、「フィールドワーク」の増訂版が出版されていることに気付いた。もう6年前の本だが、、、
昨日、メルマガにフィールドワークに関する記事を書いていて、本を調べていたら、佐藤郁哉先生の名著、「フィールドワーク」の増訂版が出版されていることに気付いた。もう6年前の本だが、、、
佐藤 郁哉「ワードマップ フィールドワーク―書を持って街へ出よう」、新曜社; 増訂版(2006)
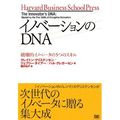 クレイトン・クリステンセン、ジェフリー・ダイアー、ハル・グレガーセン(櫻井 祐子訳)「イノベーションのDNA 破壊的イノベータの5つのスキル」、翔泳社(2012)
クレイトン・クリステンセン、ジェフリー・ダイアー、ハル・グレガーセン(櫻井 祐子訳)「イノベーションのDNA 破壊的イノベータの5つのスキル」、翔泳社(2012)
「イノベーションのジレンマ」で破壊的なイノベーションによって優位を脅かされる企業がイノベーションにおいて陥る落とし穴を示し、「イノベーションの解」で破壊する側からの視点で行動指針を示したクレイトン・クリステンセン博士が、イノベーションを実行する人と組織に着目し、その要件をまとめた一冊。特に本書で取り上げられているイノベータはアップルだとか、アマゾン、グーグルなど、いま旬の企業が多く、読み物としても面白い。
 神庭 弘年監修、Barbee Davis編、(笹井 崇司訳)「プロジェクト・マネジャーが知るべき97のこと」、オライリージャパン(2011)
神庭 弘年監修、Barbee Davis編、(笹井 崇司訳)「プロジェクト・マネジャーが知るべき97のこと」、オライリージャパン(2011)
米国の人気シリーズのひとつ「97 Things」シリーズのプロジェクトマネジャーの翻訳が出た。このシリーズは、その道のプロの「持論」を見開き1ページのエッセイにして収録したもの。
以下のようなタイトルの97のエッセイが並ぶ。
 中嶋秀隆、鈴木安而、伊熊昭等編著「伝説のPMが教える 私のいち押しプロジェクト」、評言社(2011)
中嶋秀隆、鈴木安而、伊熊昭等編著「伝説のPMが教える 私のいち押しプロジェクト」、評言社(2011)
プロジェクトマネジメントのコンサルタントや、実務家が、自らの経験したプロジェクトを語った一冊。一押しプロジェクトというだけあって、10ページ弱にまとめられた内容からもさまざまなことを感じ、学ぶことができる。
・IT
・エンジニアリング・建設
・製品開発
・業務改革・新サービス
内容にもまして、このような本が生まれたことには敬意を表したい。本書ができたきっかけは、PMIのフォーラムの雑談で、「最近はプロジェクトマネジャーになりたがらない人が多い」という例の問題意識からだという。この本を読んで、一人でも多くの人がプロジェクトマネジャーをやってみたいなと思うようになることを願ってやまない。
取り上げられているプロジェクトと筆者は以下の通り。
 Dave Gray、Sunni Brown、James Macanufo(野村 恭彦監訳、武舎 広幸、武舎 るみ訳)「ゲームストーミング ―会議、チーム、プロジェクトを成功へと導く87のゲーム」、オライリージャパン(2011)
Dave Gray、Sunni Brown、James Macanufo(野村 恭彦監訳、武舎 広幸、武舎 るみ訳)「ゲームストーミング ―会議、チーム、プロジェクトを成功へと導く87のゲーム」、オライリージャパン(2011)
今、もっとも注目されているコラボレーションの手法「ゲームストーミング」の待望の邦訳。会議やチーム、プロジェクトをクリエイティブに成功させたいと思っている人は必読の一冊。
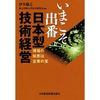 伊丹 敬之編著、東京理科大学MOT研究会編集「いまこそ出番 日本型技術経営―現場の知恵は企業の宝」、日本経済新聞出版社(2011)
伊丹 敬之編著、東京理科大学MOT研究会編集「いまこそ出番 日本型技術経営―現場の知恵は企業の宝」、日本経済新聞出版社(2011)
東京理科大学 大学院 技術経営専攻の教員と卒業生からなる東京理科大学MOT研究会がMOTのあり方を考え、発信している一冊。構成としては、伊丹先生や教員の方が総論や概論で方向性を示し、卒業生が自社の事例をその方向性にまとめた作りになっている。
 Jonathan Rasmusson(西村 直人、角谷 信太郎監訳、, 近藤 修平、角掛 拓未訳)「アジャイルサムライ-達人開発者への道-」、オーム社(2011)
Jonathan Rasmusson(西村 直人、角谷 信太郎監訳、, 近藤 修平、角掛 拓未訳)「アジャイルサムライ-達人開発者への道-」、オーム社(2011)
アジャイル開発(マネジメント)の本は多いが、これだけ、マネジメントと開発手法のバランスのとれた本は珍しい。また、説明の突っ込み方も技術書特有のポイントを絞って詳細に説明するというのではなく、全体像が把握でき、かつ、個々の説明も実用レベルという絶妙のバランスで書かれている。この点も含めて、アジャイル開発の取り組むための最初の一冊としては、文句なしにお勧めの本。
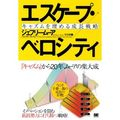 ジェフリー・ムーア(栗原 潔訳)「エスケープ・ベロシティ キャズムを埋める成長戦略」、翔泳社(2011)
ジェフリー・ムーア(栗原 潔訳)「エスケープ・ベロシティ キャズムを埋める成長戦略」、翔泳社(2011)
ハイテクの商品開発を支配するキャズム理論を考案したジェフリー・ムーア氏のエスケープ・ベロシティの翻訳が出版された。原書が出てそんなに経過していないので、ちょっとびっくりした。この記事では、少し、大局的な解説をしてみたい。
P aul Dinsmore、Terence Cooke-Davies「Right Projects Done Right: From Business Strategy to Successful Pr oject Implementation」、Jossey-Bass(2005)
aul Dinsmore、Terence Cooke-Davies「Right Projects Done Right: From Business Strategy to Successful Pr oject Implementation」、Jossey-Bass(2005)
プロジェクトガバナンスの名著。
一般的には、プロジェクトガバナンスは「Right Project Done Right」という。正しいプロジェクトを選ぶ、そのプロジェクトを正しく行うことによって、ガバナンスが実現できる。
現場だけで考えるとその通りである。つまり、戦略実行をするためには、戦略と整合性の高いプロジェクトを選び、そのプロジェクトを統合マネジメントしながら、戦略への貢献を最大化する。これによって、ガバナンスが高まっていく。
ただし、資源が無制限にあればその通りだが、一般的に資源は有限である。人・金・モノという資源の制約条件があるからだ。そのような制限の中で、ガバナンスを維持しようとすると、少し話が変わってくる。
コンビネーションを正しく行わなくてはならない。この本では、The Right Combinationと言っている。
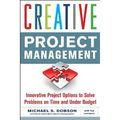 Michael Dobson「Creative Project Management」、McGraw-Hill(2010)
Michael Dobson「Creative Project Management」、McGraw-Hill(2010)
「プロジェクトの補助線」に書いている連載「アジャイルプロジェクトマネジメント入門」の第2回でも述べましたが、プロジェクトがイノベーティブ、あるいはクリエイティブにならない理由を突き詰めていくと、結局、意思決定の問題に帰着することが多いです。俗な言葉でいえば、判断ではなく、決断、決定ができないものです。