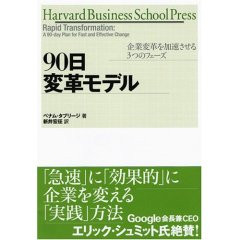 ベナム・タブリージ(新井宏征訳)「90日変革モデル 企業変革を加速させる3つのフェーズ」、翔泳社(2008)
ベナム・タブリージ(新井宏征訳)「90日変革モデル 企業変革を加速させる3つのフェーズ」、翔泳社(2008)
お薦め度:★★★★
原題:Rapid Transformation:A 90-day Plan for Fast Effective Change
最初に手前ミソな話になって恐縮だが、われわれが提唱しているスキームの中で、90日間がキーワードになっているものが2つある。ひとつは、「プログラムマネジメント」のスキームであり、そして2つ目はそのプログラムマネジメントのスキームを応用したプロジェクトマネジメントの導入・定着化スキームである。いずれも、変革のマネジメントであるが、90日間に拘っているところに経験的な意味がある。それは、変革に巻き込む人のモチベーションを最初の掛け声だけで維持できる限界が90日くらいだと思われるからだ。その意味で90日で何らかの成果を出すということがきわめて重要なことだ。この成果がなくては、求心力が弱くなり、変革は絵に描いた餅になる可能性が高くなる。
さて、この本だが、この90日の間に、クロスファンクショナルチームを作り、
フェーズ1:診断(30日)
フェーズ2:未来を描く(30日)
フェーズ3:準備をする(30日)
という3つのフェーズを実行することによって、
・参加型の変革
・包括的かつ統合的な変革
・迅速な変革
を実現しようというものである。ここで述べられているフェーズは、変革の期間ではなく、そのシナリオを計画と描く期間である。その後、変革実行を6~12か月で行うとされている。
このモデルの近い事例として、3M、ベリサイン、ベイネットワーク、アップル、ACIなど56ケースの事例から、その有効性を説いている。
本書では、まず、最初に変革の準備として何をすべきかを述べた上で、変革の取り組み体制であるクロスファンクショナルチームについて、なぜ、クロスファンクショナルチームがよいのか、そして、どのようにクロスファンクショナルチームを結成して、変革に取り組んでいくかを解説している。
次に各フェーズについてその詳細を解説するとともに、上の事例で、各フェーズにおいて、何をやったかをプラクティスとして紹介している。そして、90日間で、変革の実行をするにあたって、どのような点に留意すればよいかを説明している。
訳者があとがきに書いているように、ここで展開されているモデルは、変革手法として一般的に述べらているものとそんなに大きな違いがあるわけではない。ただ、非常に評価できるのは90日間というスケジュールの設定をしている点も含めて、非常に具体的である点だ。どのような会議を開くか、その会議でどのようなアジェンダを議論するかまで含めて説明されている。その点で、非常に実践的な本である。
特に冒頭にも述べたように、90日を如何に合理的、かつ、効果的に活動するかは極めて重要であり、そこにこれだけ具体的な方法論を提供してくれる点で素晴らしい本だと思う。
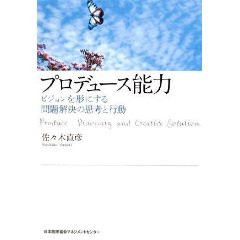 佐々木 直彦「プロデュース能力 ビジョンを形にする問題解決の思考と行動」、日本能率協会マネジメントセンター(2008)
佐々木 直彦「プロデュース能力 ビジョンを形にする問題解決の思考と行動」、日本能率協会マネジメントセンター(2008)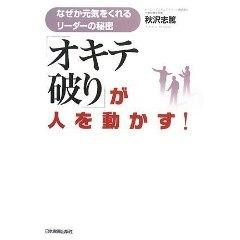
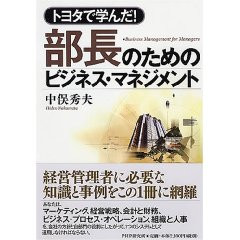
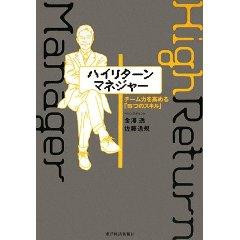
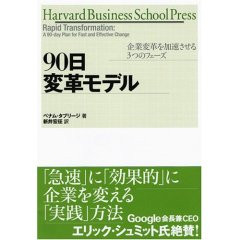
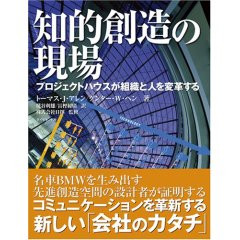


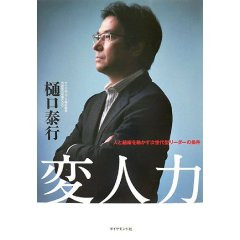
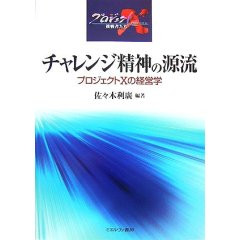

最近のコメント