本物のプロフェッショナルとは
 松本 整「勝負に強い人がやっていること―ここぞという時に結果を出す考え方・行動の仕方」、ナナ・コーポレート・コミュニケーション(2007)
松本 整「勝負に強い人がやっていること―ここぞという時に結果を出す考え方・行動の仕方」、ナナ・コーポレート・コミュニケーション(2007)
お薦め度:★★★★1/2
著者の松本整氏は競輪の世界で最年長のG1タイトル取得の記録を持つ競輪の名選手でありながら、現役時代から自分のトレーニングジムを開設し、独自のメソッドによるアスリートのトレーニングを行っているという変わったキャリアの持ち主。その松本氏が、自身のメソッドをまとめた本。
いくつもはっとするところが多い。
この本では最初にプロフェッショナルの定義から始まる。プロフェッショナルの定義はビジネスの世界ではいくつもあるし、わかったような概念になっているが、松本氏の定義はいたってシンプル。プロとは
「常に勝ち続けることのできる人」
だという。この定義は「が~ん」という感じだ。人材育成の仕事をしていながら、なんとなくプロフェッショナルの定義はよくわからないという思いを持ち続けてきたが、これで納得。この定義は単純なようで、極めて深い。
おそらく、僕が知っているすべてのプロフェッショナルの条件はこれで片付く。
プロフェッショナルの条件でおそらくもっとも多くの人が納得しているのはドラッカー博士の定義だと思う。
での定義は
「成果をあげる」という絶対目標を持ち、自らの行動に「責任」を持つ人材
である。この本の定義はイメージしにくい。何がイメージしにくいかというと、ドラッカー博士のいうところの「成長」というキーワードだ。成長するというのはどういうことか?
たぶん、ここに松本氏のいう「続ける」というキーワードがくっついていることに気付かされた。
松本氏のメッセージは、スキルだけでいえばアマチュアの方が強い場合もある。プロフェッショナルとはその職業としてトップランナーとして継続的に食っていける人だという明確なメッセージ。特に、成果を上げることができるようになってからの継続が難しい。
一つの仕事で成果を上げることもそんなに簡単なことではない。しかし、継続するのはその何十倍も難しい。だから、(特に日本人は)長くやっていることを評価する。
ビジネスでいえば、マーケティングのプロフェッショナルといえばどんな状況で売れる商品を企画できる人。プロジェクトマネジメントのプロフェッショナルというとどんなプロジェクトでもそのプロジェクトに収益をもたらすことができる人のことだ。この状況では、売れなくても仕方ないとか、プロジェクトが成功しなくても仕方ないといっている間はアマチュアっていうことだ。
この本は、このプロフェッショナルにどのようになっていくかを「一般論」として論じている。たとえば話に自身の競輪の経験を使っているケースが多いが、スポーツ一般に通じる話だと思うし、僕の読む限りではビジネスにも通じる話だ。
前半は比較的ロジカルにかかれており、後半は読者に発破をかけるような記述が多い。これも意図したものだと思われる。本物のプロフェッショナルを目指す人、元気になりたい人にお勧めしたい一冊。
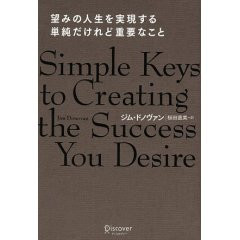
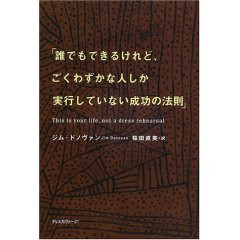
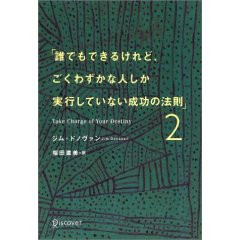
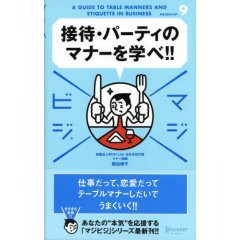

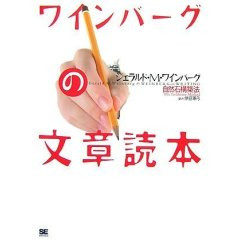
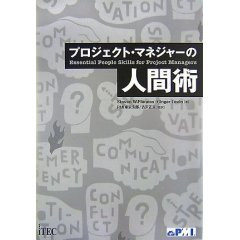
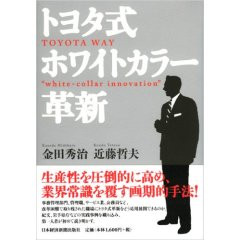
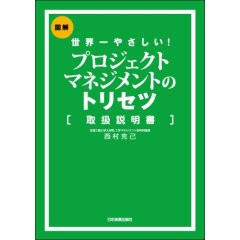
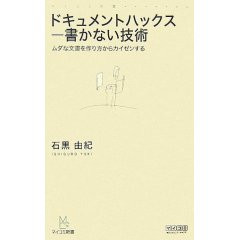
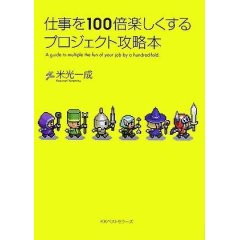
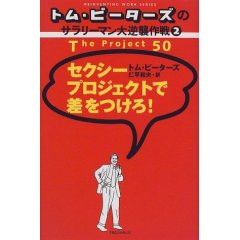

最近のコメント