ワークショップを極める!
ワークショップは、「作業場」や「工房」を意味する語であるが、20世紀に入ってからは体験型の講座の意味で用いられるようになってきた。
この意味でのワークショップは「主体的な参加」し、「自発的に作業」することによる「体験の共有」に大きな特徴がある。この特徴ゆえに、
・合意形成
・問題解決
・教育学習
など、さまざまな分野でつかわれている。今では、企業やトレーニングの中で普通に用いられる手法になっている。
ワークショップは、「作業場」や「工房」を意味する語であるが、20世紀に入ってからは体験型の講座の意味で用いられるようになってきた。
この意味でのワークショップは「主体的な参加」し、「自発的に作業」することによる「体験の共有」に大きな特徴がある。この特徴ゆえに、
・合意形成
・問題解決
・教育学習
など、さまざまな分野でつかわれている。今では、企業やトレーニングの中で普通に用いられる手法になっている。
 藤沢あゆみ「「愛され社員」で行こう! 」、日本実業出版社(2008)
藤沢あゆみ「「愛され社員」で行こう! 」、日本実業出版社(2008)
お薦め度:★★★★
『モテ本』でおなじみの、自称「恋愛・自己実現分野の作家」、「恋愛マニアリーダー」の藤沢あゆみさんが書いたビジネス本。発売されたころにさっと目を通したが、ちゃんと読んでみたいとずっと思っていた本。
 中西 雅之「対話力―なぜ伝わらないのか、どうすれば伝わるのか」、PHP社(2008)
中西 雅之「対話力―なぜ伝わらないのか、どうすれば伝わるのか」、PHP社(2008)
お薦め度:★★★1/2
この本の中核になっている仮説はコミュニケーションの問題は対話力不足にあるというもの。この仮説、みなさんはどう思われるだろうか?僕は今、もっとも必要なコミュニケーション能力だと思う。
 北川達夫、平田オリザ「ニッポンには対話がない―学びとコミュニケーションの再生」、三省堂(2008)
北川達夫、平田オリザ「ニッポンには対話がない―学びとコミュニケーションの再生」、三省堂(2008)
お薦め度:★★★★★
今、世界でもっとも注目を浴びているフィンランド教育を日本に紹介したことで有名な北川達夫氏と、演出家であり、演劇での経験をベースにしたコミュニケーションの教育・研究に携わっている平田オリザ氏のコラボレーション本。
教育、コミュニティ、対話などの視点から、コミュニケーションについての「対話」により、極めて深い洞察をしている。200ページほどの中に、今、日本に必要なものが凝縮されてぎっしり詰まっている。
特に、グローバルな社会では「対話力は生きる力」だといい、欧米においては、これがないと生きていけない「キーコンピテンシー」であるという。そして、「子供たちや若い世代の人たちに必要なコミュニケーション力」とは、「論理的に考えて、論理的に相手に伝える力」だとあまり前のように考えらているがそうではなく、「もっと日常的で、お互いの価値観をすり合わせていくようなコミュニケーション能力」だという。
本の作り方もたいへん、うまく、はっとさせられるようなメッセージがどんどん出てくる。2人の対話を読んでいくと同時に、このひとつひとつのメッセージを熟考しながら読んでほしい本だ。
あとがきに、北川氏がこんなことを書いている。
「もっとよく考えろ」というのは、「自分の頭で考えろ」という場合よりも、むしろ、「まわりの考えに合わせろ」という場合の方が多いのではないか
この指摘がこの本のエッセンスだといえる。「考える力」の重要性を説く人は多い。しかし、そこに託されている思いが北川氏の指摘のようになっていることは明らかである。本書でもさんざん繰り返されているように、今の社会では価値観の共有を前提とすることはナンセンスである。だとすると、いくら考えてみたところで「まわりの考えに合わせる」ことなどできないのだ。
この本は僕にとって一言一句まで舐めるように読みたい本だが、その中でもビジネスで特に重要だと思った話が2つあるので、紹介しておく。
ひとつは、重層性の話である。かつての地域社会には重層性があったという。学校では教師と保護者の関係があっても、家に帰れば保護者が自治会長である。これが重層性だ。このような重層性があると発言にはリスクが伴う。保護者がモンスターピアレントをやると、自治会のマネジメントで苦労する。こんな関係があったのだが、重層性がなくなってきている。これは、コミュニティだけではなく、会社の中でもそうだ。たとえば、組合活動が盛んだったころは重層性を実現していたが、だんだん、なくなってきた。ビジネスマンは仕事における重層性を持たなくてはならない。
もう一つは、シンパシーではだめで、エンパシーが必要だという話。
シンパシーはその人の気持ちになって考えることであり、エンパシーは「その人だったらどう感じるか」と考えること。ビジネスに情は必要だが、シンパシーでなんとかなっていた時代は終わった。企業の中にさまざまな価値観が渦巻いているからだ。こうなるとエンパシーを持てないと乗り越えていけない。
この2点を含めて、本当によい本だ。ぜひ、読んでみてほしい!
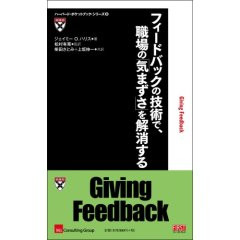 ジェイミー・ハリス(松村有晃監訳、柴田 さとみ、上坂 伸一訳)「フィードバックの技術で、職場の「気まずさ」を解消する」ファーストプレス(2008)
ジェイミー・ハリス(松村有晃監訳、柴田 さとみ、上坂 伸一訳)「フィードバックの技術で、職場の「気まずさ」を解消する」ファーストプレス(2008)
お薦め度:★★★★★
上司による部下の指導方法としてコーチングや対話が注目をされているが、もっと、基本的な指導方法として古くからあるのがフィードバックである。フィードバックというと、ちょっとした注意をするとかで、単純なものだと思われているが、この本は新書とはいえ、100ページ以上にわたり、フィードバックという比較的、地味なテーマについて書いた本である。著者は組織変革のコンサルタント。
著者は、フィードバックがうまくいかないのは、知識とスキルの欠如だと言い切り、それを補う一冊として位置づけている。まず、著者が指摘するのは、フォードバックの位置づけで、フィードバックと「審判」を混同し、受ける側は否定的なメッセージを遮断しようとし、与える側は健全な職場環境を壊したくないと考え、それでうまくいかないと指摘する。
フィードバックを正しく行うためには
・必ずしも否定的なものではない
・一方的な独白ではない
・取っ組み合いのけんかではない
・個人を攻撃する手段ではない
・それだけが唯一正しい意見というわけではない
を念頭におき、好ましい行動や問題解決を推奨、強化する(ポジティブフィードバック)、あるいは、望ましくない行動、問題解決を修正・改善し、新しい行動パターンへの対処を学ばせるために行うものだというのが著者の主張である。
さらに重要なのは、フィードバックは部下に対するものではなく、同僚、上司などすべての人に対して有効であることを指摘している。
この本では、このようなフォードバックを可能にするための、考え方、ポイント、ツールなどをふんだんに紹介している。また、巻末には自己診断のテストもあるので、自分の傾向をつかみ、自分に適したツールを使って、フォードバックスキルを向上させることができる素晴らしい本である。
冒頭に書いたように、フォードバックを100ページも使って説明しているというのは、逆にいえば、非常に詳しい。実践的であり、なおかつ、具体的である。また、単調なフィードバックの説明ではなく、最近、問題になっている職場の雰囲気の改善に当てているので、飽きずにさっと読めるのもよい。
本書は、パーバード・ポケットブック・シリーズの第8巻である。地味なテーマであるが8冊の中でもっともお薦めできる本だ。
 ロバート・サットン(矢口誠訳)「あなたの職場のイヤな奴」、講談社(2008)
ロバート・サットン(矢口誠訳)「あなたの職場のイヤな奴」、講談社(2008)
お薦め度:★★★★1/2
原題:No Asshole Rule
この10年間で僕が影響を受けた本の1冊は、ロバート・サットンの「The Knowledge Doing Gap」である。この本は、組織における成員の知識と行動のギャップについて問題指摘をし、解決方法を提案したものである。日本では、この本は2000年に一度、「変われる会社、変われない会社―知識と行動が矛盾する経営」として流通科学大学出版より出版され、2005年に講談社から「実行力不全」のタイトルで復刊されている。
専門は組織行動論、組織管理論、イノベーション理論などを専門とするサットン教授が、心理的な側面から描いた組織論である。
そのサットンの新作がこの本。実行力不全よりももう少しミクロな視点で、個人の行動と人間関係に注目してどのように対処するかを通じて、組織をどのように運営していけばよいかを語っている。
たとえば、こんなひとがでてくる。
・人の神経を逆なでするひと
・いるだけでまわりにダメージを与えるひと
・自分より弱い相手をいじめる
・ときには取引先にも被害をおよぼす
誰もが、自分のことも含めて、心当たりがあることばかりではないかと思う。その意味で、平社員は自身の行動マニュアルとして読むことができ、管理職は組織運営マニュアルとして読める本である。
組織行動論には、ステファン・ロビンスの
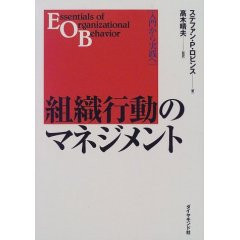 ステファン・ロビンス(高木晴夫、永井 裕久、福沢 英弘、横田 絵理、渡辺 直登訳)「組織行動のマネジメント―入門から実践へ」、ダイヤモンド社(1997)
ステファン・ロビンス(高木晴夫、永井 裕久、福沢 英弘、横田 絵理、渡辺 直登訳)「組織行動のマネジメント―入門から実践へ」、ダイヤモンド社(1997)
という名著がある。この本はマクロアプローチもミクロアプローチの両方について解説しているし、実務家にも研究者やコンサルタントにも支持されている本だ。
サットンの本はもちろん、単独で読んでも役立つが、余裕があればステファン・ロビンスの本を読んでみて、ミクロアプローチのヒントとしてサットンの本を読んでみると一段とサットンの本の価値が上がるように思う。
 酒井穣「はじめての課長の教科書」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2008)
酒井穣「はじめての課長の教科書」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2008)
お薦め度:★★★★1/2
この本を本屋でタイトルを見たときに、おっ!と思った。
手にとり、目次を見たら、期待したとおりのものだった。本書は、スキルと問題解決、社内政治とキャリアの4つを軸に、課長の活動のノウハウを書きあげている。
まず、最初の章は課長の定義をしている。経営的意思決定に対する関与、業務にたいする関与、リーダーシップと管理などの観点から課長とはこういうものであることを説明している。そして、日本の企業では組織の原動力だった課長が、成果主義の普及に伴う組織のフラット化の中で存在が薄くなっていき、今日、また、成果主義の揺り戻しの中で再び重要な役割になってきたという経緯を述べている。まさに同感である。
そして、次の章は課長に必要なスキルということで
・部下を守り安心させる
・部下をほめ方向性を明確に伝える
・部下を叱り変化をうながす
・現場を観察し次を予測する
・ストレスを適度な状態に管理する
・部下をコーチングし答えを引き出す
・楽しく没頭できるように仕事をアレンジする
・オスサイト・ミーティングでチームの結束を高める
の8つが必要だとし、これらについてポイントを解説している。
次に、課長が巻き込まれる非合法なゲームということで
・ポストと予算をめぐる社内政治
について述べて述べ、これを切にけて行くにはどうすればよいかを解説している。
そして、次に課長が直面する9つの問題ということで、問題社員への対処、部下のリテンション、部下のメンタルケア、ダイバーシティ、自身へのヘッドハンティングへの対処、海外駐在とその後のキャリアマネジメント、コンプライアンス、部下の人事評価への対処、ベテラン社員への対処といった問題について処方箋を示している。
そして最終章では、自身のキャリアマネジメントとして、自身の弱点を知る、英語力の強化、緩い人的ネットワークの構築、部長を目指す、課長で骨を埋める、社内改革リーダーになる、起業を考える、ビジネス書を読むといった戦略を示している。
これらの4本の柱は適切だと思うし、その内容もいいことがたくさん書いてある。何よりも、こういう形で課長の活動を体系化した点に価値があると思う。特に、スキルにおいては、課長になって身につけるというものではないと思うので、課長にはこんなスキルが必要だと定義したというのは画期的なことではないかと思う。
また、もう一つ、日本ではあまり社内政治を書いた本がないが、そんなに多くの分量ではないが、課長がもっとも悩む社内政治についての1章を設けているのはたいへん、素晴らしいと思う。
ひとつだけ物足りなさがあるのは、キャリアの扱い方である。スキルにしろ、問題解決しろ、社内政治にしろ、課長レベルになると、キャリアを背景に行わざるを得ない。この点があまり明確にかかれておらず、4つの柱の項目間の関連づけがあまり明示されていない。たとえば、どの部下を評価するなどは、自身のキャリアをかけた判断だし、問題解決の多くは係長のように単に答えを出せばよいという立場にはなく、キャリアをかけた答えを出さなくてはならないことがほとんどではないかと思う。
そう考えると、課長のキャリア戦略というのはもっと奥の深いものがあるように思う。企画意義もあり、内容もよくできた本だし、部分的には著者のそのような意識も垣間見れるので、よけいに残念だ。
ちなみに、僕が15年前に神戸大学の金井壽宏先生のMBAコースのゼミでクラスメートと話をしたときに、三分の二くらいの人は中間管理職のマネジメントについて学びたいと話をしていたのをいまでもよく覚えている。当時、ミドルの問題に強い関心を持つ唯一の先生が金井先生だった(今は、先生の教え子をはじめとして多少増えたが、それでもマイナーだな、、、)
ということで、実は昔から非常に関心の高いテーマ。この本を契機にこのようなニーズにこたえる出版がもっとされるとよいなと思う。本書の著者も書いているが、海外では中間管理職などマネジャーの範疇にないので、この分野の本は日本人が書くしかないな。とりあえず、酒井氏の第2作に期待!
最後に、もう、課長の人はこの本を読めばいいと思うが、これから課長を目指す人は、とりあえず、この本を先に読んでみてはどうかと思う。
 重松 清「ニッポンの課長」、日経BP社(2008)
重松 清「ニッポンの課長」、日経BP社(2008)
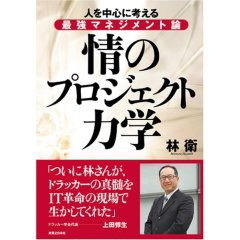 林 衛「情のプロジェクト力学」、日本実業出版社(2008)
林 衛「情のプロジェクト力学」、日本実業出版社(2008)
お薦め度:★★★★
プロジェクトマネジメントというのはマネジメントであり、経験的なアプローチや体系的なアプローチではだめで、そこに人がリーダーシップとコミュニケーションをうまく作用させる必要があることを読み物的に書いた一冊。
こういう話というのは誰も感じていないわけではなく、プロジェクトマネジャーが何人か集まれば、必ずといってよいくらいそんな話になる。井戸端会議的なアジェンダ設定で議論するのは楽しいテーマなのだが、これまで本がなかったのは体系的に整理することが難しいからだと思う。それを見事にやってのけた林衛さんに拍手したい一冊だ!
林さんの考えは、この問題の本質は人であり、人が作る組織である。したがって、如何に人が成長し、それによって組織が成長するかか、プロジェクト成功のカギになるというもの。この体系の中で、プロジェクトの本質を考え抜けとか、丁寧に訊けとか、技術センスを身につけろなどといったさまざまな要素を実にうまく整理している。
その際に、「情」が必要だと言っているところが林さんの真骨頂ではないかと思う。
「これからのビジネスパーソンは、論理を身につけた上で、情の大切さを知り、柔軟な思考で行動することが大切だ」
と言っている。そして、日本人は元来、論理と情をうまく使い分けできるのではないかと言っている。そして、システムが複雑になってくると論理だけではうまくいかなくなると言っている。
頭の中ではこの話は分かる。要するに大規模、複雑化してくると、論理的な整合性を保つのが難しくなるからだ。この下りを読んでいてふと、思ったことがある。それは問題が複雑になってくると、論理と情というマネジメントスキームそのものより、アーキテクチャー(制度、戦略)の問題の方が重要になってくるのではないかということ。
それを痛感するのが今、世の中をにぎわしている道路の問題とか、高齢者医療の問題など。かつてこの種の問題は、官僚が論理を担当し、政治家が情を担当することで全体としてうまくバランスが取れてきた。また、国民もその落とし処に理解を示してきた。ところがうまくいかなくなっている。
たとえば、地方の交通量の少ないところに道路をつくるかどうかという議論はまさにこの典型だ。論理的にいえば、「使われない道路をつくるのは税金の無駄遣いだ」、「今まで税金をプライオリティをつけて使ってきたのだからこれからも粛々とつくるのが正しい」の2つの論理が衝突している。
マネジメントとはこういった対立の解消をしていく仕事である。そこで、政治家が情をばらまく。道路ばかり作っていて病気の人や勉強したい人が困ってもよいのか」、「今までじっと黙って待っていた地域住民の思うがわからないのか」などなど。よけい話がややこしくなる。このような本質的な矛盾はマネジメントでは解決できない。
なぜ、こうなるんだろうと考えてみると、思い当たるのが制度設計(戦略)のまずさである。上のような本質的な論理的な矛盾が起るのは、時間の経緯とか、環境変化によるものではない。道路特定財源制度というのができたときから発生が予想できた問題である。つまり、このコンフリクトの解消はマネジメントではできない話で、制度設計として考えるべき話なのだ。
もう一度、本の話に戻るが、林さんはこの本の第2章で設計センスの話をしている。つまり、マネジメントというのはマネジメントする対象のアーキテクチャー(林さんの本ではシステム、道路の場合は道路特定財源制度)がセンスよく作られていることを前提にして述べているのではないかと思い至った。大賛成である。
であれば、論理と情を使い分けるというのは相当、高度なマネジメントだと言える。特に、相当、質の高い情を持つ必要がある。リーダーはこういうことができるようになりたいものだなと思うが、この本にはそのためのヒントが満載である。
特に、この本のタイトルにある「力学」を使って、「情」のレベルアップをしようという林さんの提案は素晴らしい!ぜひ、読んでみてほしい。
それから、著者へのお願いは、最後にドラッカーのマネジメント論との関係に触れているが、ぜひ、これを一冊の本にしてほしい!
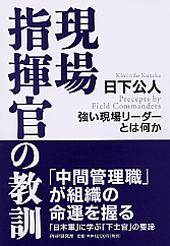 日下公人「現場指揮官の教訓―強い現場リーダーとは何か」、PHP研究所(2007)4569654029
日下公人「現場指揮官の教訓―強い現場リーダーとは何か」、PHP研究所(2007)4569654029
お薦め度:★★★★1/2
軍事や宇宙開発において膨大な国家予算を費やして開発された技術が、やがてビジネスにおいて活用され、競争優位源泉になっているものは多い。意外と目立っていないのだが、戦争の背骨になる戦略と組織(マネジメント)に対しても膨大な投資が行われており、それもビジネスの世界で活用されているものも多い。
ところが日本の軍隊は敗戦を契機に、よくないマネジメントの引き合いに出されることがあっても、よいマネジメントの引き合いに出されることはない。
この本は、多くのエピソードに基づき、日本組織の特徴を下士官に注目してまとめた本である。
この本を読んでみると、戦争というと上意下達、指揮命令系とがビシッとしている軍隊が最適だと思ってしまうが、実際にはそうではなく、下士官という「現場リーダー」がいるからこそ、「現場が動く」という現実があり、また、現場が独自の判断で行った行動に対して上官は見て見ぬふりをするという組織が意外と強いというのがよく分かる。
確かに、戦隊をどう展開するかといった戦略は現場ではどうしようもないのだろうが、現場の見えていない組織(上官)が、戦略ありきで決めたオペレーションをその通りにやるとどうなるかは大体予想できるというものだ。
欧米の軍隊だと、にもかかわらず、そこまできちんと意思決定をすることが求められ、多くの兵士の死と引き換えに上官は地位を失うのに対して、日本は現場がオペレーションの中で現場が調整をしていく。上司は日常はあまり仕事をしていないが、失敗したら責任をとる。このような組織で勝ってきた戦局が多くあることを指摘し、今、組織が機能しなくなってきたのは、下士官の存在がなくなったからだという。
下士官をビジネス組織でいえば、係長、主任、プロジェクトリーダーといったあたりの役回りである。どのような役回りか。この本の中で、米国の研究を紹介した適切な説明がある。
米国のビジネスパースンは1マス、つまり、自分の職務という「縦のライン」で、かつ、1等級分の仕事しかしていない。日本のビジネスマンは自分の職務に隣接する多種類の仕事をしているばかりか、自分の所属等級を含めて上下に三マス分の仕事をしている。つまり、九マス分の仕事をしていることになる。
隣接の仕事はさておき、上下三マスということろがミソである。少なくとも自分の領域では、自分の上と自分の下の役割も兼ねる。多能工ならぬ、多層工である。
これが日本型マネジメントの本質である。もちろん、これは「ホンネ」の部分の話であって、この本の著者も指摘しているように「タテマエ」では上のマスは上司がやっていることになっていなければならないことは言うまでもない。このあたりのヒューマンスキルをどのように軍隊の中で作り上げていたかも紹介している。
その意味で、日本型組織のベストプラクティスを紹介した非常に貴重な1冊だといえる。係長、課長クラスのマネジャーにぜひ読んでいただきたい。
 金井壽宏「やる気!攻略本」、ミシマ社(2008)
金井壽宏「やる気!攻略本」、ミシマ社(2008)
お薦め度:★★★★
実務家向けのMBAコースではケースメソッドが中心になるが、リーダーシップやモチベーションなどのヒューマン系のケースとして最も意味のあるのが、すぐれたリーダーやマネジャーの「持論」であるというのがこの本の著者である金井壽宏先生の考えで、その考えの中で、このブログでも紹介した「働くみんなのモティベーション論」が書かれている。
この本は、その続編として位置づけられた本である。最後に述べるようにこの本の制作過程に多少かかわったのだが、そのときは、そういう話だったので、結構、固めの本だと思っていたのだが、出来上がりを見てびっくりした。
内容的には
(1)モチベーションのケースとしての持論の紹介
(2)持論に関係する理論の紹介
を金井先生自身の経験と、インタビューに基づいてまとめているのだが、それらをロールプレイングゲーム風に見ていきながら、区切り区切りでやる気TIPS(あなたはここでこのような視点を手にいれました)を得るという形で整理しながら、まとめられている。また、最後に、やる気語録が掲載されている。
僕はハウツー本が嫌いなので、ほとんど読まないし、このブログでもほとんど取り上げない。仮に、金井先生が書かれた本でもハウツー本であれば取り上げない。この本をハウツー本だと読んでしまう人もいると思うが、そのように読んでほしくない。この本はやる気を探す旅を本というメディアの中に構築した本だ。TIPSは一種のハウツーだと見えなくもないが、思考のもとであり、それを得たことにより、また、違った視点を持って次の旅に出る。そんな本である。
この本の特徴は、この構成にあるように思う。
モチベーションの本というのはリーダーシップと同じように恐ろしくたくさん出ている。本がたくさん、出ている分野というのは、いろいろな考え方がある分野であると同時に、これといった決定打がない分野でもある。モチベョンもそんな分野である。
この本のアプローチがすべての人に有効だとは思わないが、いろいろなアプローチがあるのなら、こんなアプローチにはまる人もいると思う。
その意味でよい本だと思う。もちろん、内容そのものはフィールドワークでは日本の第一人者の金井先生の作られた本であるので、文句なくよい。エピソードの切り込み方は絶品である。
最後に、この本を作るにあたって、金井先生からの依頼でインターシビューイの1人にならせて戴いた。編集者の方とライターの方が来られ、
人と組織の活性化研究会、加護野忠男、金井壽宏 「なぜあの人は「イキイキ」としているのか―働く仲間と考えた「モチベーション」「ストレス」の正体」
で提案されている「イキイキ・サイクル・チャート」(この本では「やる気チャート」と呼んでいる)を書いてくれと言われて、書けなかった。デコボコがないのだ。
「イキイキ・サイクル・チャート」で落ち込んでいるところから立ち直るまでのところを分析したかったのだと思うが、僕の持論はプロフェッショナルは「やる気に左右されない」ということに尽きるので、やる気を意識しないようにしている。無駄足にしてしまったなと、そんな贖罪の思いを持ちながら読んだ。
最近のコメント