下士官にみる現場リーダーのベストプラクティス
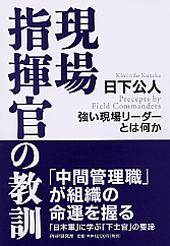 日下公人「現場指揮官の教訓―強い現場リーダーとは何か」、PHP研究所(2007)4569654029
日下公人「現場指揮官の教訓―強い現場リーダーとは何か」、PHP研究所(2007)4569654029
お薦め度:★★★★1/2
軍事や宇宙開発において膨大な国家予算を費やして開発された技術が、やがてビジネスにおいて活用され、競争優位源泉になっているものは多い。意外と目立っていないのだが、戦争の背骨になる戦略と組織(マネジメント)に対しても膨大な投資が行われており、それもビジネスの世界で活用されているものも多い。
ところが日本の軍隊は敗戦を契機に、よくないマネジメントの引き合いに出されることがあっても、よいマネジメントの引き合いに出されることはない。
この本は、多くのエピソードに基づき、日本組織の特徴を下士官に注目してまとめた本である。
この本を読んでみると、戦争というと上意下達、指揮命令系とがビシッとしている軍隊が最適だと思ってしまうが、実際にはそうではなく、下士官という「現場リーダー」がいるからこそ、「現場が動く」という現実があり、また、現場が独自の判断で行った行動に対して上官は見て見ぬふりをするという組織が意外と強いというのがよく分かる。
確かに、戦隊をどう展開するかといった戦略は現場ではどうしようもないのだろうが、現場の見えていない組織(上官)が、戦略ありきで決めたオペレーションをその通りにやるとどうなるかは大体予想できるというものだ。
欧米の軍隊だと、にもかかわらず、そこまできちんと意思決定をすることが求められ、多くの兵士の死と引き換えに上官は地位を失うのに対して、日本は現場がオペレーションの中で現場が調整をしていく。上司は日常はあまり仕事をしていないが、失敗したら責任をとる。このような組織で勝ってきた戦局が多くあることを指摘し、今、組織が機能しなくなってきたのは、下士官の存在がなくなったからだという。
下士官をビジネス組織でいえば、係長、主任、プロジェクトリーダーといったあたりの役回りである。どのような役回りか。この本の中で、米国の研究を紹介した適切な説明がある。
米国のビジネスパースンは1マス、つまり、自分の職務という「縦のライン」で、かつ、1等級分の仕事しかしていない。日本のビジネスマンは自分の職務に隣接する多種類の仕事をしているばかりか、自分の所属等級を含めて上下に三マス分の仕事をしている。つまり、九マス分の仕事をしていることになる。
隣接の仕事はさておき、上下三マスということろがミソである。少なくとも自分の領域では、自分の上と自分の下の役割も兼ねる。多能工ならぬ、多層工である。
これが日本型マネジメントの本質である。もちろん、これは「ホンネ」の部分の話であって、この本の著者も指摘しているように「タテマエ」では上のマスは上司がやっていることになっていなければならないことは言うまでもない。このあたりのヒューマンスキルをどのように軍隊の中で作り上げていたかも紹介している。
その意味で、日本型組織のベストプラクティスを紹介した非常に貴重な1冊だといえる。係長、課長クラスのマネジャーにぜひ読んでいただきたい。

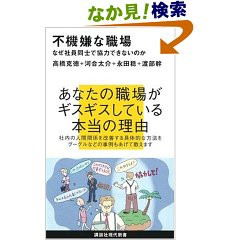
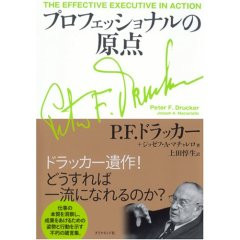
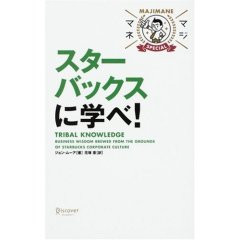
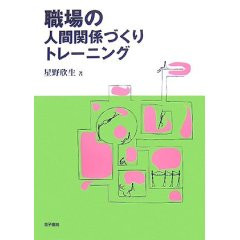
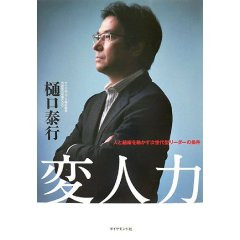
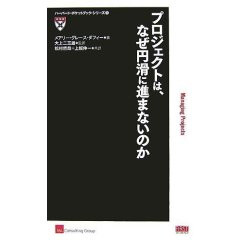

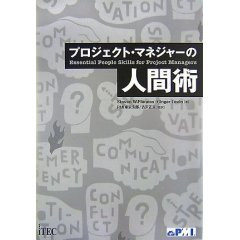

最近のコメント