プロマネ必読の人材マネジメント論!
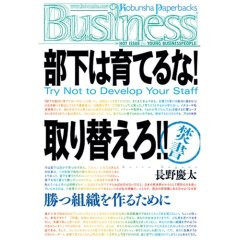 長野慶太「部下は育てるな! 取り替えろ! ! Try Not to Develop Your Staff」、光文社(2007)
長野慶太「部下は育てるな! 取り替えろ! ! Try Not to Develop Your Staff」、光文社(2007)
お奨め度:★★★★
僕は成果主義の一番の問題は、若年層を飼い殺しにしてする組織が増えたことではないかと思っている。マネジャー自身が自分の目標に追われ、長期的な視点で部下を育成するような余裕がない。一方で、米国と根本的に違う点が、部下を「切り捨てででも、成果を挙げようとする」ほどの覚悟もない。
これは一見、温情のように見えるが、結果として、失敗しないようなことだけを部下にさせるというマネジメントをしているマネジャーが多い。これでは、部下はまったく成長しない。作業に熟練するだけである。
こんなことをやっているのであれば、部下を育てることを放棄した方がよい。この問題を正面から指摘した貴重な一冊。
適材適所、捨てる神あれば、拾う神あり。能動的にチャンスを与える。
そろそろ、真剣にこのような発想を持った方がよいのではないだろうか?
■態度の悪い部下はすぐに取り替えろ!
■もう職場に「協調性」なんかいらない
■「エグジット・インタビュー」で情報王になる
■「質問1000本ノック」の雨あられ
■部下がシビれる! 革命上司の「褒める技術」
■「ヘタクソな会議」を今すぐヤメさせろ!
■あなたを勝てるチームのボスにする人事戦略
など、過激な内容が並ぶこの本を読めば、背中を押されること間違いなし。
特にプロジェクトではメンバーを育てようなどを考えないこと。使えないメンバーは切り捨てる。使えると判断すれば、厳しく使う。これによってのみ、次の世代を支えていく人財が育つのではないだろうか?
まあ、非現実的だと思う部分も多々あるが、とりあえず、読んでみよう!プロジェクトマネジャー必見の人材マネジメント論!
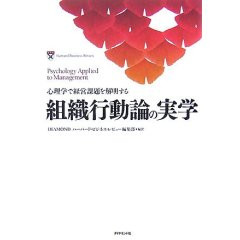
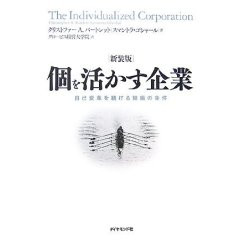
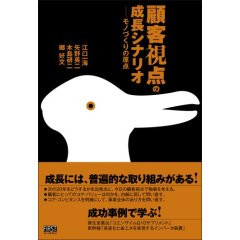
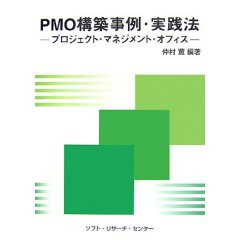
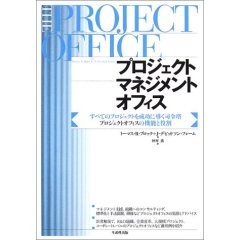
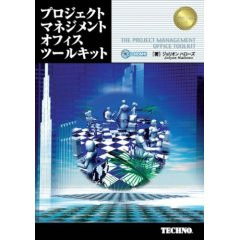
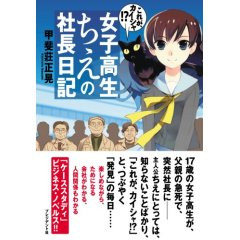
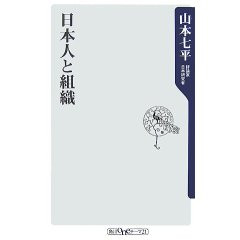
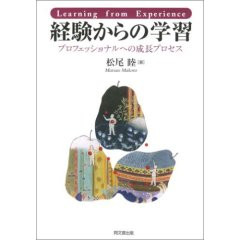
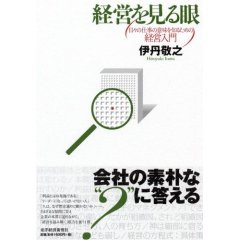
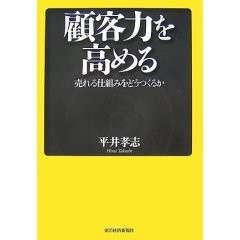

最近のコメント