オーバーアチーブの育て方
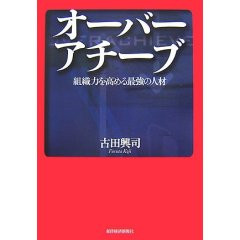 古田興司「オーバーアチーブ、組織力を高める最強の人材」、東洋経済新報社(2007)
古田興司「オーバーアチーブ、組織力を高める最強の人材」、東洋経済新報社(2007)
お奨め度:★★★★1/2
古田氏の前作、「組織力を高める~最強の組織をどうつくるか」のまとめであったオーバーアチーブ(期待を超える)人材の育成が重要だという結論の続き。
オーバーアチーブする人材になるにはどうしたらいいのか、そんな人材を育てるにはどうすればいいのかを具体的に示している。
そのアプローチとして、まず、人材像としてハイパフォーマという人材像を示している。これは
組織の中で働きながら、組織に没頭せず、仕事の質とスピードを追求し
さらには期待を応える結果を出すことにこだわり、
その一方でチームを牽引し、チーム全体の組織力を高める高能力人材
というものだ。このためには、
(1)気概
(2)着眼、解の導出力
(3)チームへの影響力
の3つの要件が必要だという。この本では、この3つの要件をさらにコンピテンシーにわけ、その育成方法を具体的な訓練方法を述べながら解説している。
また、最後にそれらをまとめる形で、6つの基礎トレーニング、4つの実践トレーニングを提案している。
【基礎編】
(1)キャリアプランを考えさせる
(2)新聞を読ませる・朗読させる
(3)本を読ませる・文章を書かせる
(4)人前で発表させる
(5)新しいことを勉強させる
(6)半分の時間でやる練習
【実践編】
(1)役員会の議事録を作成させる
(2)タスクフォースチームを活用する
(3)ウィークリーレポートを書かせる
(4)研修の企画・運営をさせる
感覚的によく合う。特に実践編は効果的な方法だと思う。マネジャーのみなさんも試してみてはどうだろうか?
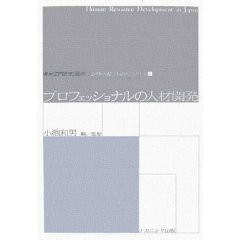
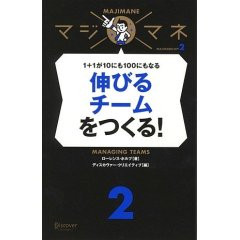
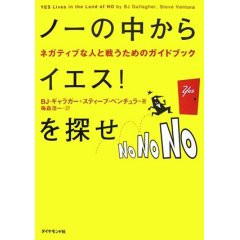
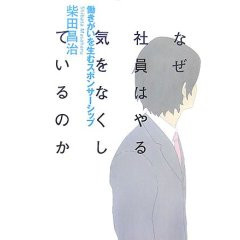
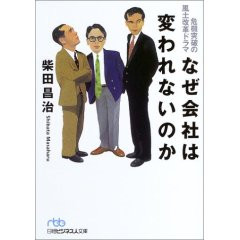
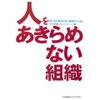


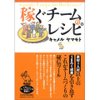
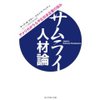

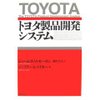

最近のコメント