見えないものを「視える化」する「ハカる」
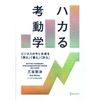 三谷 宏治「ハカる考動学」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2010)
三谷 宏治「ハカる考動学」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2010)
お奨め度:★★★★1/2
三谷 宏治さんの「いまは見えないものを見つけ出す 発想の視点力」でメインテーマのひとつであった「ハカる」ことをだけをとりだし、深めた一冊。ハカることを概念化し、豊富な事例を用いて説明し、エクスサイズを通じて理解を深めることのできる、とてもインスパイアされる本。
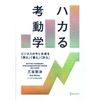 三谷 宏治「ハカる考動学」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2010)
三谷 宏治「ハカる考動学」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2010)
お奨め度:★★★★1/2
三谷 宏治さんの「いまは見えないものを見つけ出す 発想の視点力」でメインテーマのひとつであった「ハカる」ことをだけをとりだし、深めた一冊。ハカることを概念化し、豊富な事例を用いて説明し、エクスサイズを通じて理解を深めることのできる、とてもインスパイアされる本。
 青木 高夫「ずるい!? なぜ欧米人は平気でルールを変えるのか」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2009)
青木 高夫「ずるい!? なぜ欧米人は平気でルールを変えるのか」、ディスカヴァー・トゥエンティワン(2009)
お奨め度:★★★★
本田技研工業の渉外部門に勤務する著者が、税制・国内外の自動車産業のルール作りに参画する中で感じていることや、調べたルールに関する薀蓄をまとめた本。国内や国際標準の策定などにかかわる人だけではなく、組織内で組織のルール作りにかかわっている人には非常に重要な示唆があり、ぜひ、読んでほしい一冊。
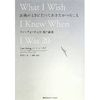 ティナ・シーリグ(高遠裕子訳、三ツ松新解説)「20歳のときに知っておきたかったこと スタンフォード大学集中講義」、 阪急コミュニケーションズ(2010)
ティナ・シーリグ(高遠裕子訳、三ツ松新解説)「20歳のときに知っておきたかったこと スタンフォード大学集中講義」、 阪急コミュニケーションズ(2010)
お奨め度:★★★★★
この本は、スタンフォード大学アントレプレナー・センターのエグゼクティブディレクターであるティナ・シーリングが、自身の体験、創造性開発プログラムでの受講者のパフォーマンス、自分でみた企業の事例など、極めて豊富な事例に基づき、自分への許可をどのように与えるかについて体系的に述べたものである。
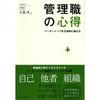 大島 洋「管理職の心得―リーダーシップを立体的に鍛える」、ダイヤモンド社(2010)
大島 洋「管理職の心得―リーダーシップを立体的に鍛える」、ダイヤモンド社(2010)
お奨め度:★★★★★
リーダーシップを、「自己のあり方」、「他者との関わり方」、「組織との向き合い方」という3つの視点から捉え、管理職として効果的なリーダーシップをとるにはどうすればよいかを論じた一冊。フレームワークが適切なので、読めば間違いなくすっきり!
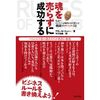 アラン・ウェバー(市川裕康訳)「魂を売らずに成功する-伝説のビジネス誌編集長が選んだ 飛躍のルール52」、英治出版(2010)
アラン・ウェバー(市川裕康訳)「魂を売らずに成功する-伝説のビジネス誌編集長が選んだ 飛躍のルール52」、英治出版(2010)
お奨め度:★★★★★
ハーバードビジネスレビューでマネジメントやビジネスとアイディアを結びつけることを学び、米国でもっとも早く成長した雑誌といれれる「ファスト・カンパニー」を作り上げ、そして、新しいアイデアや方向性を探索する旅をしたアラン・ウェバーが、キャリアの中から厳選した、新しい52の「新たな経験則」を1ルールを数ページでまとめた一冊。52を選んだスコープは本のタイトルでもある「魂を売らずに成功する」ための経験則だ。
すべての解説には、「So What」がついており、コンセプトだけではなく、具体的なアクションのヒントも手に入れることができるのもすばらしい。
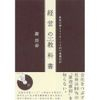 新 将命「経営の教科書―社長が押さえておくべき30の基礎科目」、ダイヤモンド社(2009)
新 将命「経営の教科書―社長が押さえておくべき30の基礎科目」、ダイヤモンド社(2009)
お奨め度:★★★★★
経営の原理原則を30にまとめた本。社長を経験した人が語る原理原則を書いた本は山のようにあるが、この本は、新将命さんという20年以上にわたり、多くの会社で社長を経験された方が、豊富な経験の中で共通的に言えることを体系的にまとめていらっしゃるので、価値がある一冊。30の原理原則を7つのジャンルに分けている。ちょっと長くなるが、記事の最後にリストアップしておく。
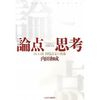 内田 和成「論点思考」、東洋経済新報社 (2010/1/29)
内田 和成「論点思考」、東洋経済新報社 (2010/1/29)
お奨め度:★★★★1/2
3年前に出版された問題解決法の名著
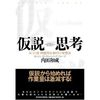 内田 和成「仮説思考 BCG流 問題発見・解決の発想法」、東洋経済新報社(2006)
内田 和成「仮説思考 BCG流 問題発見・解決の発想法」、東洋経済新報社(2006)
の実践編。BCGのコンサルタントが行っている、正しい論点の設定(問題設定)に焦点を当てた問題解決方法を具体的に解説している。仮説思考をどのように使うかもはっきりと分かる。コンサルタントはもちろんだが、経営企画やPMOなど、社内でコンサルティングの業務をしている人は必読の一冊。
 諏訪 良武(北城 恪太郎監修)「顧客はサービスを買っている―顧客満足向上の鍵を握る事前期待のマネジメント」、ダイヤモンド社(2009)
諏訪 良武(北城 恪太郎監修)「顧客はサービスを買っている―顧客満足向上の鍵を握る事前期待のマネジメント」、ダイヤモンド社(2009)
お奨め度:★★★★1/2
近藤 隆雄先生の「サービスマネジメント入門―物づくりから価値づくりへの移行」(1995)が出版されてから15年経つ。この本は、その後、改訂、改版され、2007年に
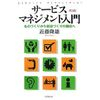 近藤 隆雄 「サービスマネジメント入門第3版―ものづくりから価値づくりの視点へ」、生産性出版 (2007)
近藤 隆雄 「サービスマネジメント入門第3版―ものづくりから価値づくりの視点へ」、生産性出版 (2007)
が出版されている。この間、サービス業のGDPは70%以上を超え、いろいろな問題を抱えているが、体系的に勉強できる本は近藤先生の本だけだった。そこに、「大物新人がやってきた」みたいな雰囲気で、この本が出てきた。
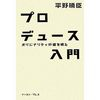 平野 暁臣「プロデュース入門―オリジナリティが壁を破る」、イーストプレス(2009)
平野 暁臣「プロデュース入門―オリジナリティが壁を破る」、イーストプレス(2009)
お奨め度:★★★★★
ビジネス書の杜Award2009は太田芳徳さんの『「決める」マネジメント』を選んだ。太田さんの本は、時代に即した概念をふんだんに取り入れ、また、極めて実践的であるゆえ、この3年間にAwardに選んだ本の中では、もっとも良い本だと思っている。しかし、もし、この本がもう少し、早い時期に出ていたら、相当、悩んだと思う。そのくらい、すばらしいプロデュース論の本。
最近のコメント