プロフェッショナルの16か条
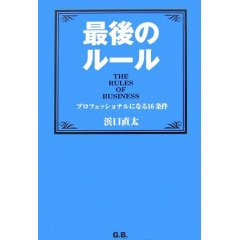 浜口直太「最後のルール―プロフェッショナルになる16条件 THE RULES OF BUSINESS」、ジービー(2007)
浜口直太「最後のルール―プロフェッショナルになる16条件 THE RULES OF BUSINESS」、ジービー(2007)
お奨め度:★★★★
「あたりまえだけどできない」シリーズで一躍名を馳せた浜口直太氏の新著。
ビジネスの最終結論だということで、プロフェッショナルとしての16の条件というのを述べている。目新しくはないが、非常に説得力があるし、はやり、書き方がうまい!各条件について、できそうなことをうまく選んで書いている。動機付けされること間違いなし!
条件★1 仕事に人生をかける
条件★2 不可能を可能にするために限りなき努力をする
条件★3 自分の仕事に誇りを持つと同時に謙虚に言動する
条件★4 先や時代を読んで仕事をする
条件★5 時間より目標を達成させるために仕事をする
条件★6 高い志、理念、目標に向かって邁進する
条件★7 結果に全ての責任を持つ
条件★8 成果によって報酬を得る
条件★9 仕事において甘えがない
条件★10 能力向上のために常に学び、努力し続ける
条件★11 仕事を通して人間性・能力を高める
条件★12 謙虚にかつ貪欲に誰からも学ぶ
条件★13 仕事を通して周りの人に夢と感動を与える
条件★14 仕事のために自己管理を徹底させる
条件★15 尊敬できる人を持ち、その人から徹底的に学ぶ
条件★16 真剣に人材(後輩)を育成している
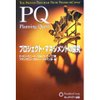
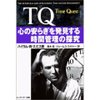
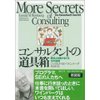


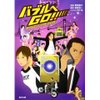
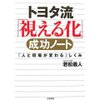
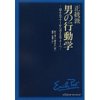

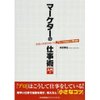
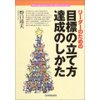
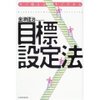
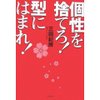
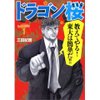
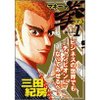


最近のコメント