毎日の小さな実践が大きな変革を起こす
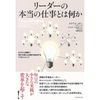 ダグラス・コナン、メッテ・ノルガード(有賀 裕子訳)「リーダーの本当の仕事とは何か――わずかな瞬間で相手の抱える問題を解決する3つのステップ」、ダイヤモンド社(2012)
ダグラス・コナン、メッテ・ノルガード(有賀 裕子訳)「リーダーの本当の仕事とは何か――わずかな瞬間で相手の抱える問題を解決する3つのステップ」、ダイヤモンド社(2012)
お奨め度:★★★★★+α
米国大手食品メーカー、キャンベルスープのCEOとして、急降下していた業績と従業員のやる気を回復させ大きく成長させた評判の著者が、自ら実践して鮮やかな効果をあげた「タッチポイント流リーダーシップ」の本質を語った1冊。
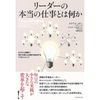 ダグラス・コナン、メッテ・ノルガード(有賀 裕子訳)「リーダーの本当の仕事とは何か――わずかな瞬間で相手の抱える問題を解決する3つのステップ」、ダイヤモンド社(2012)
ダグラス・コナン、メッテ・ノルガード(有賀 裕子訳)「リーダーの本当の仕事とは何か――わずかな瞬間で相手の抱える問題を解決する3つのステップ」、ダイヤモンド社(2012)
お奨め度:★★★★★+α
米国大手食品メーカー、キャンベルスープのCEOとして、急降下していた業績と従業員のやる気を回復させ大きく成長させた評判の著者が、自ら実践して鮮やかな効果をあげた「タッチポイント流リーダーシップ」の本質を語った1冊。
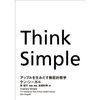 ケン・シーガル(林 信行監修・解説、高橋 則明訳)「Think Simple―アップルを生みだす熱狂的哲学」、NHK出版(2012)
ケン・シーガル(林 信行監修・解説、高橋 則明訳)「Think Simple―アップルを生みだす熱狂的哲学」、NHK出版(2012)
お奨め度:★★★★★+α
facebookページ:「「シンプル」に忠誠を尽し、複雑さと戦う」
アップルの「Think Different」キャンペーンにたずさわり、iMacを命名した伝説のクリエイティブ・ディレクターであるケン・シーガルが初めて明かす、ビジネスとクリエイティブにおける「シンプル」という哲学。多数あるアップル本、ジョブズ本とは一線を画しているのは、ケン・シーガルのデルなど他の企業における経験の紹介がスパイスのように効いている点だ。
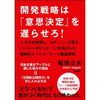 稲垣 公夫「開発戦略は「意思決定」を遅らせろ! ─トヨタが発想し、HPで導入、ハーレーダビッドソンを伸ばした画期的メソッド「リーン製品開発」」、中経出版(2012)
稲垣 公夫「開発戦略は「意思決定」を遅らせろ! ─トヨタが発想し、HPで導入、ハーレーダビッドソンを伸ばした画期的メソッド「リーン製品開発」」、中経出版(2012)
お奨め度:★★★★
facebookページ:「ベールを脱ぐ「リーン製品開発」」
今、注目のリーン手法の中の「リーン」製品開発について、日本に紹介した稲垣公夫さんが一般のビジネスマン向けに解説した本。三部構成で、第1部では、食品加工機メーカ「村坂工業」の成長かリストラかというストーリーで、リーン製品開発のイメージを掴め、第2部が理論、第3部が事例紹介という構成になっている。第1部のストーリーを読んでみて、興味があれば第2部の理論を読み、使えると思ったら、第3部の事例で研究するというなかなか、考えられた構成になっている。
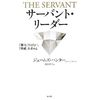 ジェームズ・ハンター(高山祥子訳)「サーバント・リーダー 「権力」ではない。「権威」を求めよ」、海と月社(2012)
ジェームズ・ハンター(高山祥子訳)「サーバント・リーダー 「権力」ではない。「権威」を求めよ」、海と月社(2012)
お奨め度:★★★★★
2004年にPHP研究所から「サーバント・リーダーシップ」のタイトルで出版されたジェームス・ハンダーの「The Servant」の新訳。原書は1998年の出版だが、ちょうど、勉強会で読む機会があり、すごく大切なことを学んだ本。
小説仕立ての本で、世界的なガラスメーカで例をみない若さで工場を任され、順調なキャリアを歩むジェネラルマネジャーが妻から警告され、教会の牧師に相談されることを提案され、牧師から修道院の修道会に参加することを提案される。気乗りはしなかったが、その修道院に伝説の経営者がいることに興味をひかれて、参加する。そして、その伝説の経営者から、リーダーシップを学ぶというストーリー。
 ピーター・シムズ(滑川 海彦、高橋 信夫訳)「小さく賭けろ!―世界を変えた人と組織の成功の秘密」、日経BP社(2012)
ピーター・シムズ(滑川 海彦、高橋 信夫訳)「小さく賭けろ!―世界を変えた人と組織の成功の秘密」、日経BP社(2012)
お奨め度:★★★★★
facebook記事:「素早し失敗、素早い学習を繰り返す」
シカゴ大学のエコノミスト、デビッド・ガレンソンによるとイノベーターには、「概念的イノベーター」と「実験的イノベーター」の2種類がいるという。概念的イノベーターは非常に大胆に新しいアイデアを追求し、多くは若くして業績を上げる。著者は概念的イノベーターの典型としてモーツァルトを上げている。天才であるが、天才はそうそういるわけではなく、多くのイノベーターは実験的イノベーターである。実験的イノベーターは実験を好み、試行錯誤を繰り返す中で徐々にブレークスルーをしていく。彼らは、ゴールに向かうときに、失敗や挫折を恐れずに執拗に努力をする。その代表はエジソンであり、音楽家でいえば、徐々に自分の形を作っていったベートーベンである。
この本は実験的イノベーターがどのように成功をおさめるかを分析している。成功した実験的イノベーターの手法を紹介している。試行錯誤といっても、行き当たりばったりということではなく、むしろ、分析的であり、戦略的である。
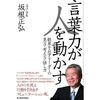 坂根 正弘「言葉力が人を動かす―結果を出すリーダーの見方・考え方・話し方」、東洋経済新報社(2012)
坂根 正弘「言葉力が人を動かす―結果を出すリーダーの見方・考え方・話し方」、東洋経済新報社(2012)
お奨め度:★★★★★
facebook記事:「結果を出すコミュニケーション」
坂根正弘氏は、21世紀に入ってからコマツの業績をV字回復させ、真の意味でグロ
ーバルな企業に育て上げた名経営者である。その坂根会長が、自らの経験に基づいて展開するコミュニケーション論。コミュニケーションという言葉から、多くの人は対人的なコミュニケーション(マンツーマン、あるいはチームコミュニケーション)を思い浮かべると思うが、この本でいうコミュニケーションは組織的なコミュニケーションである。組織的コミュニケーションは、対人的なコミュニケーションほど意識されないが、リーダーは組織的コミュニケーションに熟達し、組織を動かさなくてはできなくては仕事ができない。そのような問題意識を持っている人にぜひ、組織的コミュニケーションの達人の書いた本書をぜひ読んでいただきたい。
 ヴィニート ナイアー(穂坂かほり訳)「社員を大切にする会社 ―― 5万人と歩んだ企業変革のストーリー」、英治出版(2012)
ヴィニート ナイアー(穂坂かほり訳)「社員を大切にする会社 ―― 5万人と歩んだ企業変革のストーリー」、英治出版(2012)
お奨め度:★★★★★+α
facebook記事:「世界でもっともモダンな経営」
HCLテクノロジーズ(以下、HCLT)の2005年からの対話を中心にした企業変革の道のりを、トップリーダーであるヴィニート・ナイアー自身が振り返った一冊。HCLTの変革の特徴は、「従業員第一、顧客第二」というビジョンにある。
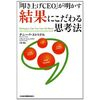 デニー・ストリグル、フランク・スウィアテク(川村 透訳)「「叩き上げCEO」が明かす結果にこだわる思考法」、日本経済新聞出版社(2012)
デニー・ストリグル、フランク・スウィアテク(川村 透訳)「「叩き上げCEO」が明かす結果にこだわる思考法」、日本経済新聞出版社(2012)
お奨め度:★★★★★
電話設置の現場担当からベライゾン・ワイヤレスのトップに上り詰めたデニー・ストリグルのマネジメント論。マネジメントの4大原則を中心に、マネジャーがすべきことをまとめた内容は、非常に実践的であり、具体的である。この紹介記事では、もっとも概念的な指摘をお伝えするが、各項目について、これを1段階~2段階、具体化した内容の書籍であると思って戴けばよい。
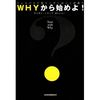 サイモン・シネック(栗木 さつき訳)「WHYから始めよ!―インスパイア型リーダーはここが違う」、日本経済新聞出版社(2012)
サイモン・シネック(栗木 さつき訳)「WHYから始めよ!―インスパイア型リーダーはここが違う」、日本経済新聞出版社(2012)
お奨め度:★★★★
facebook記事:チームをインスパイアする
人をインスパイアすることをテーマに、リーダーシップのあり方を論じた一冊。視点は、WHYから始め、HOW、WHATと考えていくことだ。ジョブズに焦点を当てているわけでもなく、さまざまなリーダーの事例を引き合いに論じられていて、非常に納得性がある。
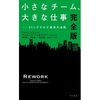 ジェイソン・フリード、デイヴィッド・ハイネマイヤー・ハンソン(黒沢 健二、松永 肇一、美谷 広海、祐佳 ヤング)「小さなチーム、大きな仕事〔完全版〕: 37シグナルズ成功の法則」、早川書房(2012)
ジェイソン・フリード、デイヴィッド・ハイネマイヤー・ハンソン(黒沢 健二、松永 肇一、美谷 広海、祐佳 ヤング)「小さなチーム、大きな仕事〔完全版〕: 37シグナルズ成功の法則」、早川書房(2012)
お奨め度:★★★★★
facebook記事:リワークする
SOHO向けのソフトウエア開発企業として世界的に有名な「37シグナルズ」の創業者ジェイソン・フリードと共同経営者のデイヴィッド・ハイネマイヤー・ハンソンが自らの企業のポリティーをまとめた一冊。会社は大きい方がよいという前提を捨て、どうすればやりがいのある仕事をしながら収益を上げることができるかをメインテーマにしている。
最近のコメント