リーダーシップに「心理学」を生かす

お奨め度:★★★★1/2
この本、お奨め!
本では読めないような論文がずらっと並んでいる。論文といってもそんなに読みにくくはない。素人の僕にはよく分からないが、背景にいろいろな心理学の理論があるのだと思うが、少なくとも表に出てきている内容は、「ほ~」という感じのことばかりで、引き込まれるように読めるものが大半だ。
特に、お奨めは2点。
マイケル・マコビーの「転移の力:フォロワーシップの心理学」。フォロワーシップの特性を転移という現象から議論している。
もうひとつは、エドガー・シャインの「学習の心理学」。学習とリーダーシップ、組織文化の関係を議論している。強制的な説得の怖さを指摘した上で、学習にも組織文化の構築にも強制的説得が必要なことを主張している。
==========
![]() 人気ランキング投票! → クリック!
人気ランキング投票! → クリック!
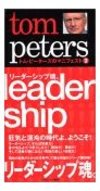
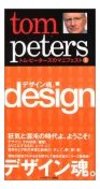













最近のコメント